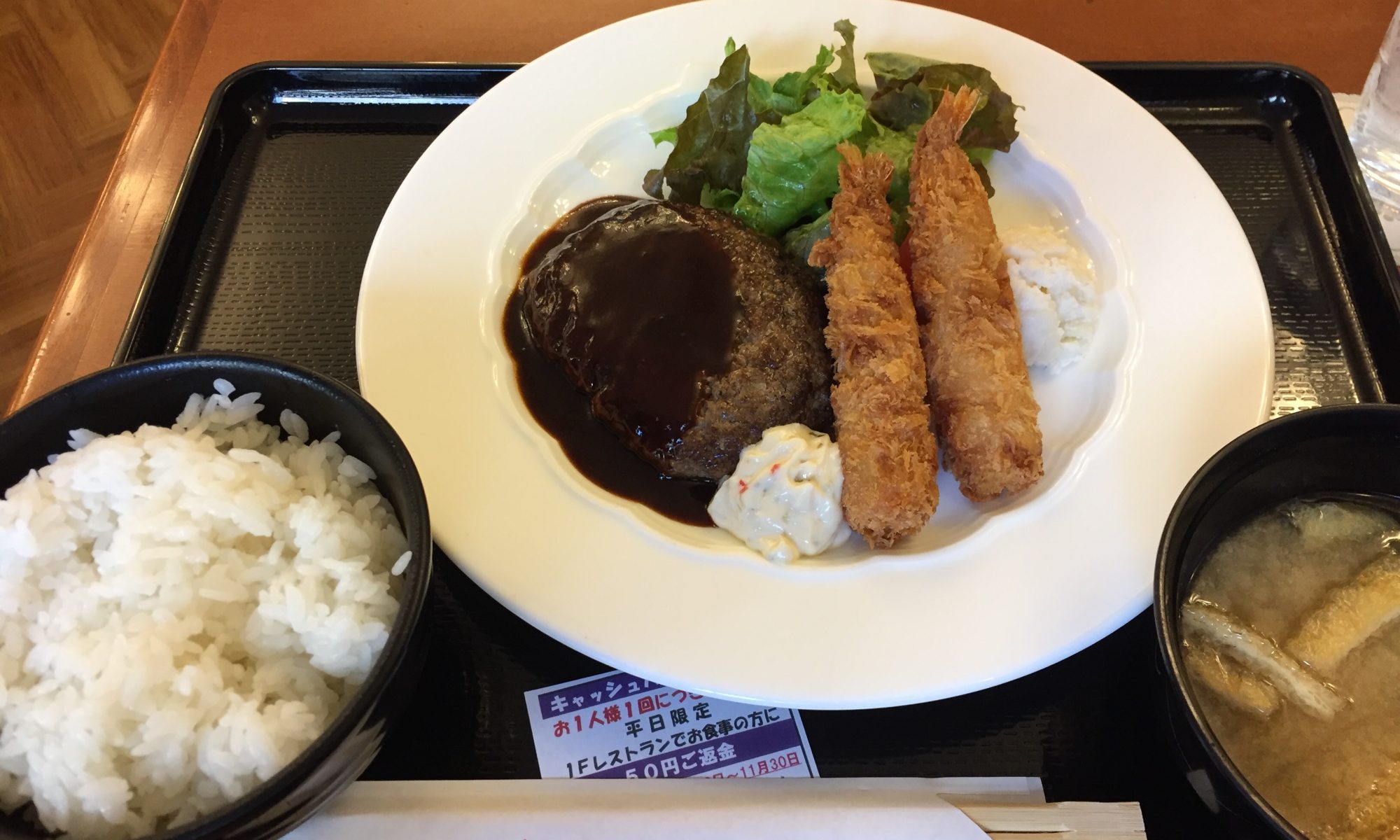出口治明著「還暦からの底力―歴史・人・旅に学ぶ生き方 (講談社現代新書、2020年5月20日初版)を読了しました。
1948年生まれの著者は、60歳でライフネット生命保険を創業して名を成し、70歳で別府市の立命館アジア太平洋大学(APU)の学長に就任した人で、その間、「教養は児童書で学べ」「人類5000年史」など多数のビジネス書や歴史書を出版し、週刊誌にも何本か連載していた方で、「週5~6冊は読む」という読書量も半端ではない。「よくそんな時間があって過労で倒れないかなあ」と心配していたら、今年1月から入院されていて、現在でも病気療養中とのことで、一刻も早いご回復をお祈り申し上げる次第です。
この本は、還暦を過ぎた高齢者向けだけはなく、別に若い人が読んでも十分に通用すると思います。定年後の生き方とか趣味などの指南書になっていないからです。誰でも「今」が一番若く、人生をいかに楽しく充実したものにするか、といった哲学書に近いかもしれません。
ただ、著者の御意見に全面的に賛同することはできませんでした。それは、歴史観の違いかもしれません。歴史観と言っても、「歴史修正主義」とか、そんな大それた問題ではなく、例えば、「西郷隆盛は詩人で夢見る人で永久革命家」「大久保利通は私財を公に投入し、借財を残して死んだので敬愛する」といった著者の断定的な語り口には「そうかなあ」と度々、首を傾げてしまいました。好き嫌いの話になってしまうかもしれませんが、人間はもっと多面的で複雑だと思ったからです。(私自身が、大久保よりも西郷の生き方に惹かれてしまうせいかもしれませんが)

勿論、著者の思想を否定するわけではなく、かなりの部分で共鳴したことは付記しておきます。「子孫に財産を残さず、自分で稼いだお金は自分で使うこと」といった助言は御尤もです。特に、賛同したいのは「教養を磨くには古典を読むに限る」という著者の主張です。出口氏がその必読の古典として取り上げていたのが、以下の6冊です。(著者の名前や出版社、価格は勝手に付け加えました)
1,ベネディクト・アンダーソン「想像の共同体」(書籍工房早山、2200円)
2,イマニュエル・ウォーラーステイン「近代世界システム」1~4(名古屋大学出版会、各5280円)
3、アダム・スミス「国富論」(講談社学術文庫、上・下 計4730円)
4,アダム・スミス「道徳感情論」 (講談社学術文庫、2321円)
5,ジョン・ロック「統治二論」(岩波文庫、1650円)
6,チャールズ・ダーウィン「種の起源」(光文社古典新訳文庫、上・下 計1848円)
いやあ、正直、皆さまとは違って、煩悩凡夫の私自身はこの中で一冊も読んでいませんでした。3~6の古典は著者と書名は知っていましたが、1は全く知らず、2は著者名だけは知っていました。何故、この6冊なのか?
日本人が入っておらず、1,2は米国人、3~6は英国人で少し偏っているも気もしますが、これからチャレンジしてみましょうか。