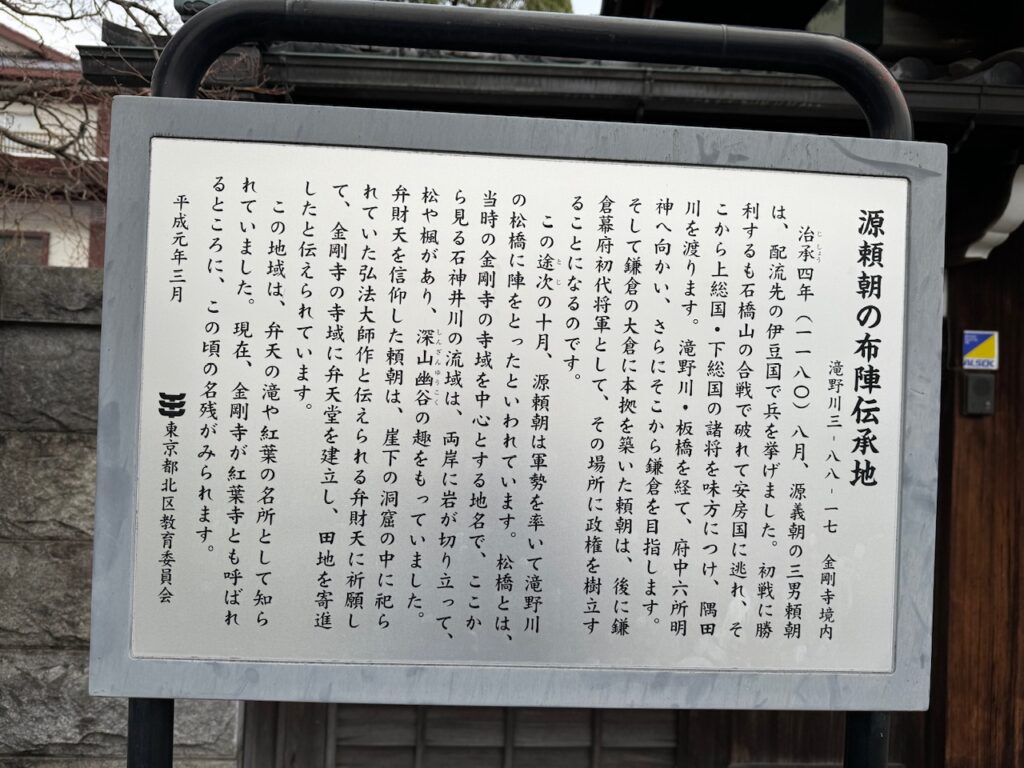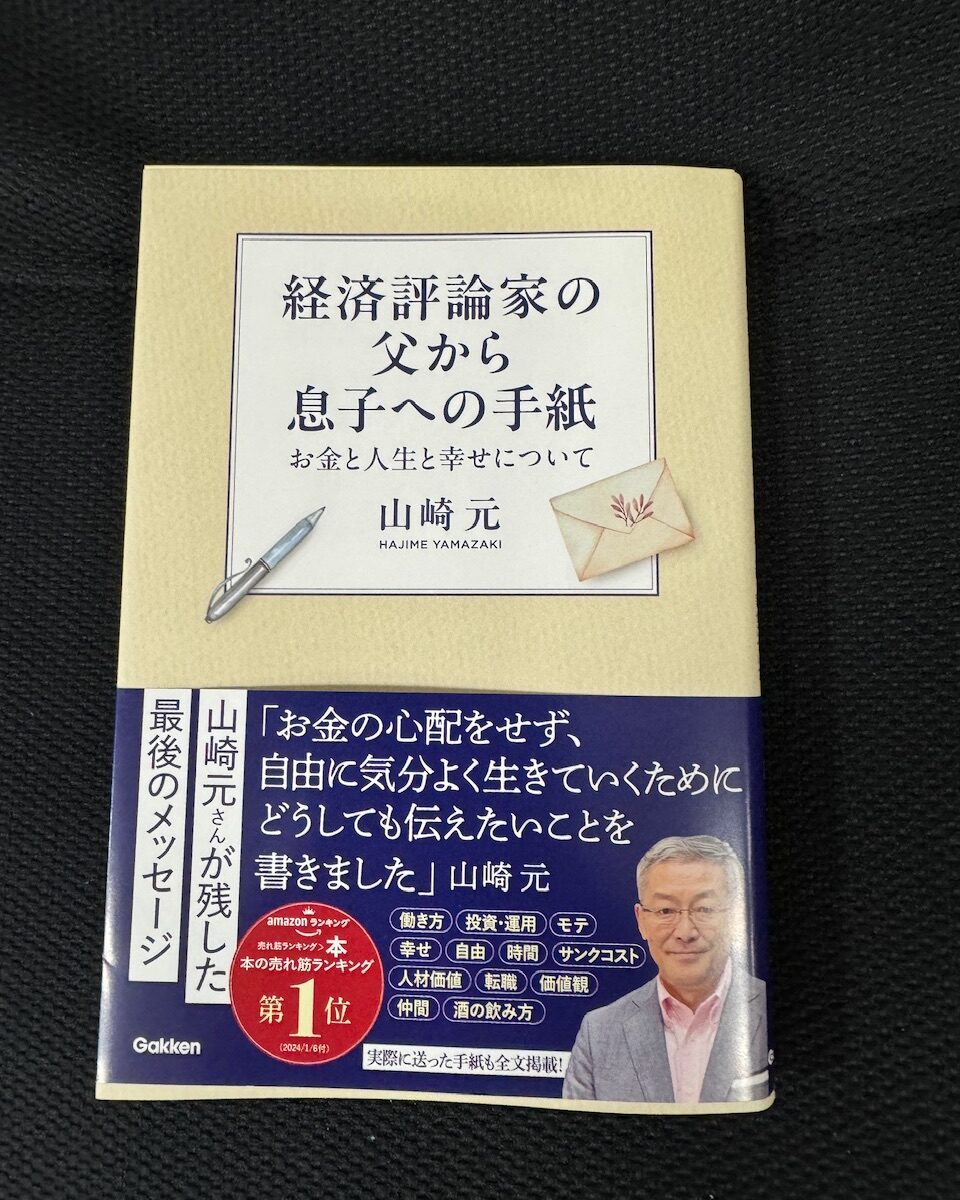私の父方の祖父高田正喜は小学校の音楽の先生でした。明治36年(1903年)10月に佐賀県浜崎町(現唐津市)に生まれ、昭和19年(1944年)9月に亡くなっておりますのでまだ40歳でした。父浩が18歳の時に亡くなっておりますから、当然私は会ったことがありません。序ながら、小松製作所の社員だった母方の祖父岡本五八も明治30年(1897年)5月に生まれ、昭和17年(1942年)12月に45歳で病死しているので会ったことがありません。お爺ちゃんは二人とも知らないわけです。
父方の祖父高田正喜ですが、父親から伝え聞いた話では、佐賀師範学校(現佐賀大学教育学部)を首席で卒業して銀時計をもらったそうですが、卒業後、地元の渕上(ふちのうえ)小学校などで音楽教師を務めた後、昭和6年(1931年)に上京して横浜に出てきて、鶴見の下野谷小学校などに勤めたといいます。よく分かりませんが、当時は、師範学校卒だけでは中学などの上級の教師になれないので、資格検定試験を受けたそうです。祖父は、声が悪かったので、いつも声楽の試験で落とされたそうです。そこで、声を良くしたいと、本当かどうか知りませんが、ナメクジを飲んでいたそうです。
祖父は小学校の生徒を引き連れて、日本放送協会での子ども合唱会のラヂオ番組に出演したことがあったと聞き、昔、私がNHK記者クラブに勤務していた時、資料室に行って確かめてみましたが、見つからず、裏が取れませんでした。

当時、ピアノが家庭にある家はお金持ちでしたが、久留米藩士の末裔で維新後、焼き物店などを開いたものの、「武士の商法」で家計は火の車だったと聞いたことがある高田家にピアノを買う余裕があるはずもなく、祖父が何処でピアノを習ったのかも不明です。同じ佐賀県出身で、小澤征爾のピアノの師だった豊増昇(1912~75年)にも習ったことがあったか、知り合いだったのか、薄っすら父親から聞いたことがありますが、詳しく聞かないうちに父も亡くなってしまいました。
いずれにせよ、音楽教師ともなれば、ピアノは必需品ですから、父親の記憶では、祖父は家に居る時は、朝から晩までピアノばかり弾いていたようです。祖母が「ご飯ですよ」と呼びに行くと、「うるさい!」と言って怒鳴っていたそうです。特に、ベートーベンのピアノ・ソナタが多かったと聞きました。私は特にモーツァルトとバッハ、ブラームスが好きなのですが、クラッシック好きは祖父の遺伝なのかと思っています。
また、クラシックに限らず、私は、ビートルズやジャズ、ボサノヴァなどの音楽が好きで、作詞作曲したりするのも、これまた祖父の血かな、と思っています。
ということで、昨日つくったばかりの新曲”Going back to Rome” も公開することにしました。
“Going back to Rome” composed by Kin-no-souke TAKATA
1,Hey, You run away from home.
I swear it, I’m coming back from Rome.
2,You look so bad,. You’re buried, never to be found.
I’m feeling down. I’m feeling like going outbound.
※ You seem to me how long life to be
But you should remember how short it could be
ちょっと暗い曲なのですが、最近の私のメンタル状況を反映していると思われます(苦笑)。次はもっと明るい曲をつくります(笑)。