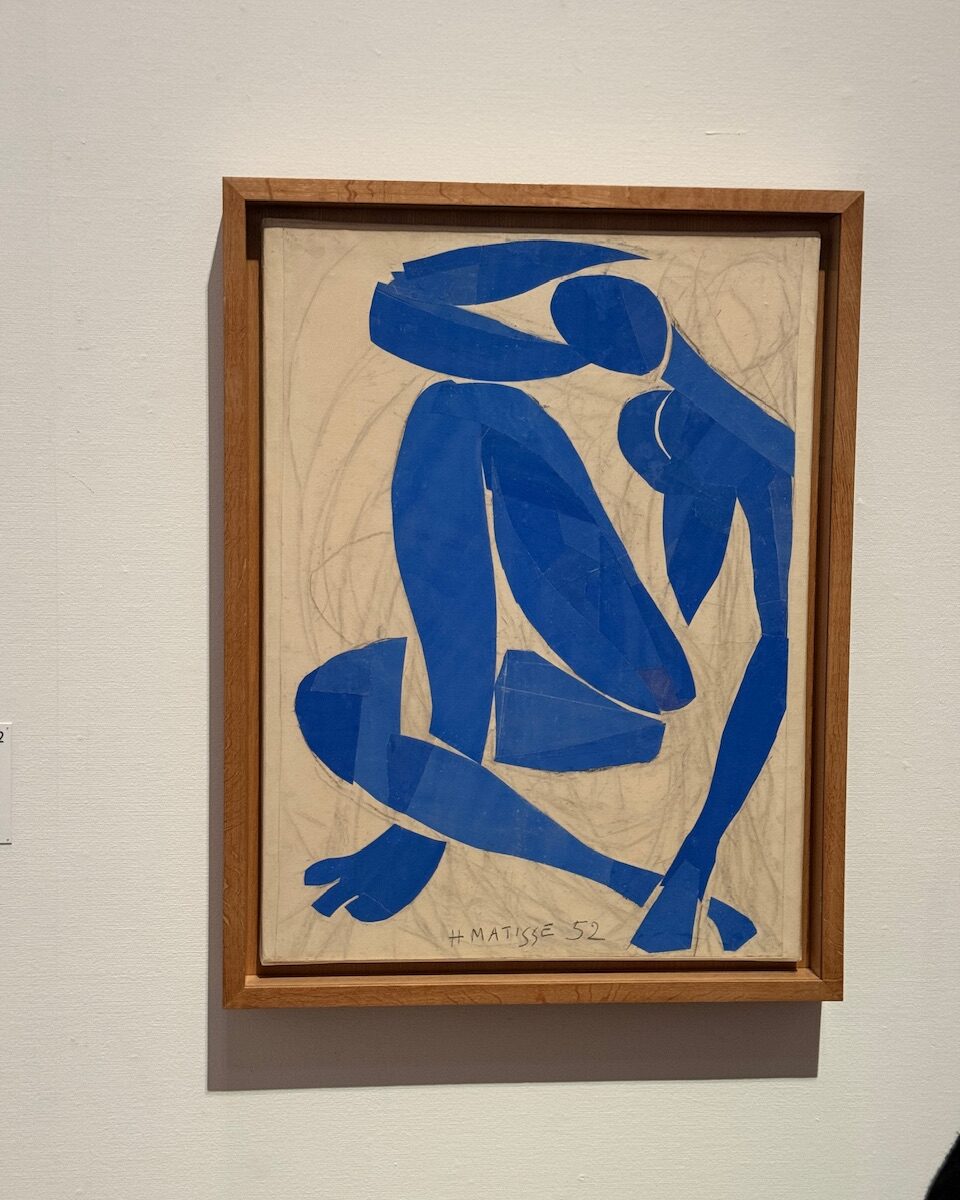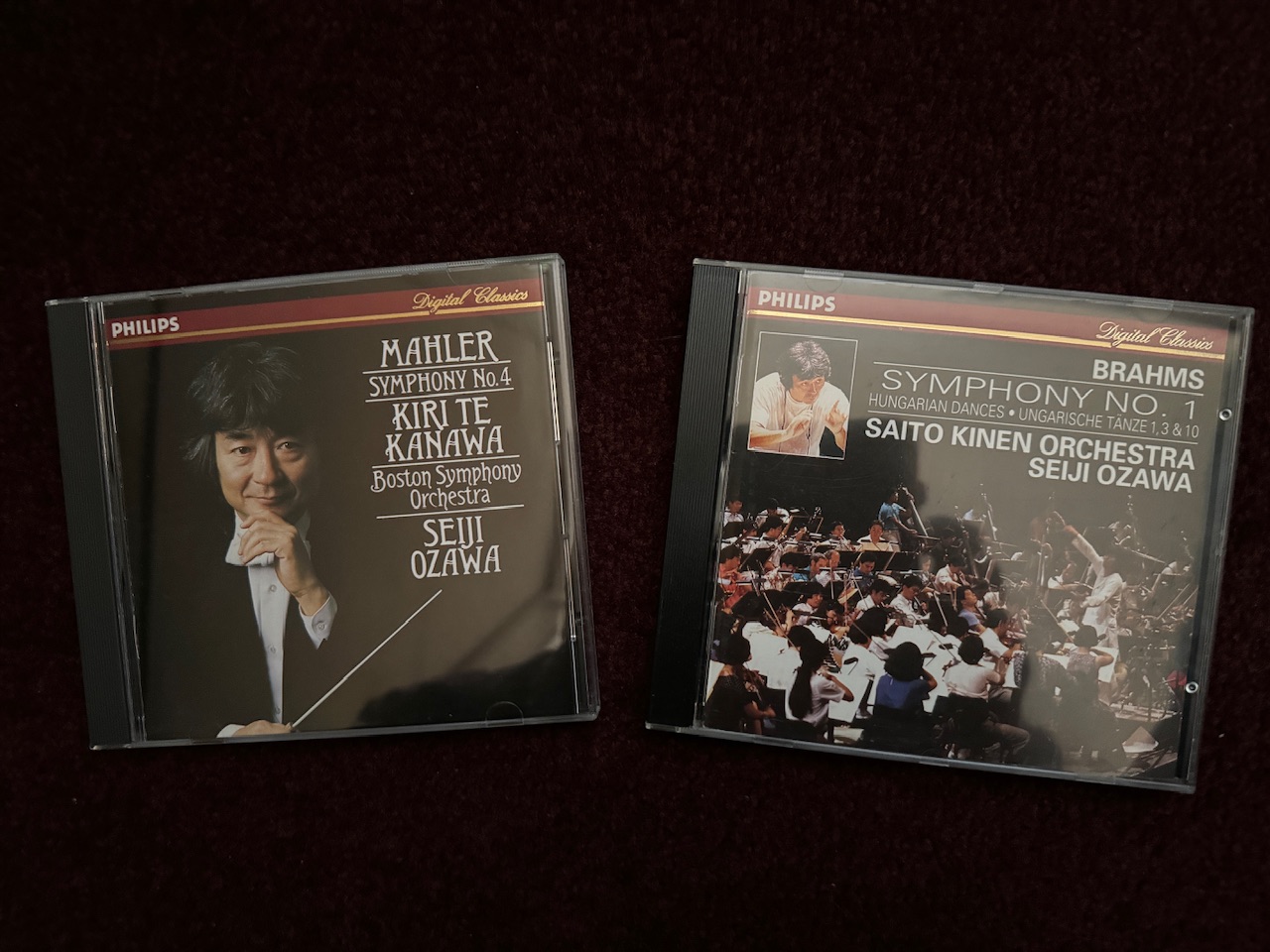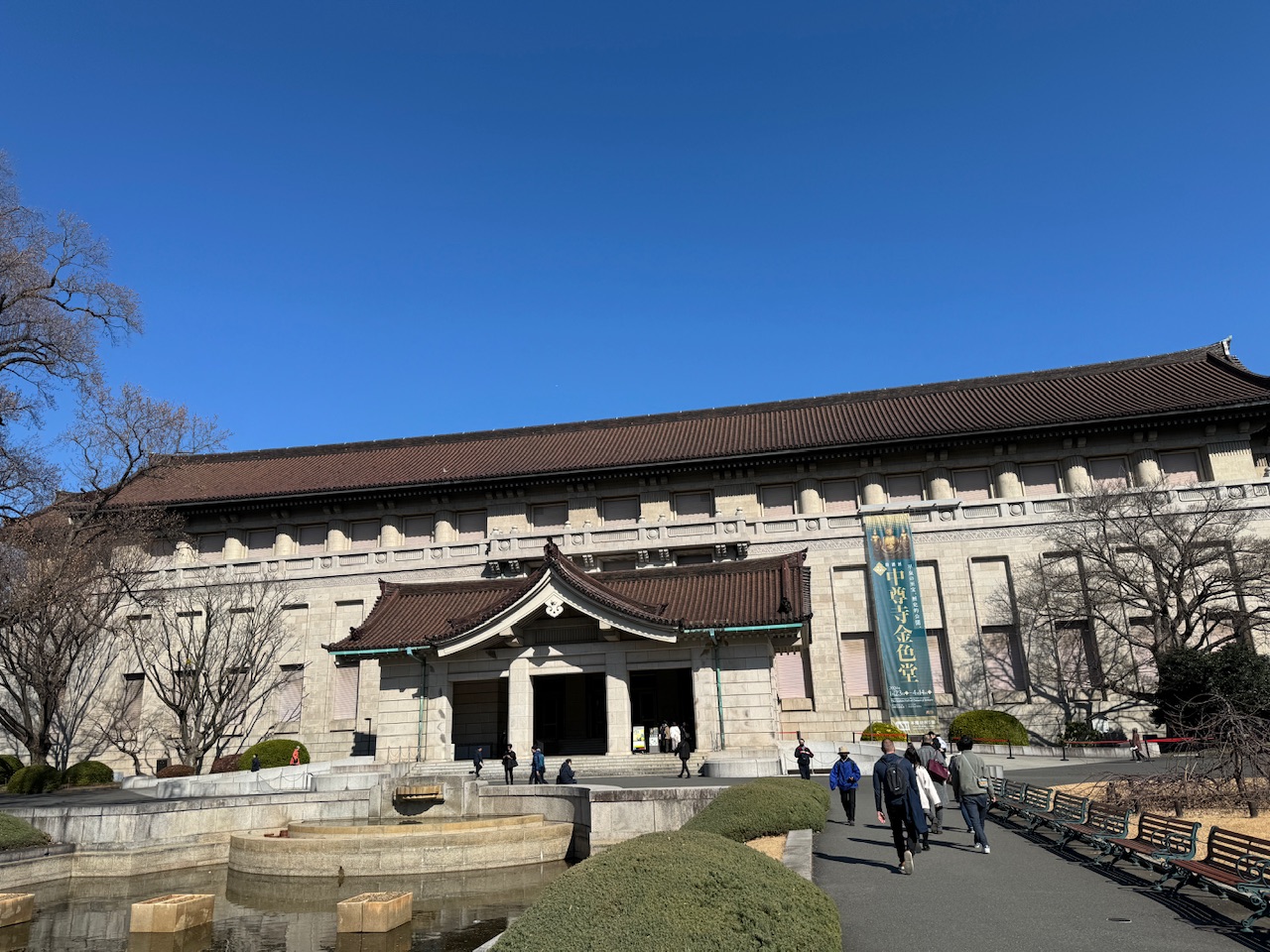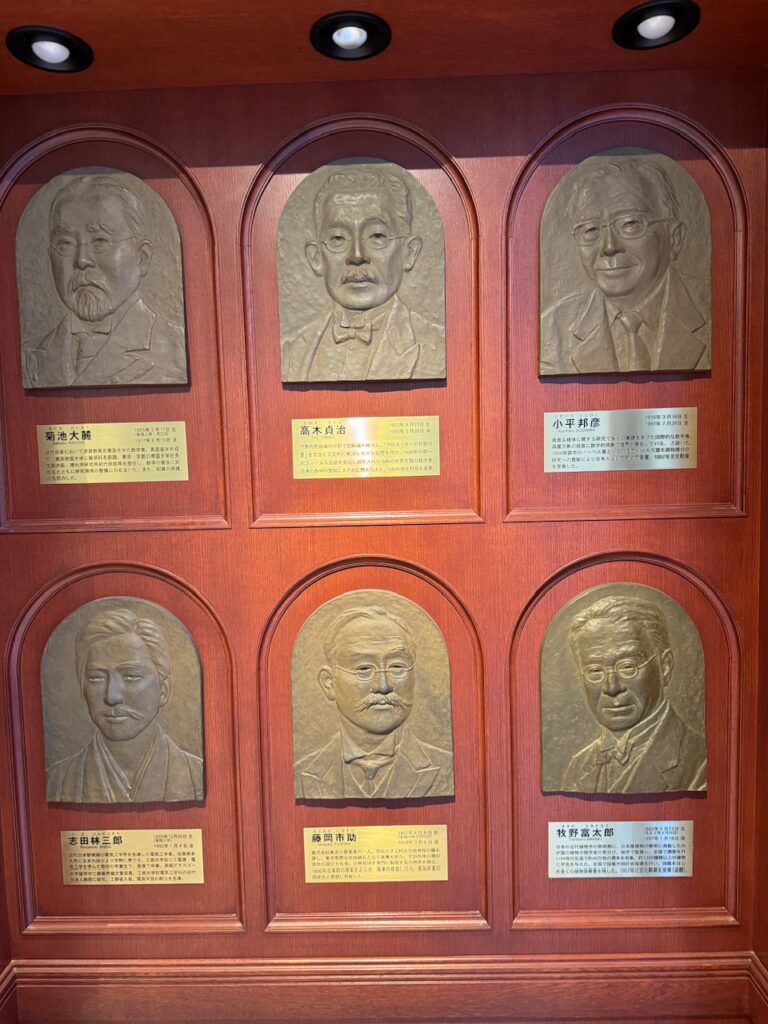ネット時代の昨今では、もう旧聞に属してしまいますが、「ドランゴンボール」などで知られる漫画家の鳥山明さんが、3月1日に急性硬膜下血腫で亡くなりました。行年68歳。
私は、手塚治虫、赤塚不二夫、石ノ森章太郎らの世代ですので、「ドラゴンボール」は一度も読んだことも見たこともありませんが、漫画の累計発行部数は2億6000万部を超え、アニメ化されて世界80カ国・地域以上で放送されたので、世界中に実に多くの熱烈なファンがいたことを知らされました。
何しろ、彼は人気ゲーム「ドラゴンクエスト」のシリーズ1作目からキャラクターやモンスターのデザインを担当したといいますから、世界中で知らない人はいないわけです。私はゲームはやらないので、これまた知りませんでしたが、「ドラクエ」の名前だけは聞いたことがあります。これが、シリーズの累計出荷本数は昨年3月末の時点でダウンロード販売を含めて世界で8800万本に上っているといいますから、つい、著作権料がどれくらい入ってきたのか想像したくなります(失礼!)。
そんな世界的な超有名人なのに、テレビや新聞などで、彼の「顔写真」が20代の1980年代の頃が今更採用されていることに気がつきました。彼はマスコミ嫌いなんでしょうが、それだけ、マスコミのインタビューに応じることがなく、実に地味に暮らしていたということになります。
実際、「Dr.スランプ」が大ヒットした1982年頃(当時27歳)の鳥山さんは「あまりブームにはならなかった方がよかったと思っています。騒がれるのは嫌ですから。地道に漫画だけ描いていたかったです」と、NHKのインタビューに応えています。
やはり、有名になったり騒がれたりするのは嫌いな方だったんですね。漫画を描くことが好きで好きでたまらない「職人気質」の人だったということが分かります。

とにかく露出して、有名になって、CMに出て、お金を稼ぎたいというタレントが多い昨今の風潮とは全く逆です(苦笑)。特に、今の時代はSNSが隆盛で、プロの有名人だけでなく、無名の素人さんでもYouTubeなどで発信して、視聴回数によって莫大なお金が稼げる時代になりましたから尚更です。
鳥山さんはスマートフォンさえも持っていなかったといいます。その話を聞いたのが、この記事を書くきっかけになりました。「ドラゴンボール」も読んだことがないので、私に書く資格はないと思っていましたが、この人は本物です。やはり、「本物」はチャラチャラしていません。流行は追わず、他人と同じようなことはせず、孤立を恐れず、自己の信念を貫き通すことによって初めて「本物」になるのではないでしょうか。