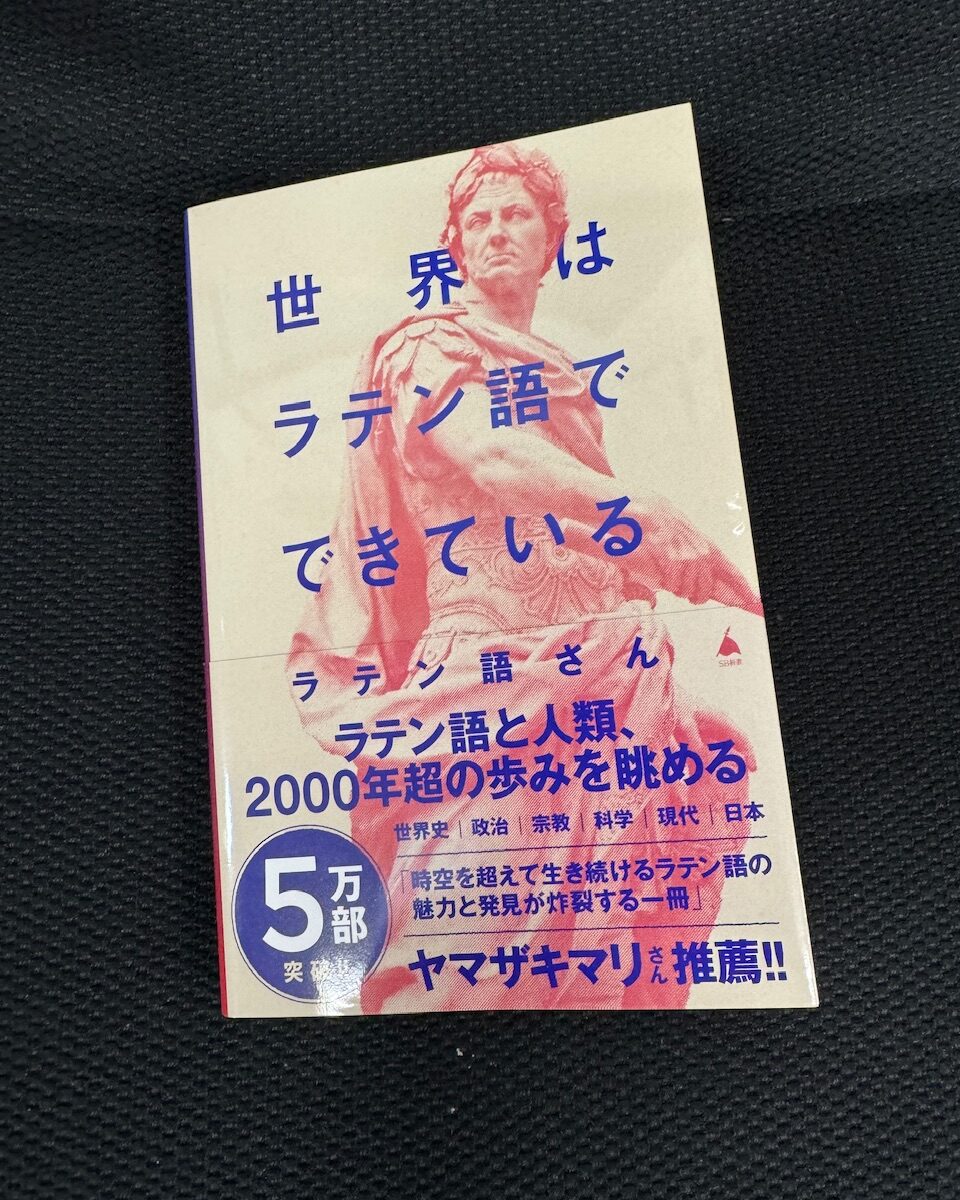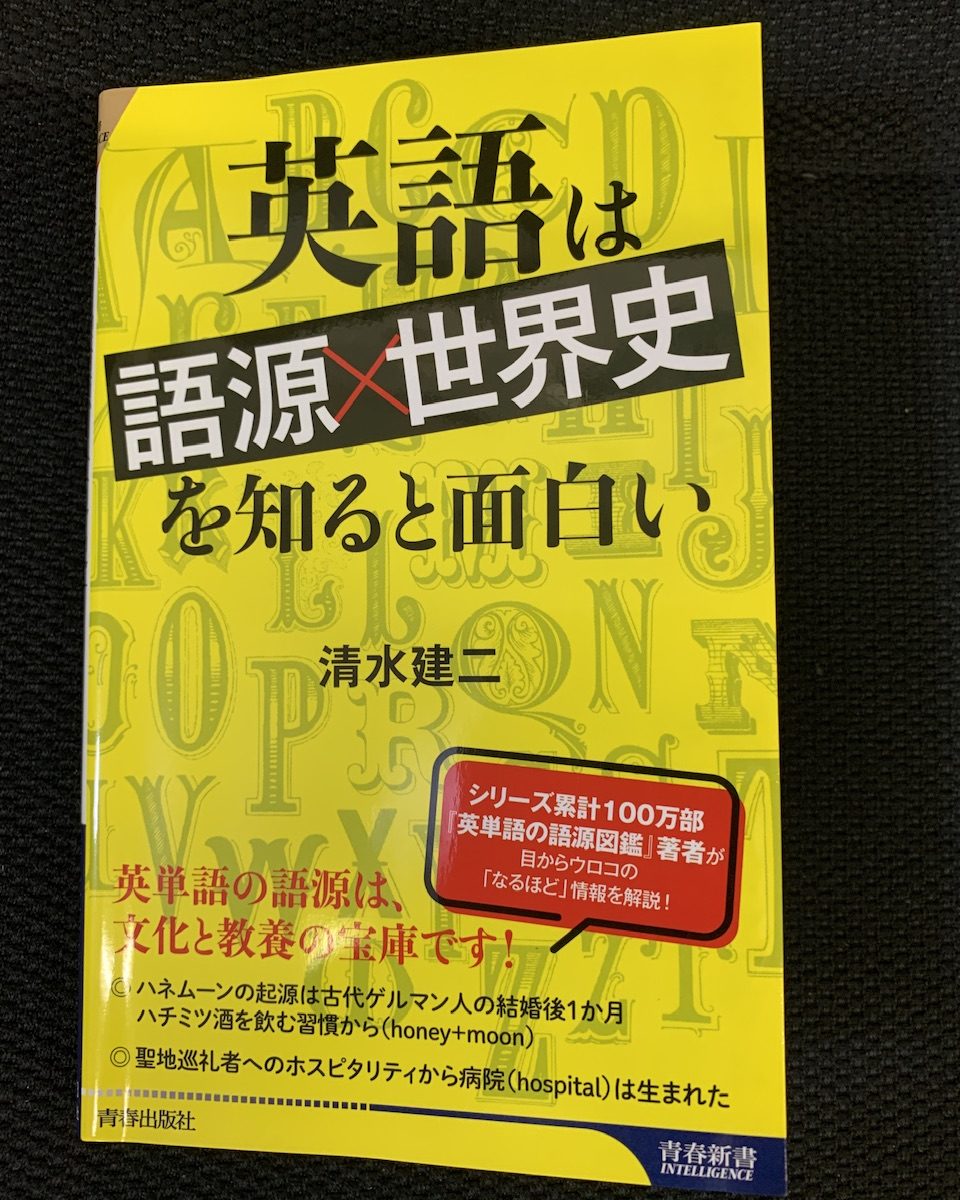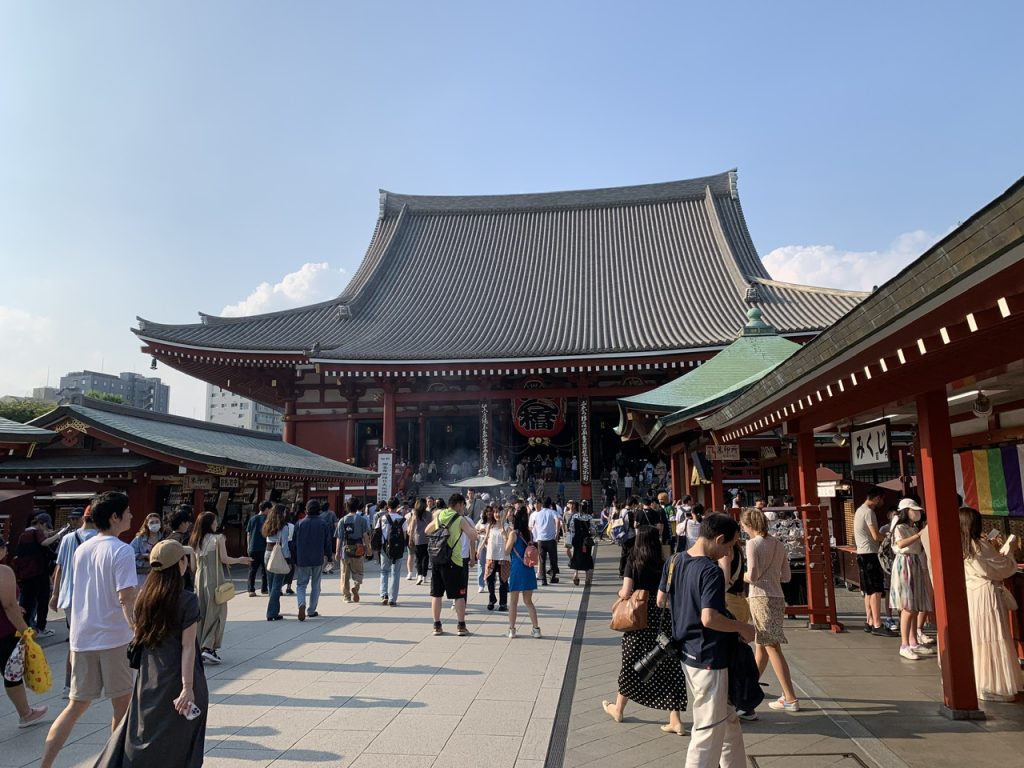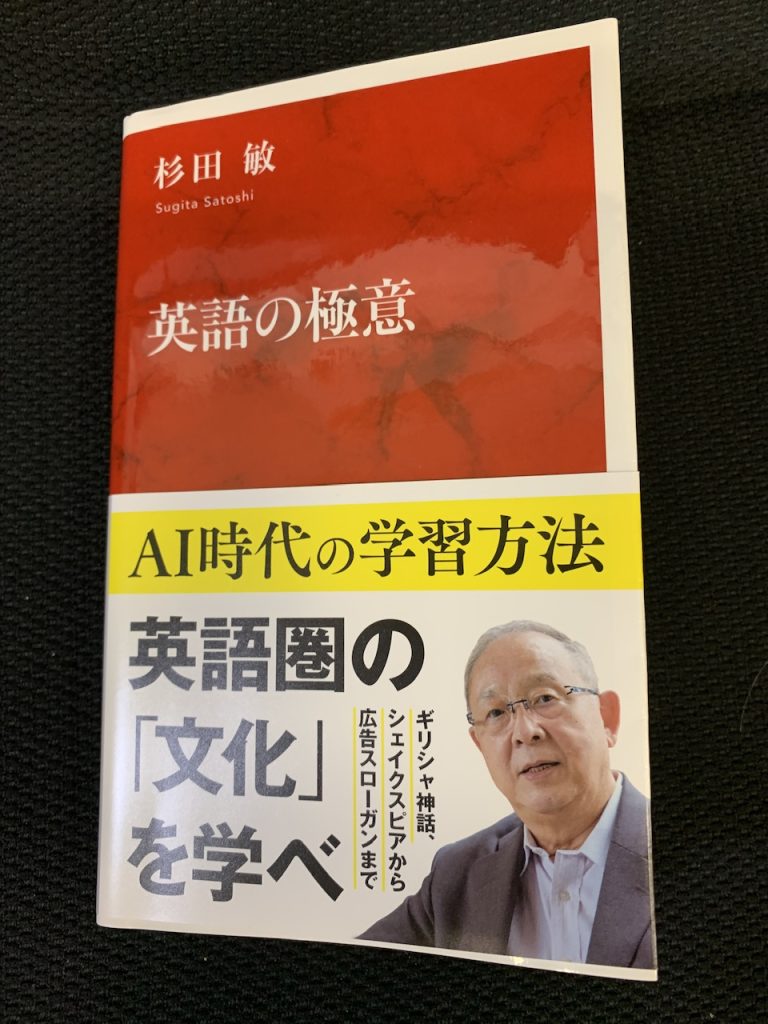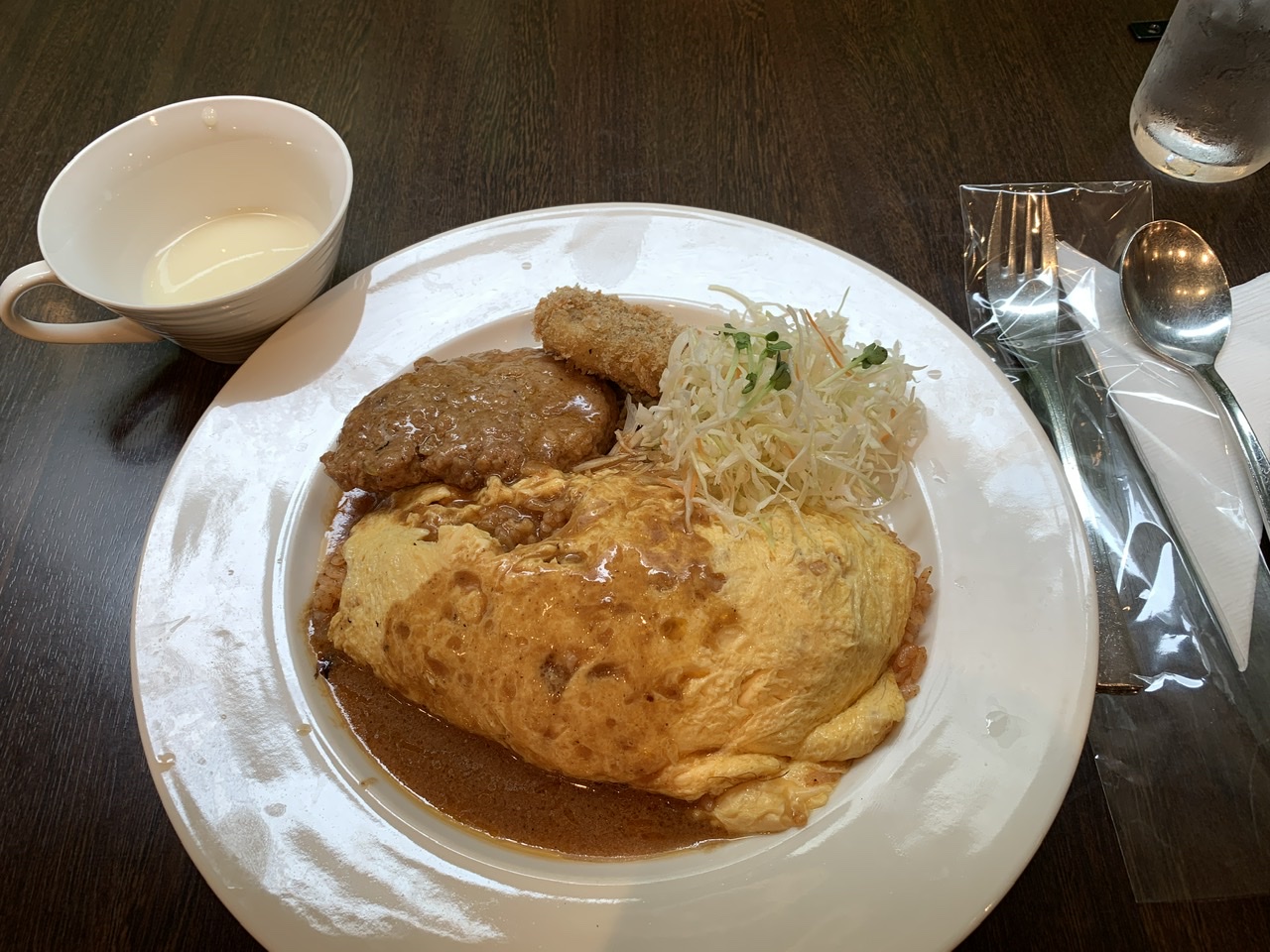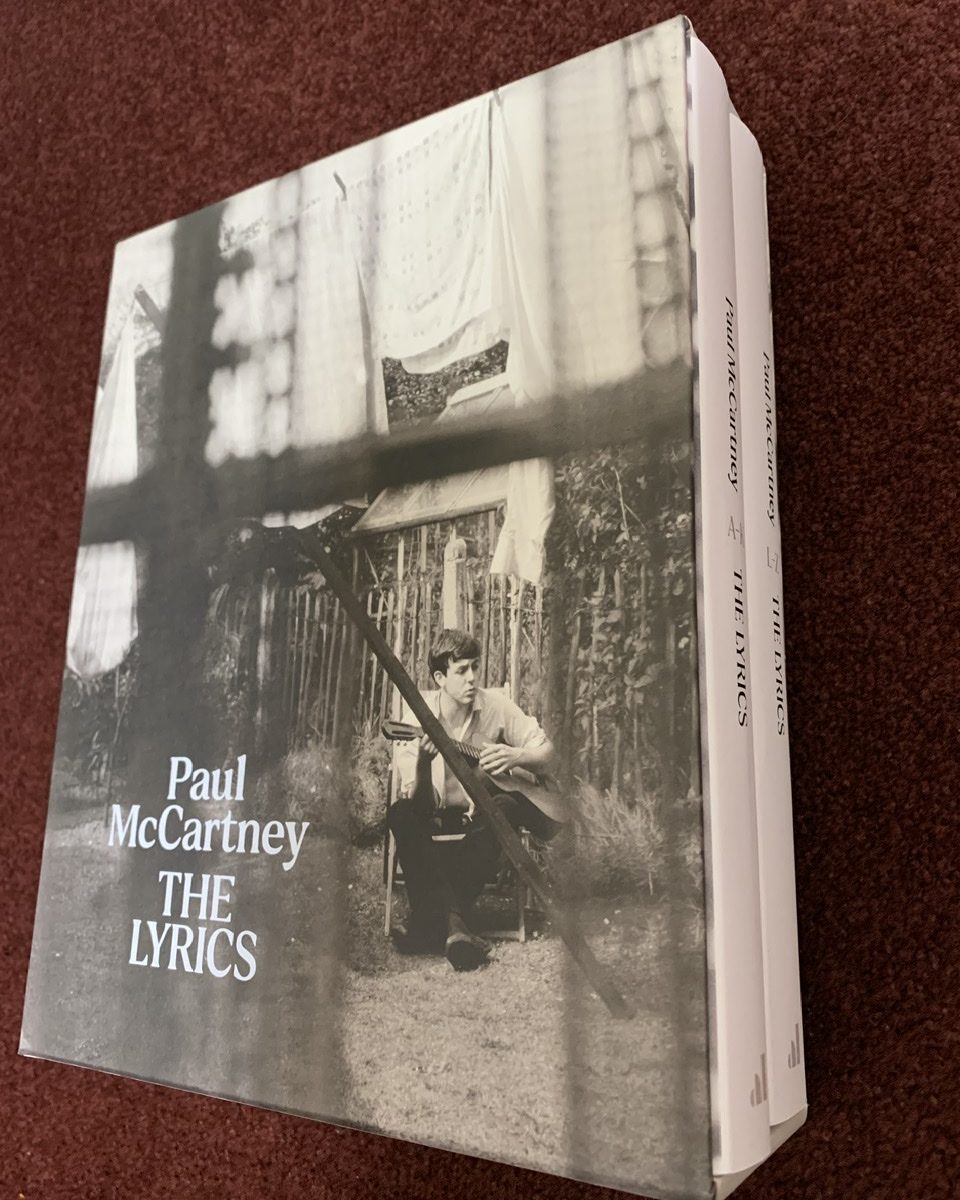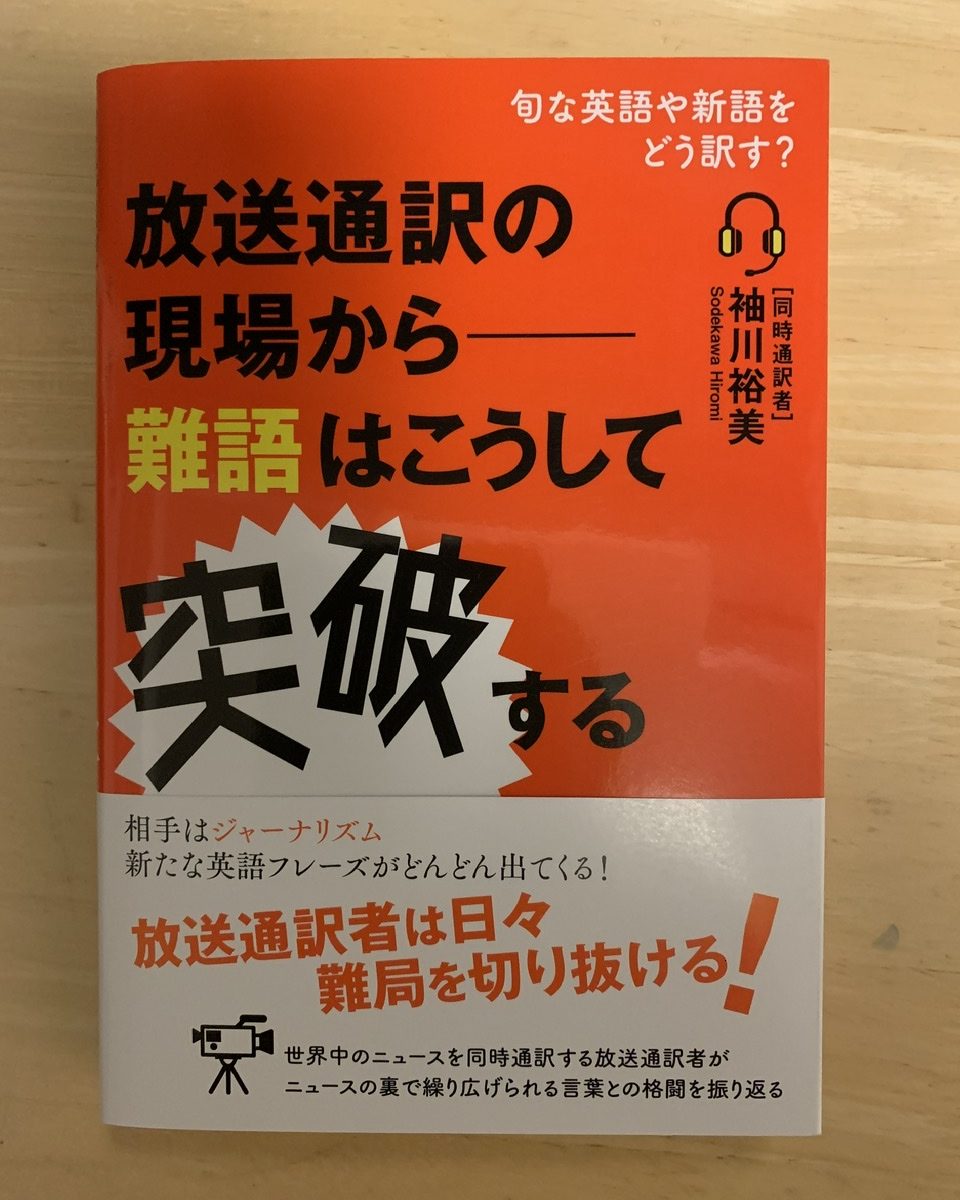今、巷で話題になっている「世界はラテン語でできている」(SB新書、2024年2月26日第5刷、990円)を読んでおります。著者は「ラテン語さん」という人を食ったような命名ぶりですが、ラテン語を高校2年から学び始め、大学は語学専門の東京外国語大学(英語)を卒業されているということで、そして、何よりも「売れている」ということで、書店で山積みになっていたので購入したのでした。
ラテン語は古代ローマ帝国の公用語でしたが、それが後に英語やドイツ語やフランス語やスペイン語などに借用され、現代の世界の言語の「語源」になっている、というのがこの本の趣旨、もしくは肝になっています。
私も学生時代、名著と大変評判だった村松正俊著「ラテン語四週間」(大学書林、初版が1961年!)を購入して独学しましたが、あまりにも難しくて途中で何度も挫折してしまいました。勿論、その本はもう家にありませんが(苦笑)。私も同じ語学専門の大学だったので、ラテン語の選択科目がありましたが、浅はかだったので、敬遠してしまいました。
でも、大学時代は、俗ラテン語を起源に持つロマンス語系と言われるフランス語を学んだお蔭で、間接的にラテン語も勉強した格好になりました。英語だけ学んでいただけでは、駄目ですね。ラテン語は英語よりもイタリア語やスペイン語、仏語の方が「残滓」が残っています。

ラテン語を勉強すれば得するのか?ーいや、別にラテン語を習得すれば商売がうまくいったり、出世したりするわけではありませんので、(例外を除いて)得するわけではありませんけど、知っていても困るわけでもないですし、むしろ、世界が広がるかもしれません。日本語は漢語が語源になっているので、中国語を勉強した方が良いでしょうが、学術用語などで日本語に取り入れられている例がこの本には沢山出てきます。(植物名やホモ・サピエンスなど)
私もラテン語が語源の言葉はある程度知っているつもりでしたが、この本を読むと知らないことばかりでした。
沢山あり過ぎるので、2~3例を挙げますと、money(お金)の語源は、警告者を意味するMoneta(モネータ)が語源です。これは、ローマのカピトリーヌスの丘にあった神殿に女神ユーノー・モネータ(警告者ユーノー)が祀られ、この神殿に貨幣の鋳造所があったため、ということですが、分かるわけありませんよね(苦笑)。
また、ファシズムの語源になったのは、ラテン語のfasces(ファスケース)で「束」を意味します。これが古代ローマでは特別な意味を持つ「束桿(そっかん)」になります。束桿というのは、斧の周りに木の枝を束ねて革紐で縛ったもので、執政官に仕えた警士が携帯し、権威のシンボルになったといいます。(この本ではこのように書かれていませんが、説明が分かりにくかったので、自分で調べて書きました。)
ちなみに、斧はラテン語でsecuris といい、語源はseco(切る)になります。これが、英語のsect(分派)、sector (分野)、section(部門)などの語源になったといいます(本文75ページ)。
キリがないのでこの辺でやめときますが、ラテン語は近世まで欧州各地で使われていたことを特筆しておきます。宗教改革の基になったドイツのマルティン・ルターの「95箇条の論題」(1517年)=私が学生時代は「95箇条の御誓文」と言ってました。また、ルターが糾弾したものは「免罪符」と呼んでおりましたが、最近は「贖宥状」と言うんですか!全然、違うじゃないか!=も、地動説を唱えたポーランドのコペルニクスの「天球回転論」(1543年)も、重力を「発見」した英国のアイザック・ニュートンの「プリンキピア」(自然哲学の数学的諸原理 Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica、1687年)もラテン語で書かれていたのです。

いずれにしても、「世界はラテン語でできている」というのは大袈裟ではなく、幾つも例があるので、驚くばかりです。
ラテン語は日本人にとって、文法がかなり難しいので途中で挫折してしまいますが、文字はローマ字読み出来るので、意外と近しく感じるかもしれません。