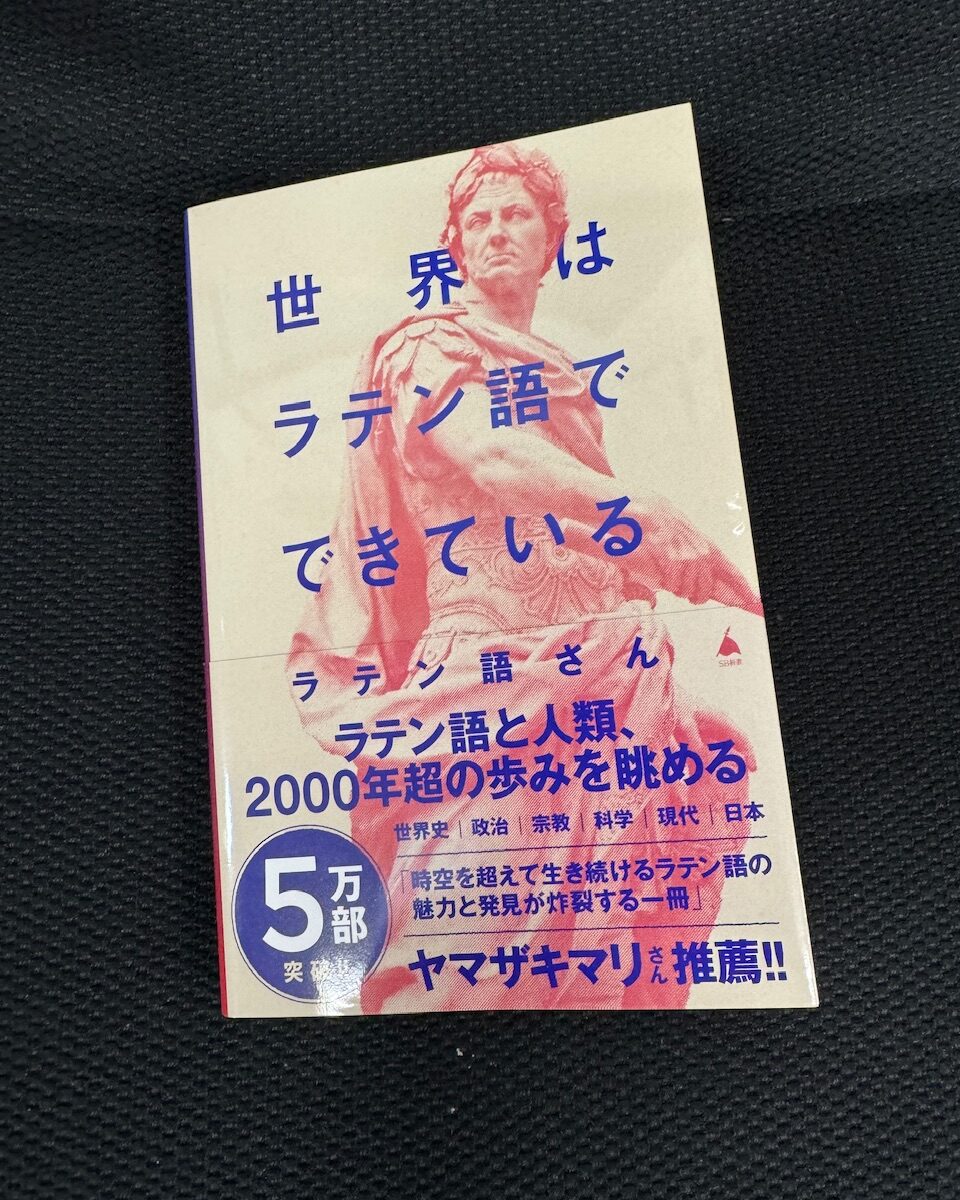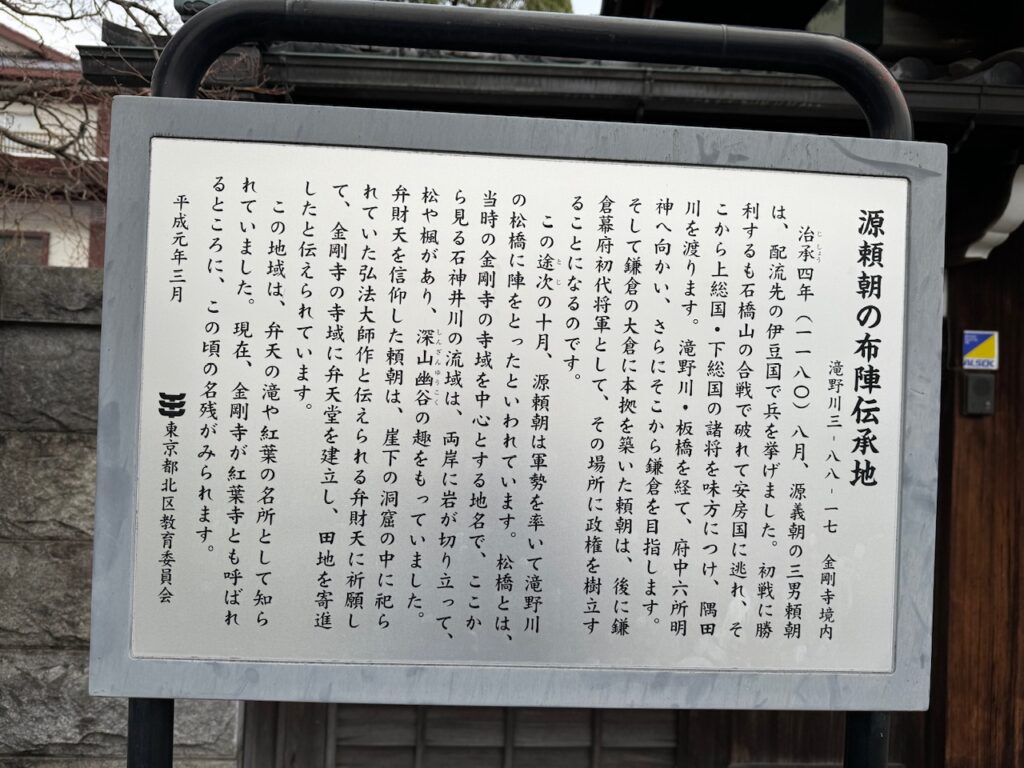進境著しいインドは、2027年にはGDP(国内総生産)でドイツ、日本を追い抜いて、米国、中国に続く世界第3位になると予想されています。
人口は昨年、14億2860万人と推計され、中国(14億2570万人)を抜いて世界一になったというニュースは記憶に新しいです(国連人口基金)。
まさに、飛ぶ鳥を落とす勢いですが、考えてみれば、インドの発展は今に始まったわけではありません。19世紀から20世紀にかけて、100年近くも英国の植民地になったため、「遅れた地域」の印象が焼き付けられましたが、もともと人類の世界4大文明の一つ、インダス文明(紀元前2600年頃)の発祥地だったんですからね。建国250年そこそこの米国など当時は影も形もありません。何しろ、「零」を発見した民族で、特別に数学に強く、世界中の大手IT会社から引っ張りだこで、グーグルやマイクロソフトなどでインド系の人がCEOも務めていたりしています。
インドの歴史を一言で語ることは私には出来ません。アショカ王のマウリヤ朝、カニシカ王のクシャン朝など学生時代に一生懸命に覚えましたけど、大方忘れてしまいました(苦笑)。
それより、インドといえば、何よりも宗教と哲学(ウパニシャッド)の国だという印象が私には強いです。宗教に関しては、日本の外務省の基礎データによると、インドでは「ヒンドゥー教徒79.8%、イスラム教徒14.2%、キリスト教徒2.3%、シク教徒1.7%、仏教徒0.7%、ジャイナ教徒0.4%(2011年国勢調査)」になっています。
日本を始め、チベットや中国、朝鮮、東南アジアに普及して多大な影響を与えている仏教徒が、本国インドではわずか0.7%しかいないとは意外でした。イスラム教は、パキスタンやバングラデシュがインドから独立してイスラム国家をつくったのですが、インド本国にもイスラム教徒が14.2%占めていたんですね。でも、ほとんどのインド人は約8割を占めるヒンドゥー教徒だということが分かります。
ですから、インドではヒンディー語が使われているものと思っていたのですが、多言語国家だと知って吃驚しました。ヒンディー語は「公用語」ではありますが、他に州単位で21の言語が公認されているというのです。知りませんでした。本日、この記事を書くきっかけとなりました。
例えば、インド北東部では「ボージュプリ語」、南インドでは「タミル語」、インド西部では「マラーティー語」、北インドとパキスタンでは「ウルドゥー語」、インド南東部では「テルグ語」、インド東部では「オリャー語」が話されているというのです。タミル語とウルドゥー語はかろうじて知っていましたが、その他は初めて聞く言語ばかりです。
インドの歴史を一言で語れないのもそのせいかもしれません。あまりにも複雑で、色んな民族が入り乱れているからです。今のアフガニスタン系の人が一時ですが、インドの一部に王朝を築いたこともあります。
Copyright par TY インド文明の転換点は、紀元前1500年頃のアーリア人の侵入だと言えます。これまで、印欧語族のアーリア人は、インド北西部から今のイラン、アフガニスタンを経てインド大陸に侵攻し、ついに南部のドラヴィダ人のインダス文明を滅ぼしたという説が有力でしたが、最近では、インダス文明の滅亡は、インダス川の氾濫などが要因で、アーリア人侵攻とは無関係という説が有力になっているようです。
それでも、アーリア人がインドを征服したことには変わりはありません。彼らが信仰していたバラモン教は、現在のヒンドゥー教に発展し、バラモンを頂点とするカースト制度がこの時に社会形成されたと言われています。征服者のアーリア人が被征服者のドラヴィダ人などの上に君臨するといった構図です。
そうです。やはり、インドといえば、カースト制度の国で、「バラモン」(司祭)、「クシャトリア」(王侯・士族)、「ヴァイシャ」(庶民)、「シュードラ」(隷属民)の四つの身分制度があり、その制度の最下層に「ダリット」と呼ばれる不可蝕民がいます。仏教の開祖ゴータマ・シッダールタ(釈迦)は出家する前は王子でクシャトリア階級でしたから、お釈迦さまでさえバラモン階級から差別されました。そこで、身分の隔たりなく、煩悩凡夫でも誰でも覚りを開くことを導く宗教を打ち立てのでした。その関係なのか、現在のインド仏教は、最下層のダリット階級の人々に多く信仰されていると聞いたことがあります。
この身分制度は、3500年間、ガチガチで揺るぎないものだと私は思っておりましたが、最近では、「反バラモン運動」なるものが盛んで、これまで高額所得が得られる公務員や大企業の社員などになれるのはバラモン階級ぐらいだったのが、だんだん、その他の階級にも門戸が開かれるようになったといいます。現代インドは共和政であり、為政者も国民による選挙で選ばれるようになっていますからね。
いずれにせよ、インドの歴史、文明、宗教、哲学はあまりにも複雑過ぎて、とても一言では表現できません。というのも、現在、日本で報道されるインド関係のニュースといえば、モディ首相の動向ぐらいです。あとは、世界最大と言われるインド映画の話題ぐらいですか。「反バラモン運動」が盛んになっていることなど、私は全く知りませんでした。
今、聴き逃しサービスで聴いている水島司東大名誉教授によるNHKカルチャーラジオ「歴史再発見 走り出すインド」(全13回)で色々と教えてもらっています。