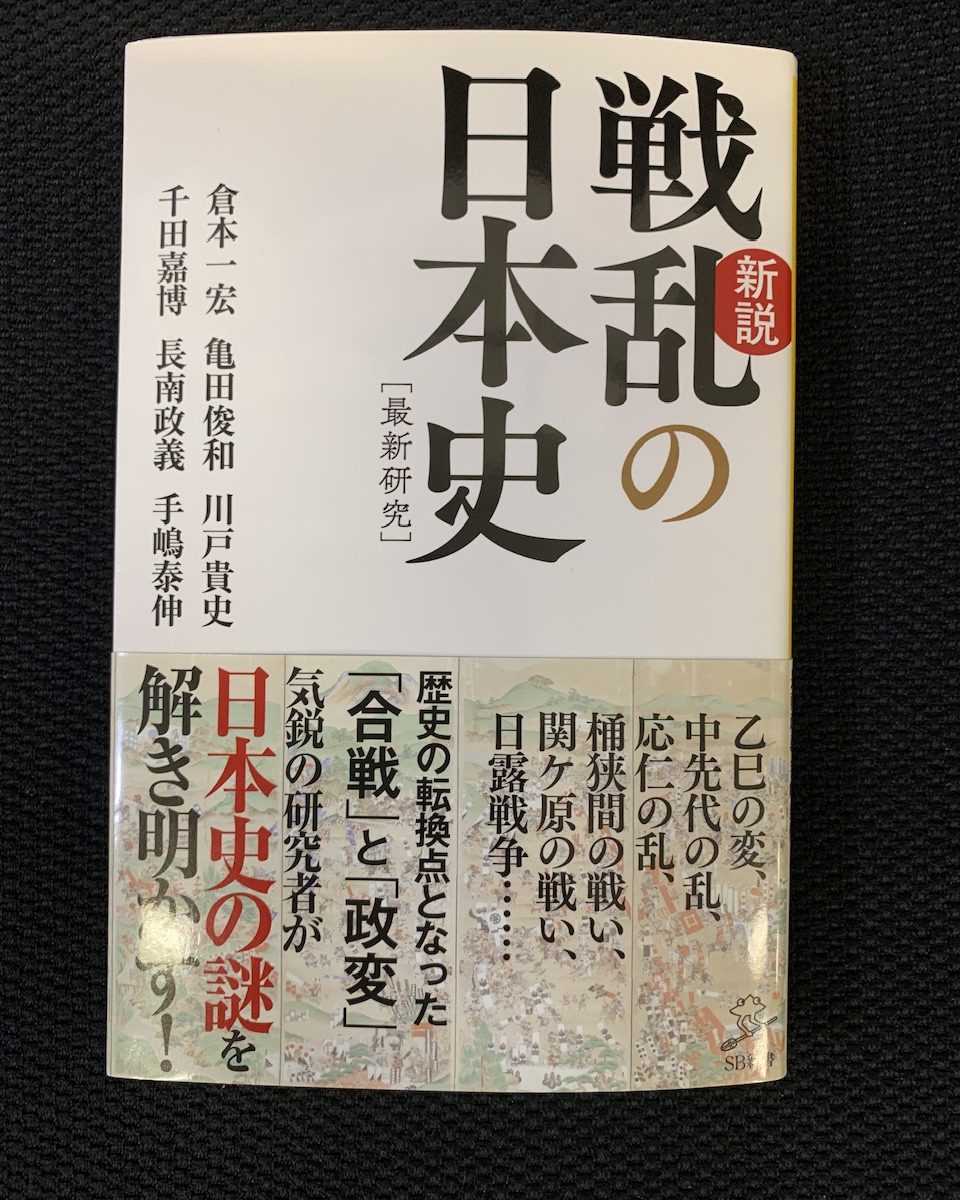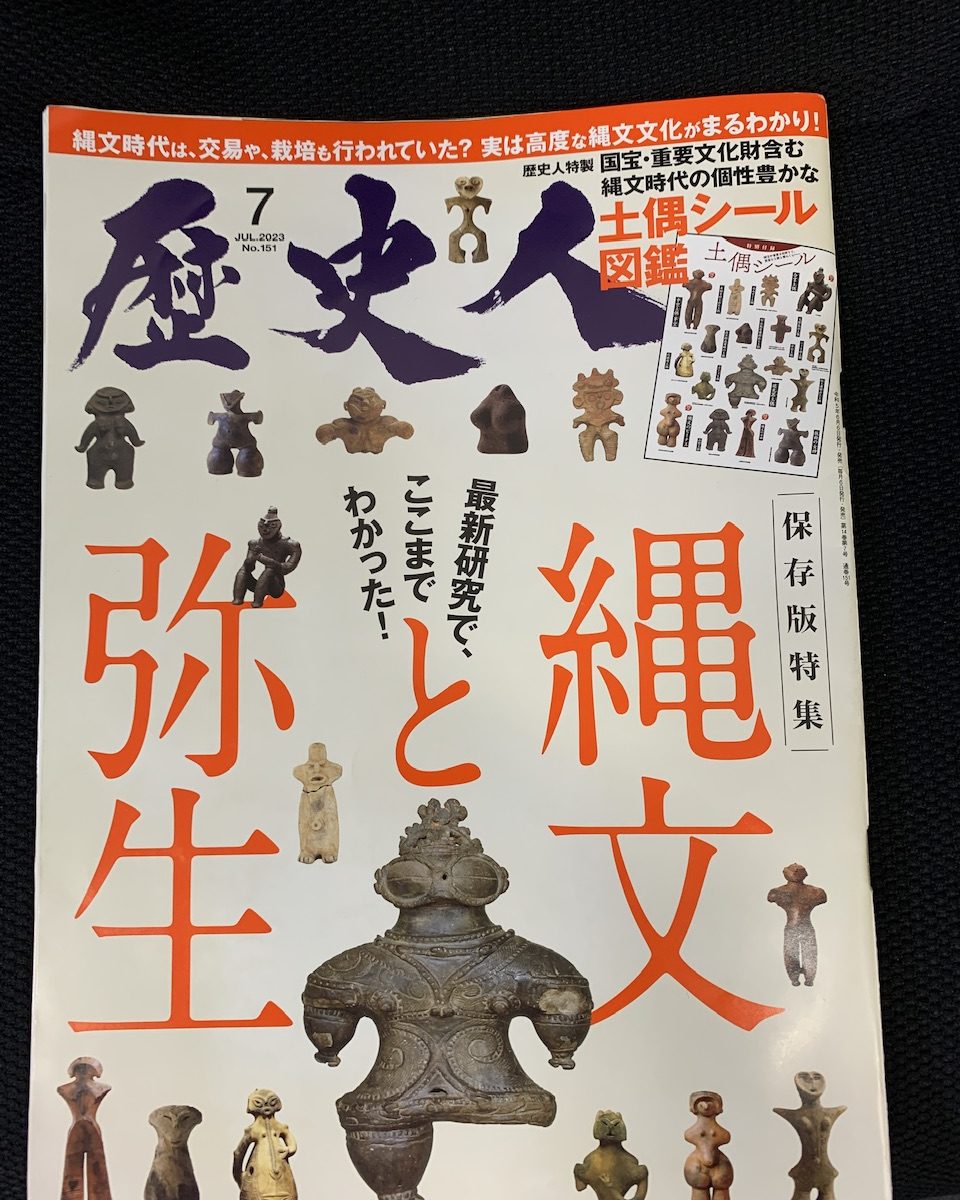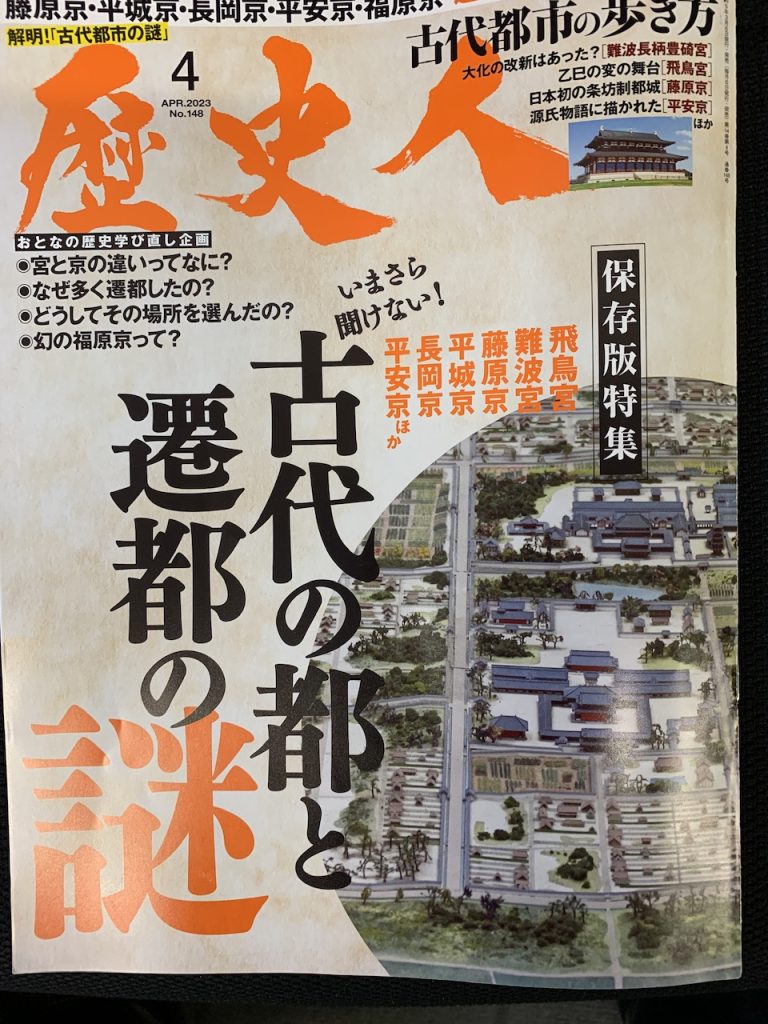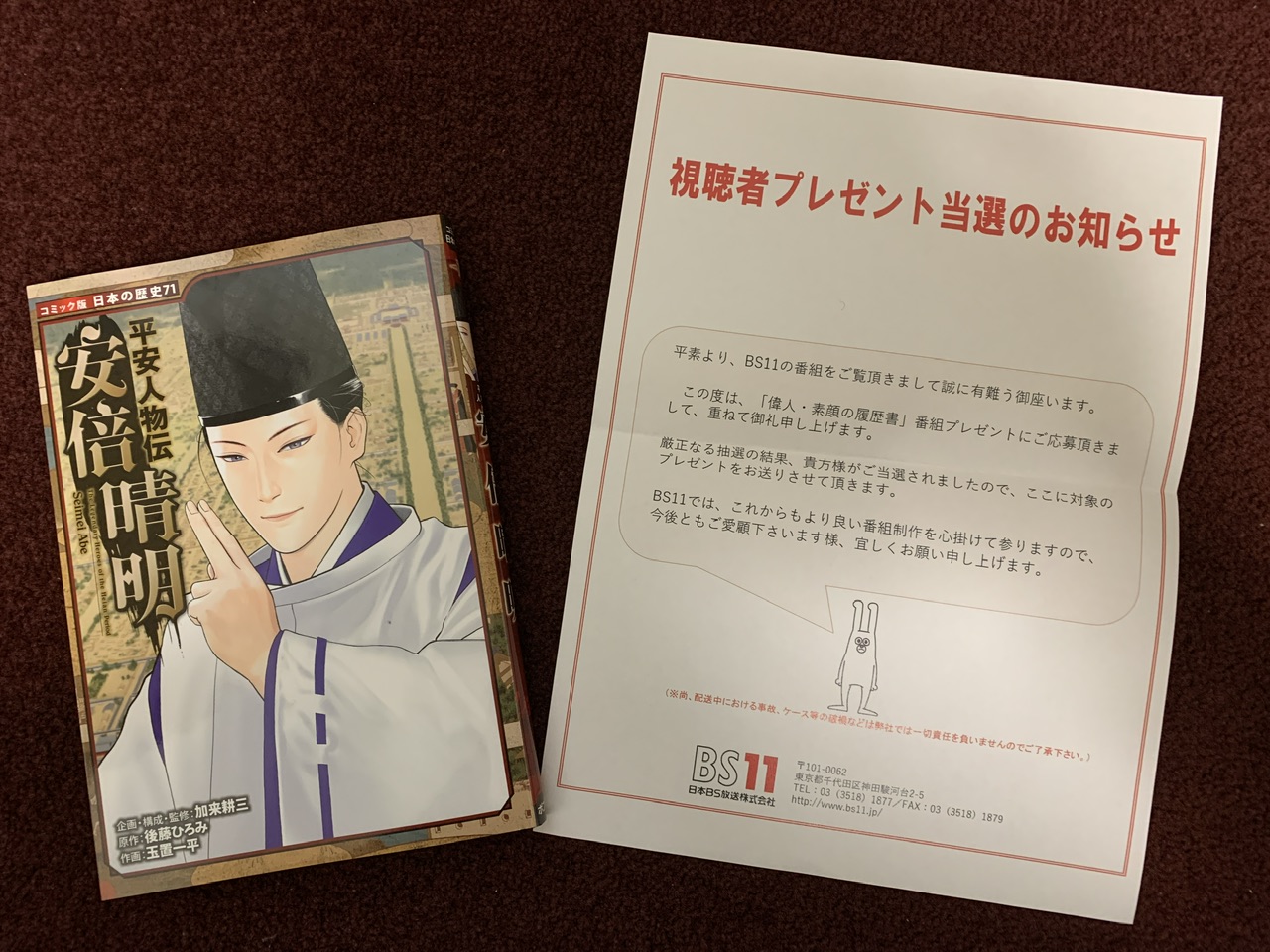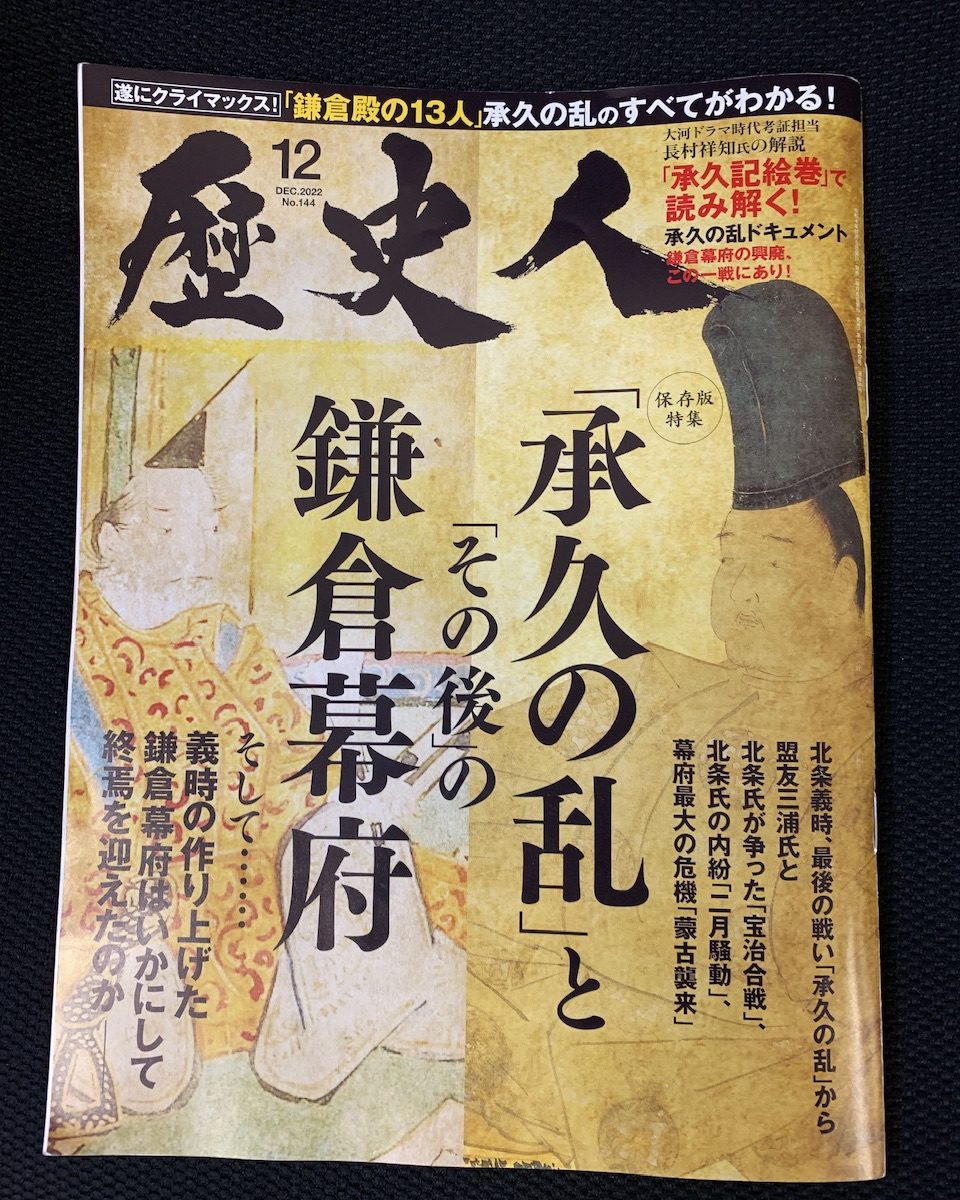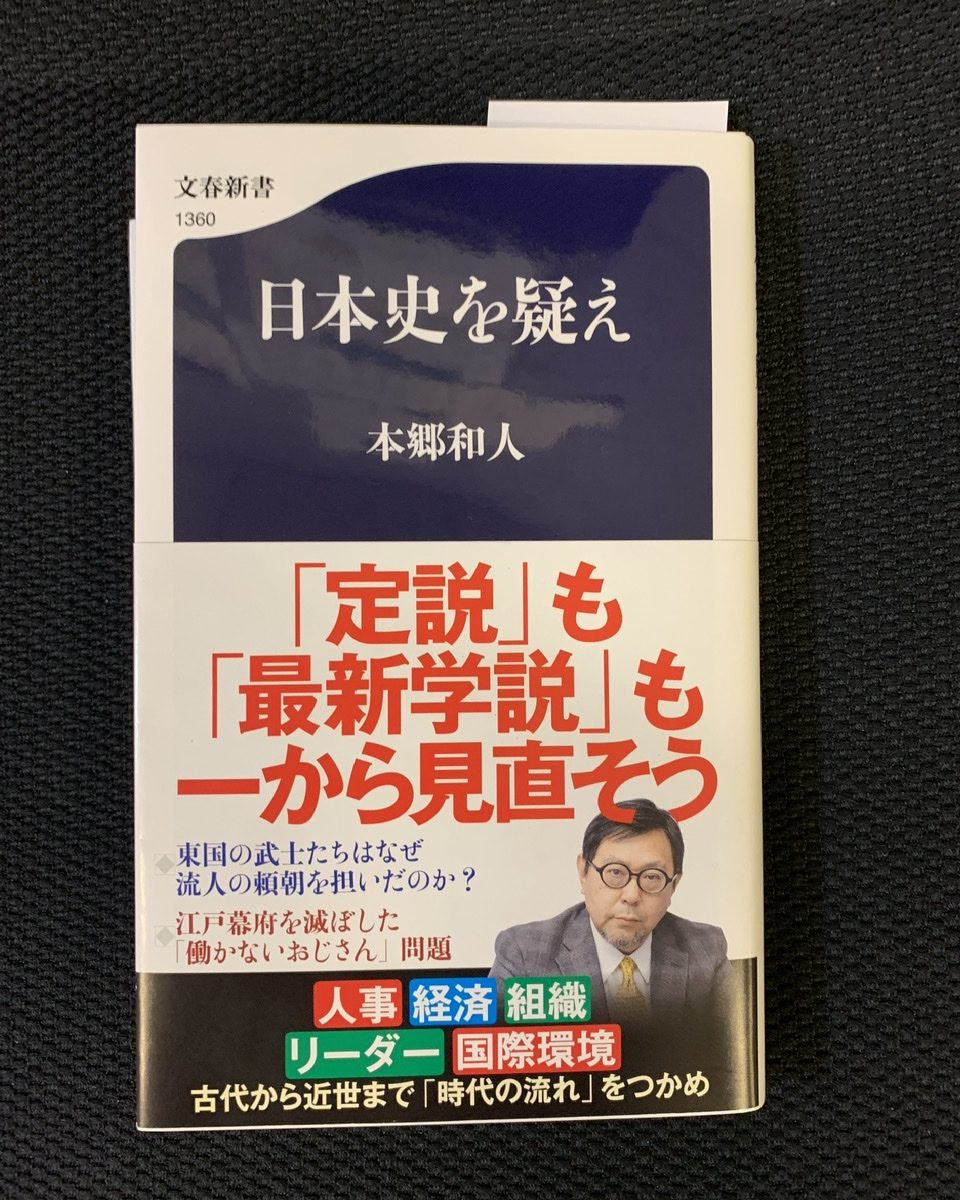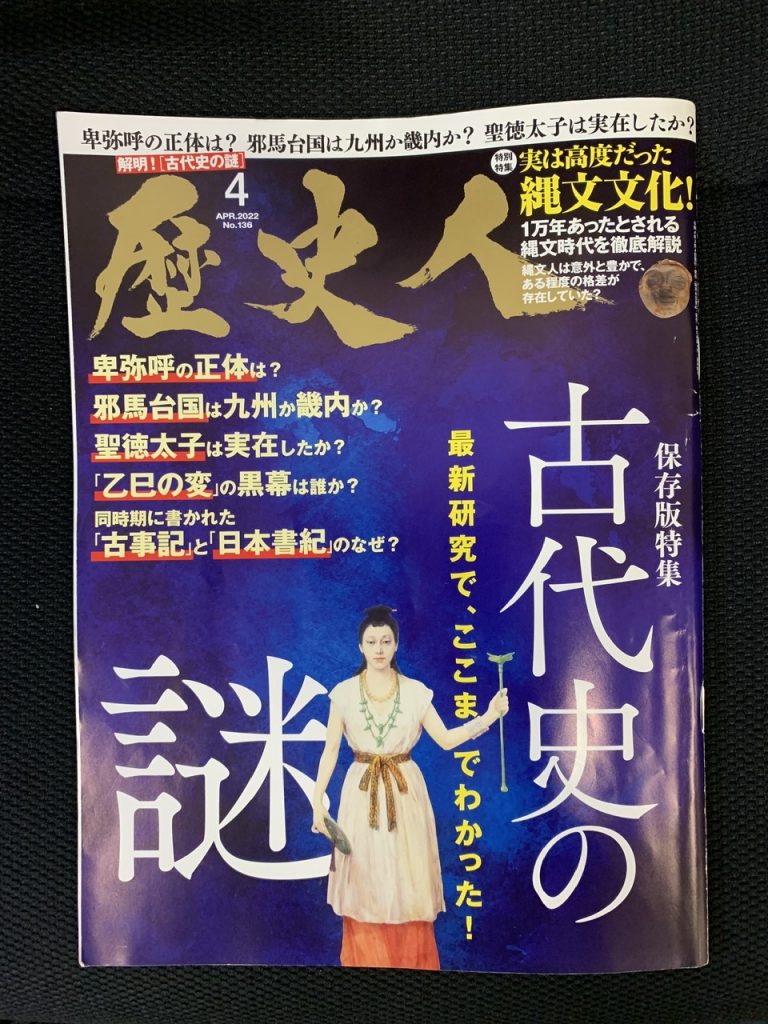先日、NHKBSで放送された「フロンティア」第1回「日本人とは何者なのか」は、この《渓流斎日乗》の愛読者の皆さんには必見の番組でした。ちょっと制作者側のわざとらしさが目に付きましたが、内容はひっくり返って驚くほど衝撃的でした。(NHK総合で、12月18日午前0時25分から再放送あり)
私はせっかちなので、結論を先に書いてしまいますが、我々日本人はもともとタイ南部に今でも狩猟採取を続けるマニ族(東京大学の太田博樹教授によると、タイやラオス周辺に住んでいる「ホアビニアン」と呼ばれる民族)の流れを汲む1000人の勇気のあるフロンティアが北上して3万年前に日本列島に住み着いて「縄文人」となり、その後、3000年前に大陸の北東中国から渡来した「弥生人」との混血が進み、これまでの定説ではその「二重構造説」でお仕舞いでした。しかし、次世代シーケンサーと呼ばれる最新のDNA解析により、3世紀の古墳時代に東アジア全域から渡来した民族との混血、つまり、「三重構造説」だったということが分かったというのです。これは驚きです。
要するに、DNA解析により、今の日本人の多くには、東アジアから渡来した「古墳人」が半分、「弥生人」が4分の1、「縄文人」が4分の1の割合で混血したDNAが残っているというのです。(縄文人の流れを色濃く残すアイヌ民族と沖縄人は除きます)ただし、この肝心要の「古墳人」については、まだ研究の最中なので、どんな人たちなのか、何故、3世紀になって大量の東アジアの民族が日本列島に渡来したのかはまだ不明で分かっていません。東アジアの民族とは、中国だけではなく、ベトナムのキン族なども含まれているようです。中国には56も民族がありますから、日本人とそっくりの雲南省の白(ペー)族なども含まれているのではないかと思われます。(番組ではそこまで詳しくやってくれませんでした!)

我々の祖先であるホモ・サピエンスは20万~30万年前にアフリカで誕生し、7万年前にアフリカを出て西アジアに行き、そこから欧州に行く者と東アジアに行く者とに分かれ、日本列島には3万年前に辿り着いたといいます。それが、先述したホアビニアンの1000人です。3万年前は、まだ氷河期で日本列島と大陸は、くっついていたといわれます。南は対馬と九州が、北は北海道が大陸にくっついていたので、歩いて渡って来ることが出来たのでしょう。
それが、1万8000年前に氷河期が終わり、温暖化で海面が上昇し、日本列島は孤立状態となります。お陰で、列島に閉じ込められた人たちが縄文文化(1万6000年前~3000年前)を1万3000年間も花咲かせます。なあんだ、鎖国じゃん、と突っ込みたくなります(笑)。あの火炎土器も奇妙な宇宙人のような土偶も、鎖国の産物だったとは!
でも、今から3000年前に北東中国から渡来した「弥生人」たちは、稲作と金属器をもたらしました。恐らく、高度な造船と航海術を身に付けていたからこそ、渡来できたのでしょう。縄文人と混血します。

そして、残るは「古墳人」です。3世紀となると、日本はもう卑弥呼の時代でした。中国では漢王朝が滅亡して魏呉蜀の三国時代などになりますから、内乱続きで不安定なため、日本列島に「亡命」する人が溢れたのではないかと推測されます。職人や技術者や技能者だけでなく、手に職を持たない一般庶民も多く渡来したようです。現代日本人のDNAの半分も「古墳人」が占めているといいますから、相当大量の民族が海を渡って日本にやって来たことは確かです。この時の「日本人」と言っても、容姿や皮膚の色が違い、お互いに言葉が全く通じない、現代以上に国際色豊かだったと考えれています。(「人類の起源」の著者篠田謙一国立科学博物館館長)
最新のDNA解析って本当に凄いですね。古墳人を中心にもっともっと解明されていけば、日本人とは何者なのか、分かっていきます。これは大いに楽しみです。皆さんも一緒に長生きしましょう(笑)。