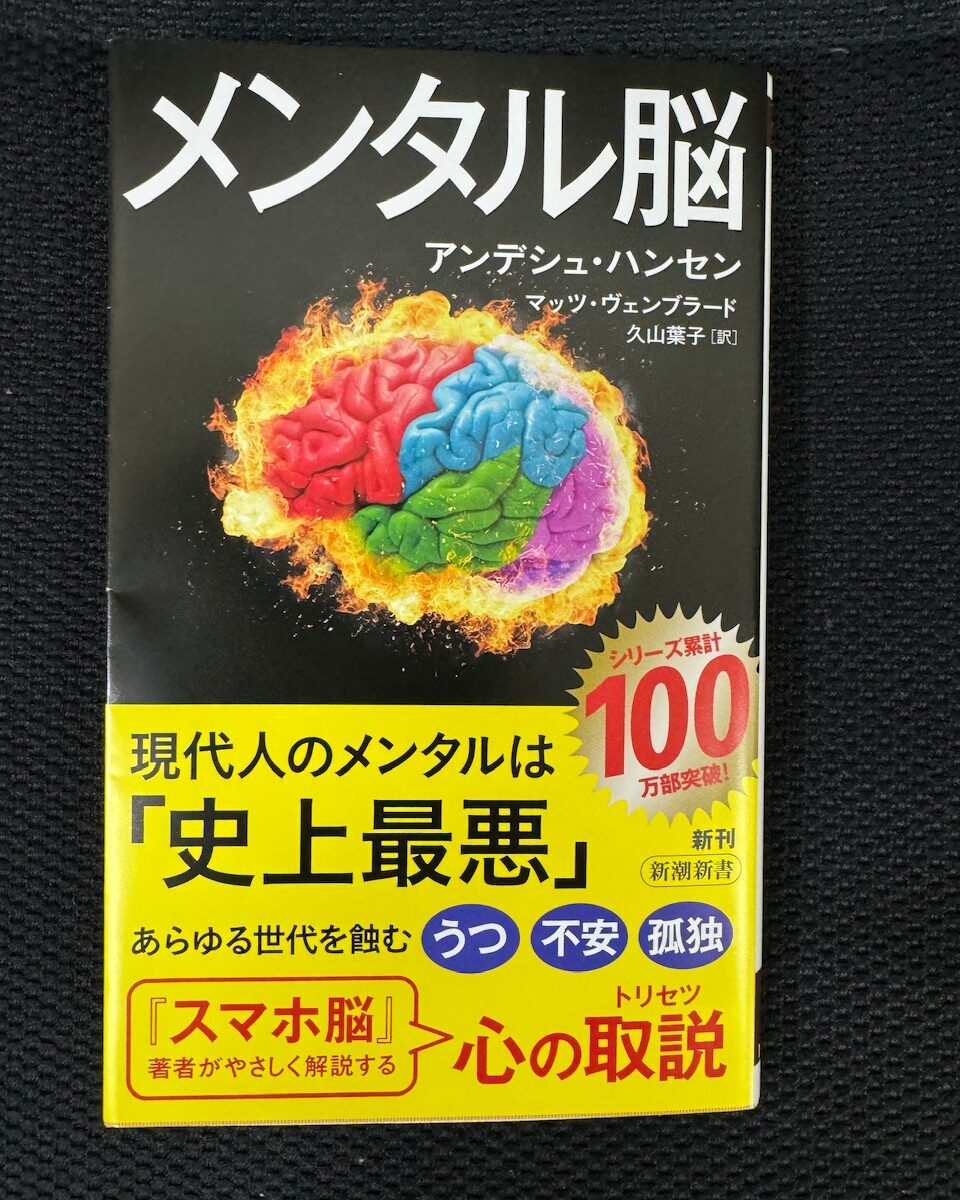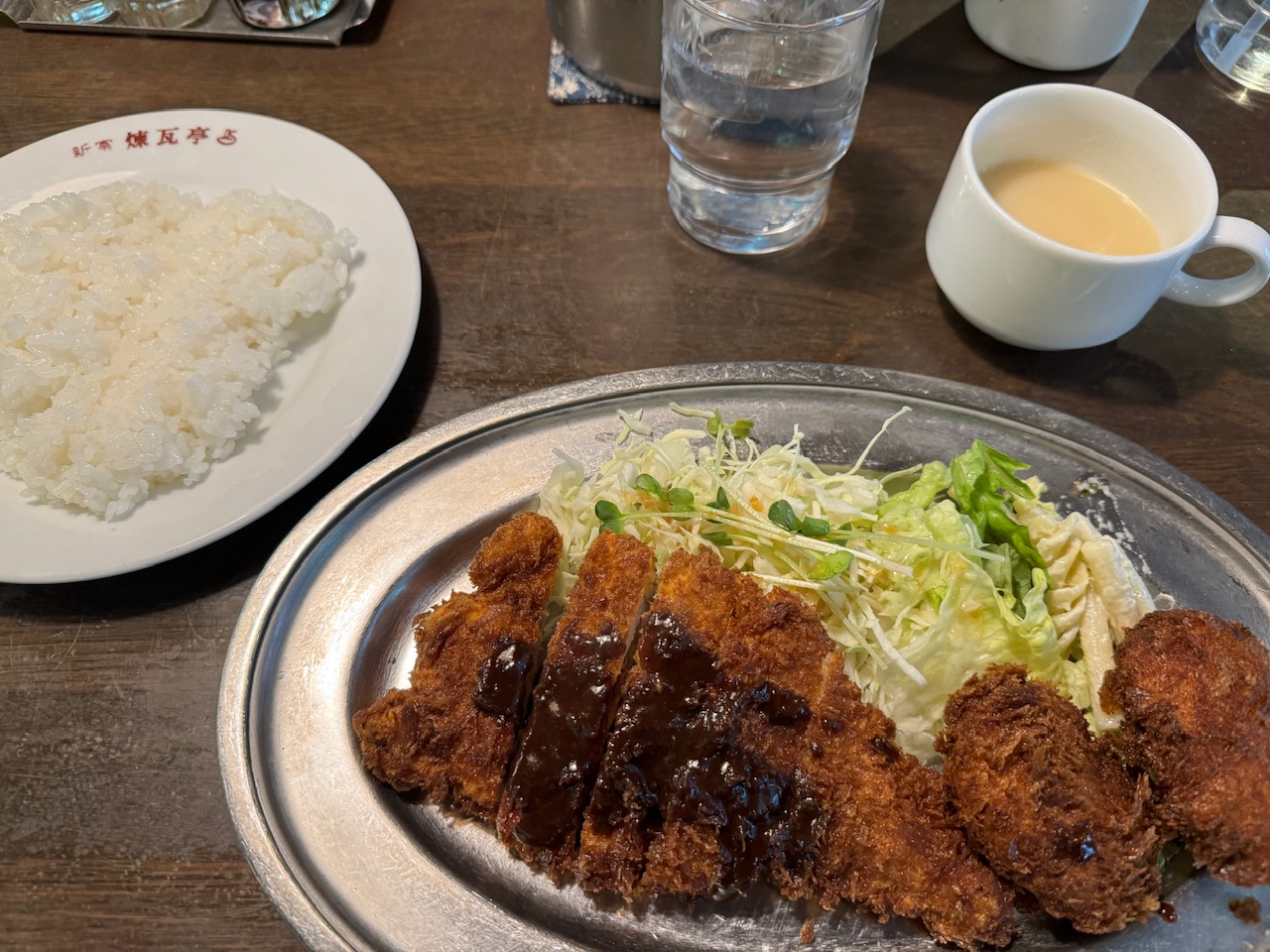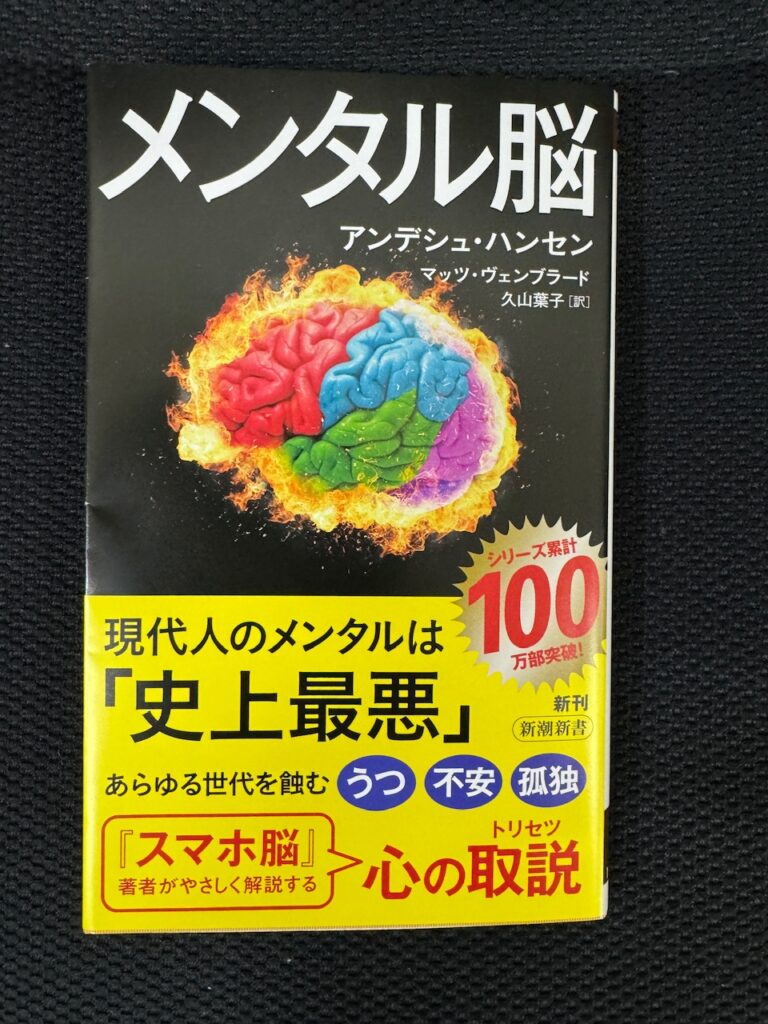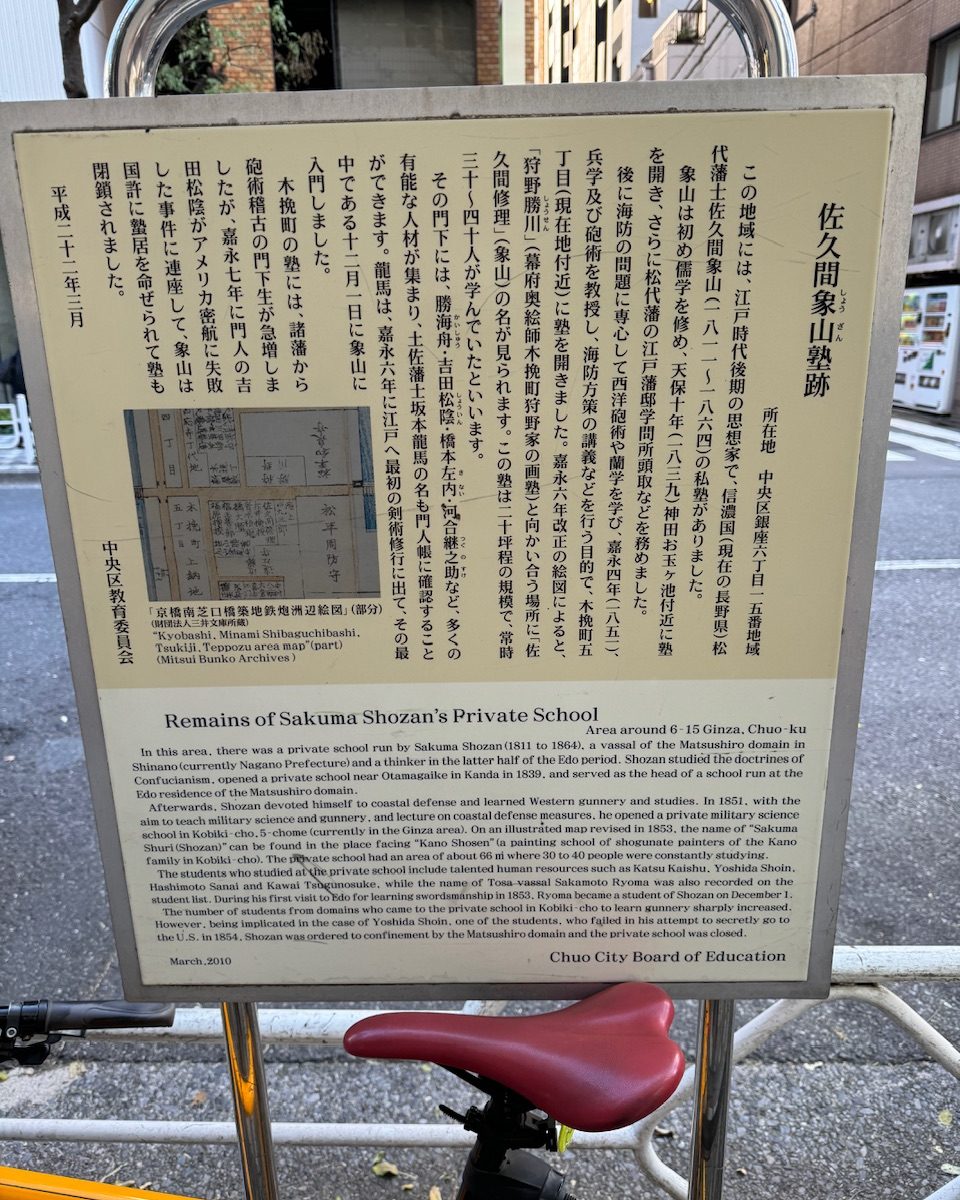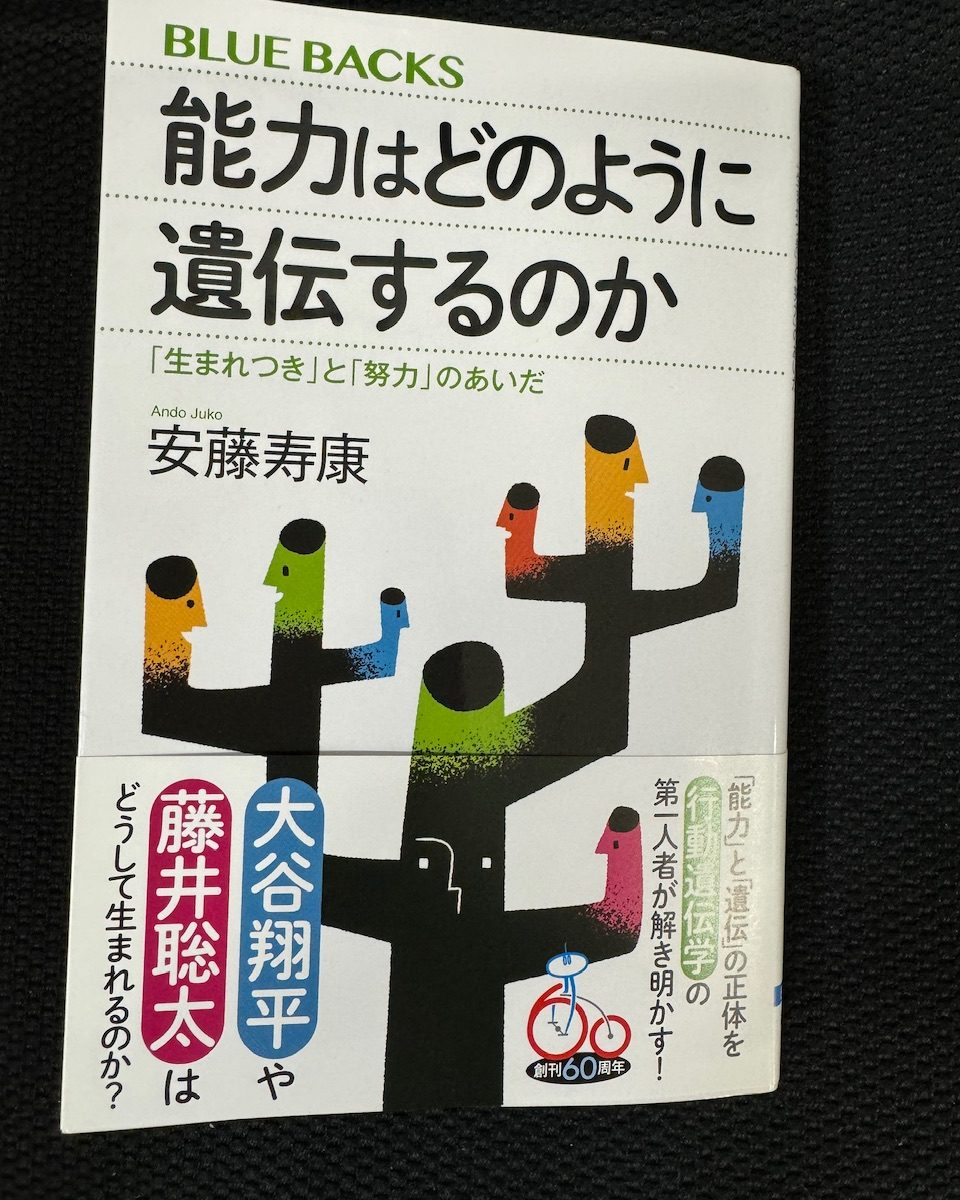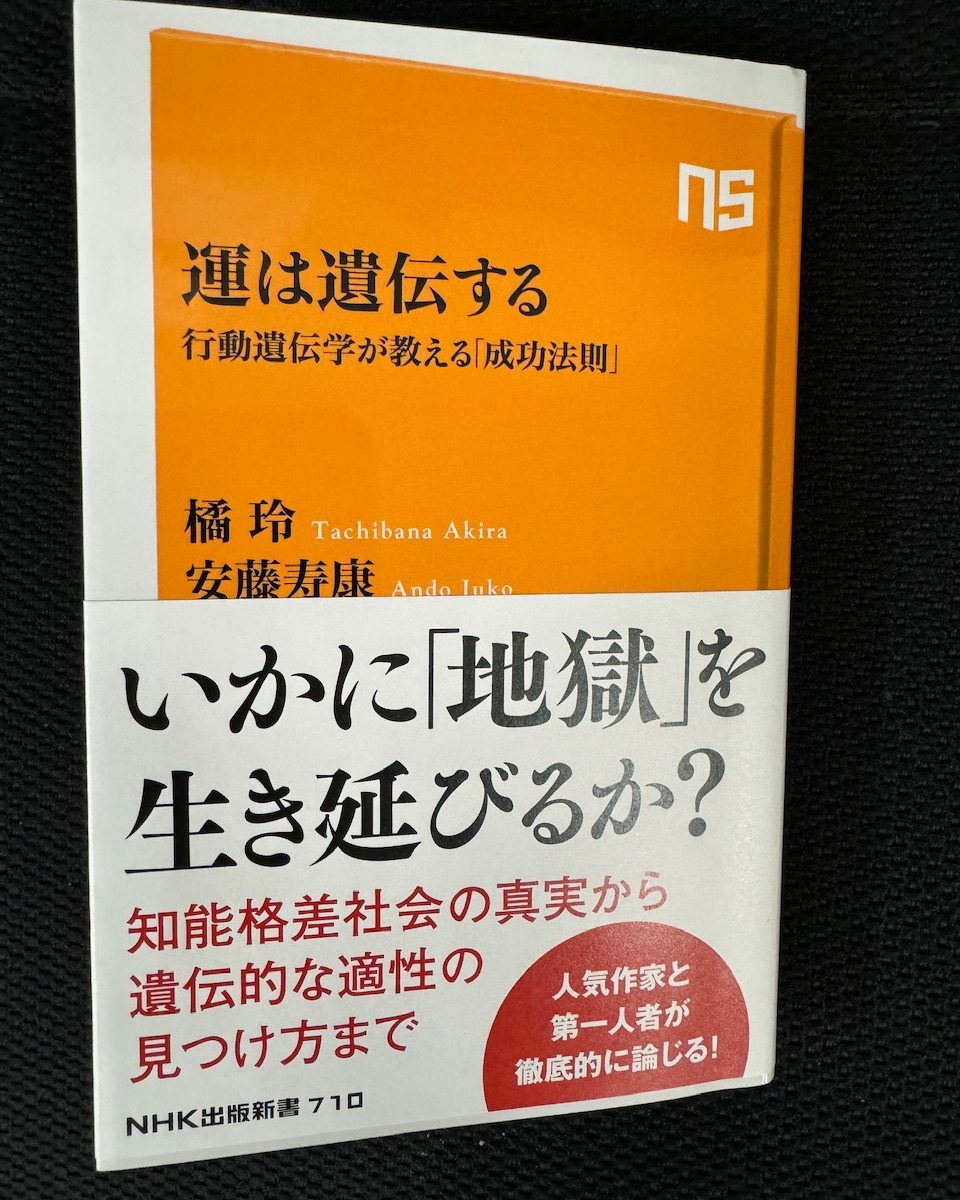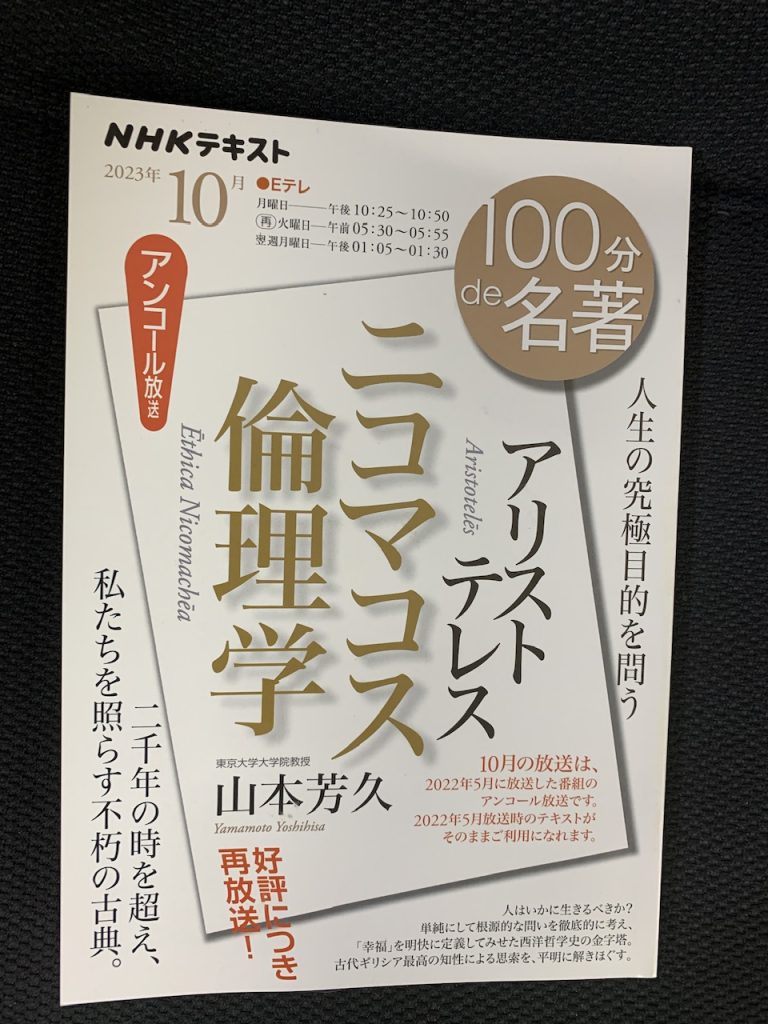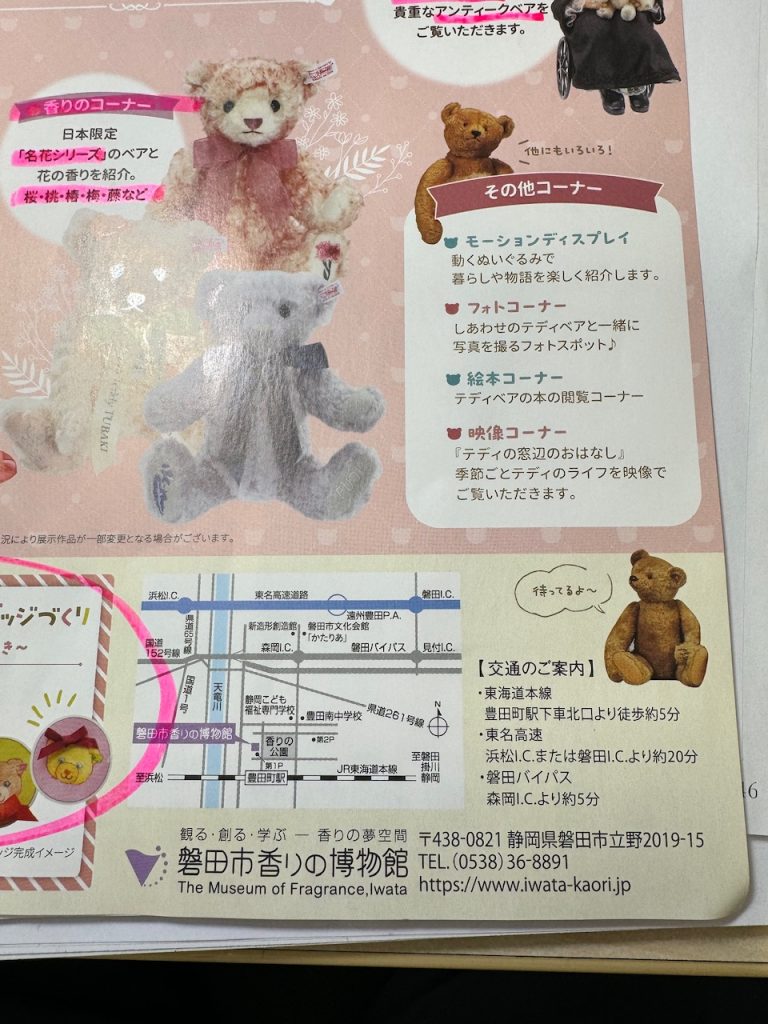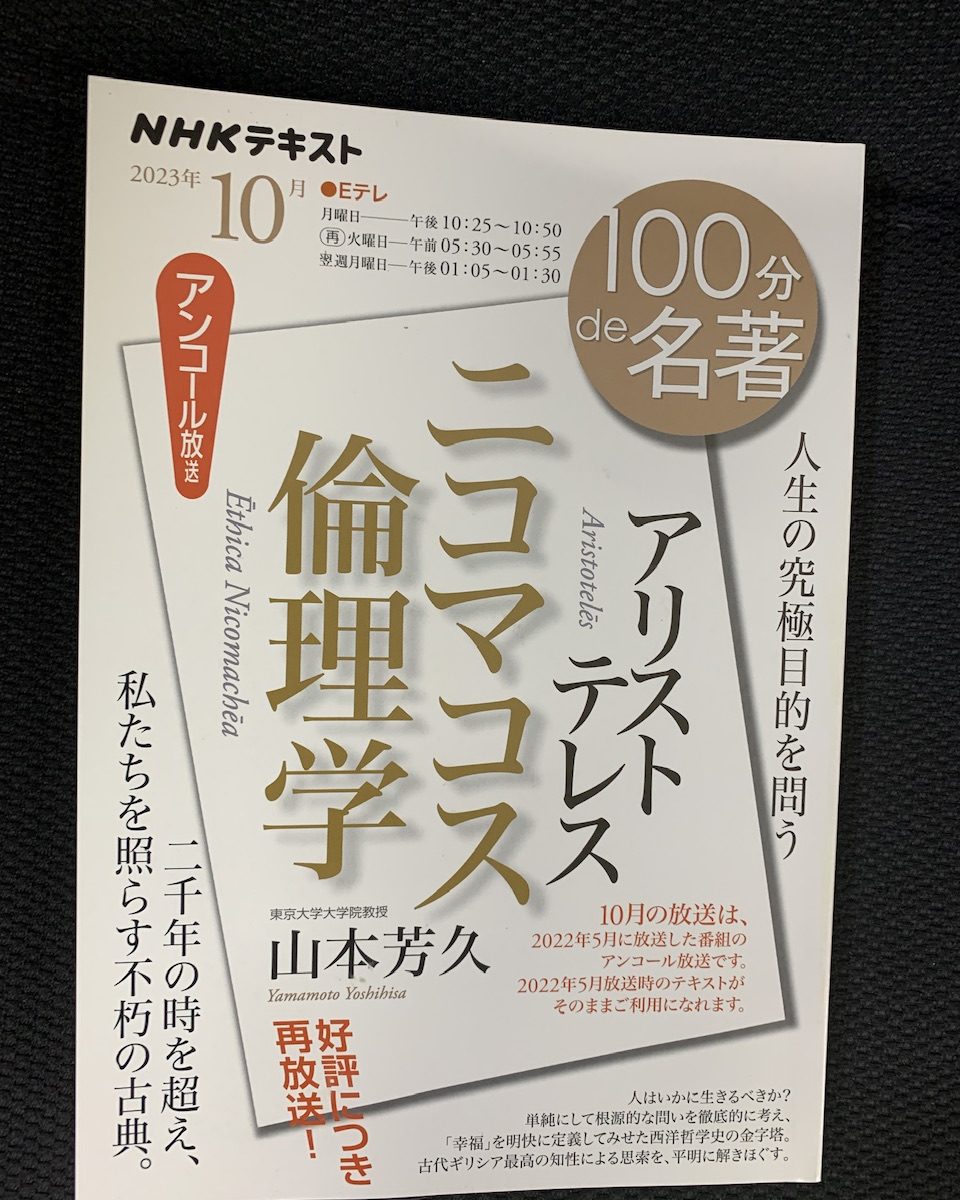数日前から少しずつ橘玲、安藤寿康著「運は遺伝する 行動遺伝学が教える『成功法則』」(NHK出版新書、2023年11月10日初版)なる本を読んでいます。有楽町の三省堂書店にNHKラジオのフランス語のテキストを買いに行って、ついでに書棚を覗いていたら、偶然この本が見つかったのです。まさに、セレンディピティ(思い掛けぬ幸運)かもしれません。
この本は、三省堂有楽町店の新書部門で第1位を獲得していたので目立つ所にありました。中をパラパラめくっていたら、こんな文章に巡り合いました。(ちなみに、この本は、「言ってはいけない」などで知られるベストセラー作家の橘氏と、「能力はどのように遺伝するのか」を今年出版した行動遺伝学者の安藤慶大名誉教授との対談で構成されています。)
病気になったり、近しい人が亡くなったり、強盗に遭うなど、一般的に運が悪かったとされる偶然の出来事と、離婚や解雇、お金の問題など、本人にも責任があると見なされる出来事を比較したところ、偶然の出来事の26%が遺伝で説明でき、本人に依存する出来事の遺伝率30%と統計的に有意な差はなかった。(14ページ)
えっ?どういうこと??? 次にこんなことが書かれています。
よく考えてみると、病気には遺伝が関わっているし、…強盗に遭うのは確かに運が悪かったのでしょうが、危険な場所にいたり、目立つ行動をとったりしたのが原因だとすれば、そこにも遺伝の要素がある。知人が交通事故に遭ったら、「運が悪かったね」と同情するでしょう。でもそれが信号を無視して横断歩道を渡ろうとしたり、無理な追い越しをしようとして起きたら単なる偶然とは言えない。そう考えれば、私たちの人生の全てを遺伝の長い影が覆っていて、そこから逃れることができないのではないでしょうか。(15ページ)
この渓流斎ブログを長年お読み頂いている皆様はご承知かと存じますが、私は色んなことに好奇心を働かせております。そのうちの一つが、「人間は、遺伝で決まるのか、育った環境によって決まるのか」といった難題です。俗に言う「氏(うじ)か、育ちか」、「生まれつきか努力か」、Nature or Nurture? です。だから、これまで苦労して人類学や進化論に関する書籍を読んできたのです(苦笑)。
でも、我思うに、もしこれが、AかBかの二者択一問題だとしたら、日本人は圧倒的に「氏」を尊重してきた民族だと言っても良いのではないでしょうか。天皇制にしろ、武家社会にしろ、現代政界にせよ、芸能の歌舞伎の世界にせよ、「世襲」を重んじてきたからです。
大興善寺(佐賀県) この本では、作家の橘氏が、行動遺伝学者である専門家の安藤氏に質問を投げかける形で対談が進んでおりますが、博覧強記のお二人ですから、私なんか全く知らなかった多くの文献を引用されています。例えば、行動遺伝学の大御所ロバート・プロミンは、著書「ブループリントーDNAはどのようにして、私たちが何者であるかをつくりあげるのか」を出版し、遺伝子レベルで行動遺伝学の知見が証明されたと「勝利宣言」したといいます。
また、行動遺伝学の大立者エリック・タークハイマーは「行動遺伝学の3原則」(原則 1:人間の行動形質は全て遺伝の影響を受ける。 原則 2:同じ家庭で育ったことの影響は、遺伝の影響よりも小さい。 原則3 :人間の複雑な行動形質に見られる分散のうち、相当な部分が、遺伝でも家族環境でも説 明できない。)を提唱し、この3原則が今や、行動遺伝学の基本中の基本になっているようです。
そんなことを急に言われても、何のことを言っているのか分からないと思いますので、そもそも行動遺伝学とは何かと言いますと、知能や性格を含めて、あらゆる行動や心の働きが遺伝の影響を受けるというのが原則だという学問です。おおよそですが、知能は60%ぐらい遺伝子の影響を受け、「協調性」や「外向性」や神経質」などの性格は、30~40%遺伝によるというものです。行動遺伝学は、主に、双生児(一卵性、二卵性)の方々を長年追跡して科学的知見を追究していきます。
そこで、この本は、まさに「遺伝か環境か、どちらなのか」の議論が展開されています。1冊の本になるぐらいですから、色んな所見が出てきて面白い読み物になっていますが、なかなか結論は出てきません。色んな要素が複雑に絡み合っているからだというのです。結局、ヒトは、遺伝と環境の要素を50%ずつ受けているのが正解なのでしょうが、「30%の遺伝でも多いと言えばかなり多い」「偶然であっても、遺伝的に必然だったかもしれない」などと言われると、こちらも思わず頷いてしまいます(笑)。
大興善寺(佐賀県) さらに言えば、例えば、私は、電車やバスや職場などで嫌~な奴に遭遇することがあるのですが、彼ら本人だけが悪いのではなく、生まれつきの遺伝の産物なんだと思うと、あまり腹が立たなくなるんですよね(笑)。
「病気になったのは遺伝のせい」「学力がなく、年収が低いのも全て遺伝のせい」ということにすれば、大変気が楽になりますが、この本をじっくり読めば、行動遺伝学はそこまで結論づけて断定的に言っていない、ということになっています。「じゃどっち何だ!」と思う方はこの本を読むしかないでしょう。そして、自分自身で納得する結論を引き出したらどうでしょうか。