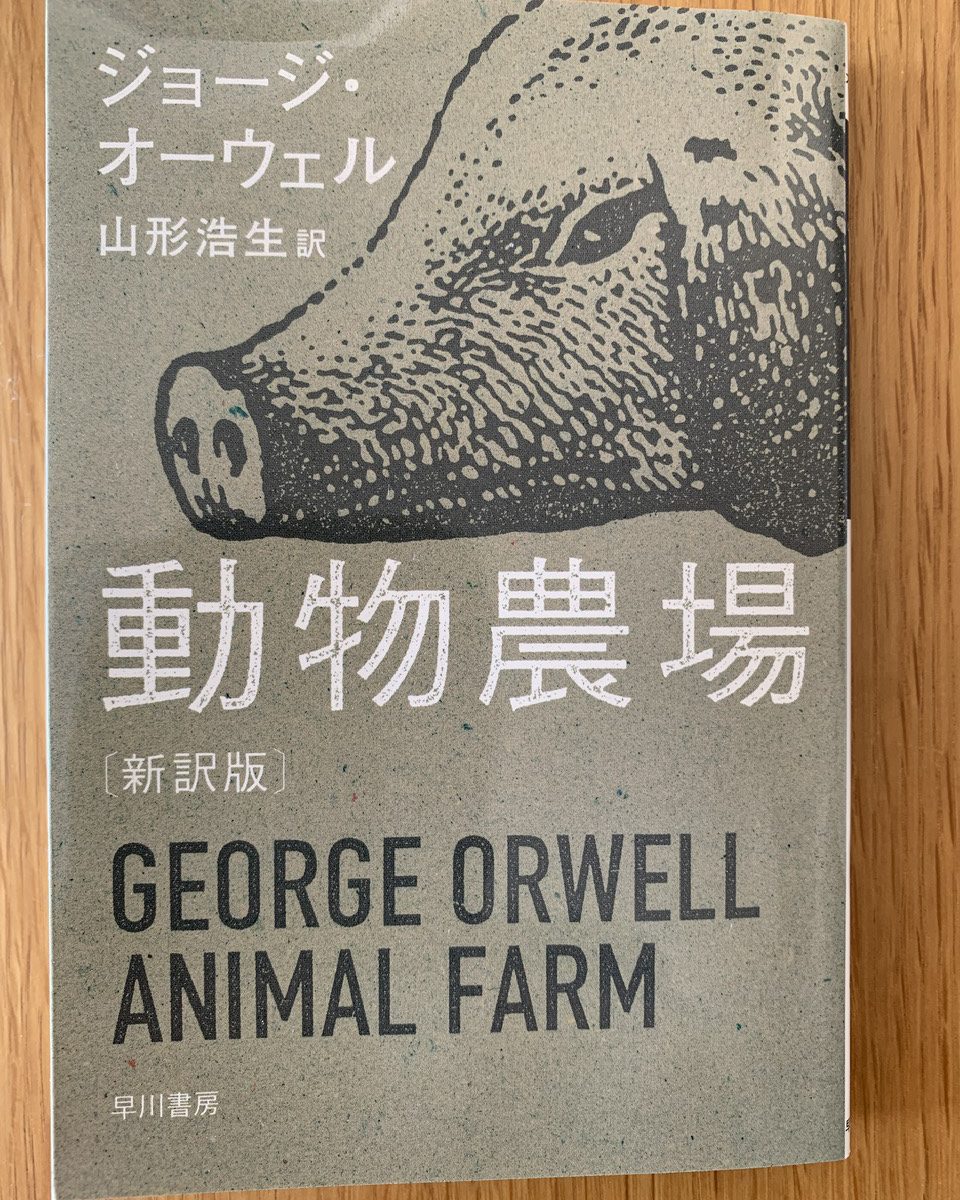ジョージ・オーウェルの代表作「動物農場」(早川文庫)を読了しました。
読書力(視力、記憶力、読解力)が衰えたせいか、「あれ?このミュリエルって何だっけ?」「ピンチャーって何の動物だったかなあ…?」などと、何度も前に戻って読み返さなくてはなりませんでした。嗚呼…。
◇ケッタイな小説ではない
しかも、読み終わった後も、「何だか、ケッタイな小説だったなあ」と関西人でもないのに、関西弁が出る始末です。でも、この浅はかな感想は、巻末のオーウェルによる「報道の自由:『動物農場』序文案」と「『動物農場』ウクライナ語版への序文」、それに「訳者あとがき」を読んで、自らに鞭を打たなくても撤回しなければならないことを悟りました。
この本を読む前の予備知識は、ソ連の社会主義、というよりスターリン独裁主義を英国伝統のマザーグース(寓話)の形を取って暗に批判したもの、ぐらいだと思っていたのですが、もっともっと遥かに深く、含蓄に富んだ野心作だったのです。著者によると、1944年に書き上げた時点で、この作品を世に出そうとしたら、出版社4社にも断られたといいます。当時は、まだ秘密のヴェールに包まれたソビエト社会主義に対する幻想と崇高な憧れが蔓延していて、こんな本を出してロシア人の神経を逆なでしては不味いという「忖度」が、出版を取り締まる英国情報省内にあったようです。

社会主義者を自称するオーウェルに対して強硬に批判したのが、右翼ではなく、まだスターリンの粛清や死の強制収容所の実態を知らない左翼知識人だったというのは何とも皮肉です。後にノーベル文学賞を受賞する詩人T・S・エリオット(当時、出版を断ったフェイバー&フェイバー社の重役だった)もその一人です。訳者の山形浩生氏によると、同書は、ナチスによる反共プロパガンダに似たようなものと受け止められた可能性さえあったといいます。当時の時代背景をしっかり熟慮しなければいけませんね。(日本は太平洋戦争真っ只中で、敗戦に次ぐ敗戦)
いずれにせよ、この作品は1945年にやっと刊行され、日本でも、米軍占領下の1949年に永島啓輔による訳(GHQによる翻訳解禁第1号だった)が出されるなど世界的ベストセラーとなり、オーウェルの代表作になりますが、その間、色々とすったもんだがあったことが巻末の「あとがき」などに書かれています。
日本ではこの後、あの開高健まで訳書を出すなど何冊か翻訳版が出ていますが、私が読んだのは、2017年に初版が出た山形氏による「新訳版」です。日本語はすぐ古びてしまうので、このように新訳が出ると助かります。原書を読んでもいいのですが…。
◇知らぬ間に独裁政権
私自身は浅はかな読み方しかできませんでしたが、登場するブタの老メイジャーがレーニン、インテリで演説がうまいスノーボールがトロツキー、そして、このスノーボールを追放して徐々に徐々に独裁政権樹立していくナポレオンがスターリンをモデルにしていることは感じていました。当初は、人間であるメイナー農場主のジョーンズを「武装蜂起」で追放して、平等な動物社会を築いていく目論見だったのが、最初に皆で誓った「七戒」が、ナポレオンに都合の良いように書き換えられていくことがこの作品の眼目になっています。例えば、もともと最後の7番目の戒律が「すべての動物は平等である」だけだったのに、いつのまにか、「だが一部の動物は他よりもっと平等である」という文言が付け加えられていて、次第次第にブタのナポレオンが、イヌや羊や馬やロバやガチョウなどの上に君臨して富と権力を独占していくのです。
◇抗議しないことは独裁者容認と同じ
私自身は、こういった独裁者に対する批判だけが著者の言いたかったことだと皮相的に読んでしまったのですが、訳者の山形氏は「あとがき」でこう書いておりました。(一部変更)
ここで批判されているのは、独裁者や支配階級たちだけではない。不当な仕打ちを受けても甘んじる動物たちの方である。…動物たちの弱腰、抗議もせず発言しようとしない無力ぶりこそが、権力の横暴を招き、スターリンをはじめ独裁者を容認してしまうことなのだ。
なるほど、さすがに深い洞察です。
ここで思い起こすことがあります。今、ロシアのプーチン政権下で、毒殺されかけた反体制指導者アレクセイ・ナワリヌイ(44)氏が、拘束されると分かっていながら、1月17日、ドイツからモスクワに帰国し、案の定、空港で拘束されて30日間の勾留を命じられました。ナワルヌイ氏は、とても勇気のある行動で尊敬に値することですが、私は、正直、無謀の感じがして、普通の人なら「長い物には巻かれろ」で黙ってしまうと思ってしまいました。でも、抗議の声を上げないことは権力者の横暴と独裁を容認することになってしまう、という自覚がナワリヌイ氏にあったということなのでしょう。「動物農場」を読んでその思いを強くしました。