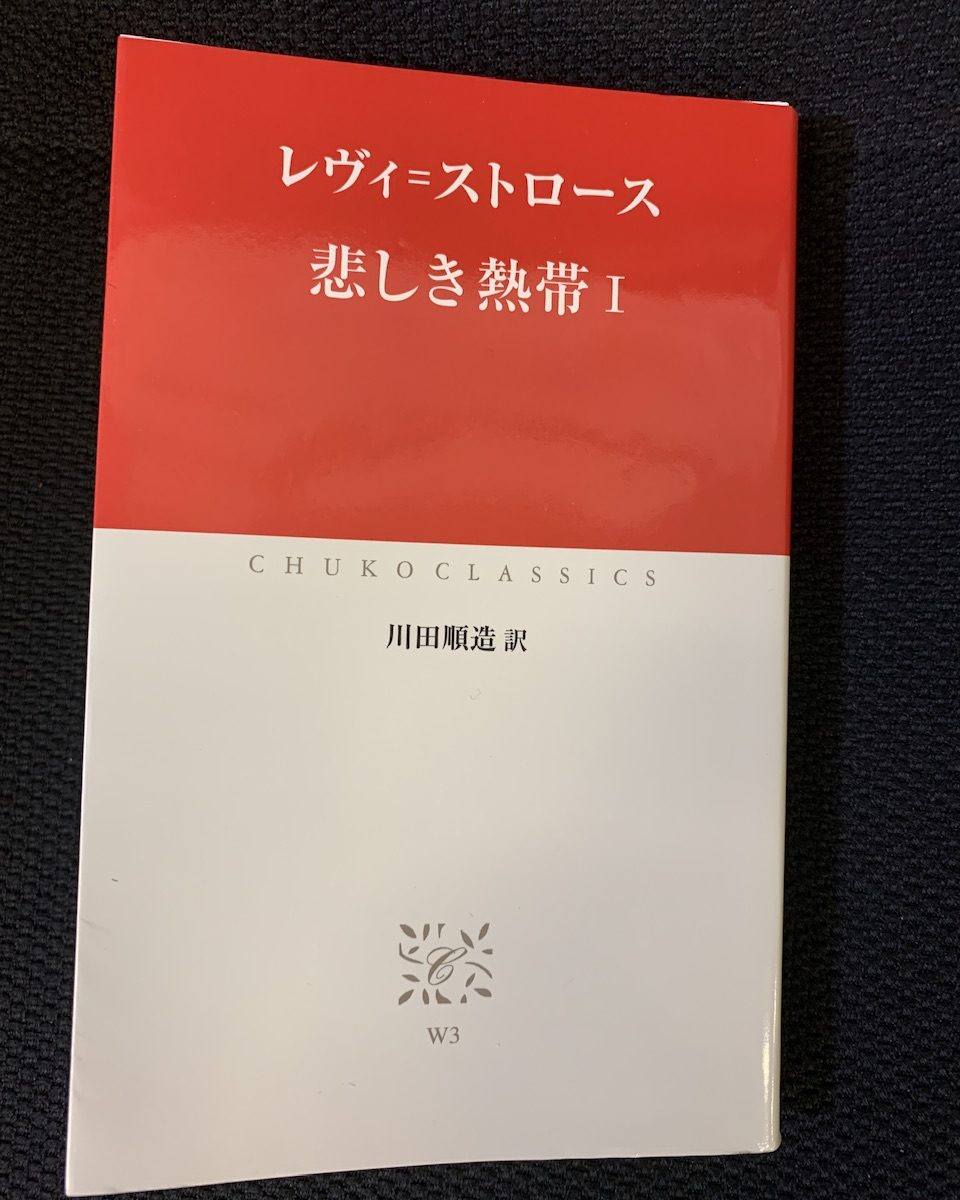レヴィ=ストロース(1908~2009年)著、川田順造訳「悲しき熱帯Ⅱ」(中公クラシックス)をやっと読了することが出来ました。マルセル・プルーストのような文章は、非常に難解で、かなり読み解くのに苦労しましたが、やはり、名著と言われるだけに、読了することが出来てズシリと重い達成感があり、感無量になりました。
最後まで読んでいたら、本当に最終巻末に「年表」や「関連地図」(大貫良夫氏作成)まで掲載されていたので、「ありゃまあ、知らなかった」と驚いてしまいました。最初から地図があることを知っていたら、参照しながら読めたのに、と思ったのです。確かに、カタカナの固有名詞が出て来ると、最初は、これが地名なのか、ヒトの名前なのか、植物なのか、戸惑うことが多かったからです。そんなら、今度は地図を見ながら再読しますか?(笑)

「悲しき熱帯」の大長編の中で、一つだけ印象深かったことを挙げろ、と言われますと、私は迷うことなく、ナンビクワラ族の訪問記を挙げますね。この部族に関しては、以前にもチラッとこのブログに書きましたが、とにかく、アマゾン奥地の未開人の中で最も貧しい部族だったからです。(著者は、ナンビクワラ族のことを「石器時代」なんて書いております。)
「悲しき熱帯Ⅱ」の161ページにはこんな記述がみられます。
ハンモックは、熱帯アメリカのインディオの発明によるものだ。が、そのハンモックも、それ以外の休息や睡眠に使う道具も一切持っていないということは、ナンビクワラ族の貧しさを端的に表している。彼らは地面に裸で寝るのである。乾季の夜は寒く、彼らは互いに体を寄せあったり、焚火に近寄ったりして暖をとる。
この前の141~142ページには、ナンビクワラ族の生活様態が描かれています。
ナンビクワラ族の1年は、はっきりとして二つの時期に分けられている。10月から3月までの雨の多い季節は、集団は各々、小川の流れを見下ろす小さな高地の上に居住する。先住民は、そこに木の枝や椰子の葉でざっとした小屋を建てる。(中略)乾季の初めに村は放棄され、各集団は幾つかの遊動的な群れになって散って行く。7カ月の間、これらの群れは獲物を求めてサバンナを渡り歩くのである。獲物といっても多くは小動物で、蛆虫、蜘蛛、イナゴ、齧歯動物、蛇、トカゲなどである。このほか、木の実や草の実、根、野性の蜂蜜など、いわば彼らを飢え死にから守ってくれるあらゆるものを探し歩く。
うーむ、凄いなあ、凄まじい生活ですね。蛆虫まで御馳走?になるなんて、最も生活レベルが低い人類であることは間違いないことでしょう。とても、生き残れるとは思えません。彼らはその後どうなったのか? と思ったら、日本人の文化人類学者がしっかりと、フォローされているようですね。巻末に参考文献として列挙されていました。
一つは、著名な文化人類学者の今福龍太氏の論考「時の地峡をわたって」(レヴィ=ストロース著「サンパウロのサウダージ」(みすず書房)の今福氏による翻訳版に所収)です。今福氏が2000年3月にサンパウロ大学に招聘されたことを機会に、60年余り前にレヴィ=ストロースが住み、写真を撮った地点を丹念に再訪して鋭利な考察を行ったものです。
もう一つは、この「悲しき熱帯」を翻訳した川田順造氏の著書「『悲しき熱帯』の記憶」(中公文庫)です。レヴィ=ストロースのブラジル体験から50年後(1984年)に、ナンビクワラをはじめ、ブラジル各地を訪れて感じ、考えたことを起点に「悲しき熱帯」の現在を考察したものです。
いずれも、私自身未読なので内容は分かりませんが、こうして、世界中の文化人類学者がレヴィ=ストロースに大いなる影響を受けたことが分かります。レヴィ=ストロースのもう一つの代表作「野生の思考」(みすず書房)も私自身、未読ですので、いつか挑戦してみたいと思っております。