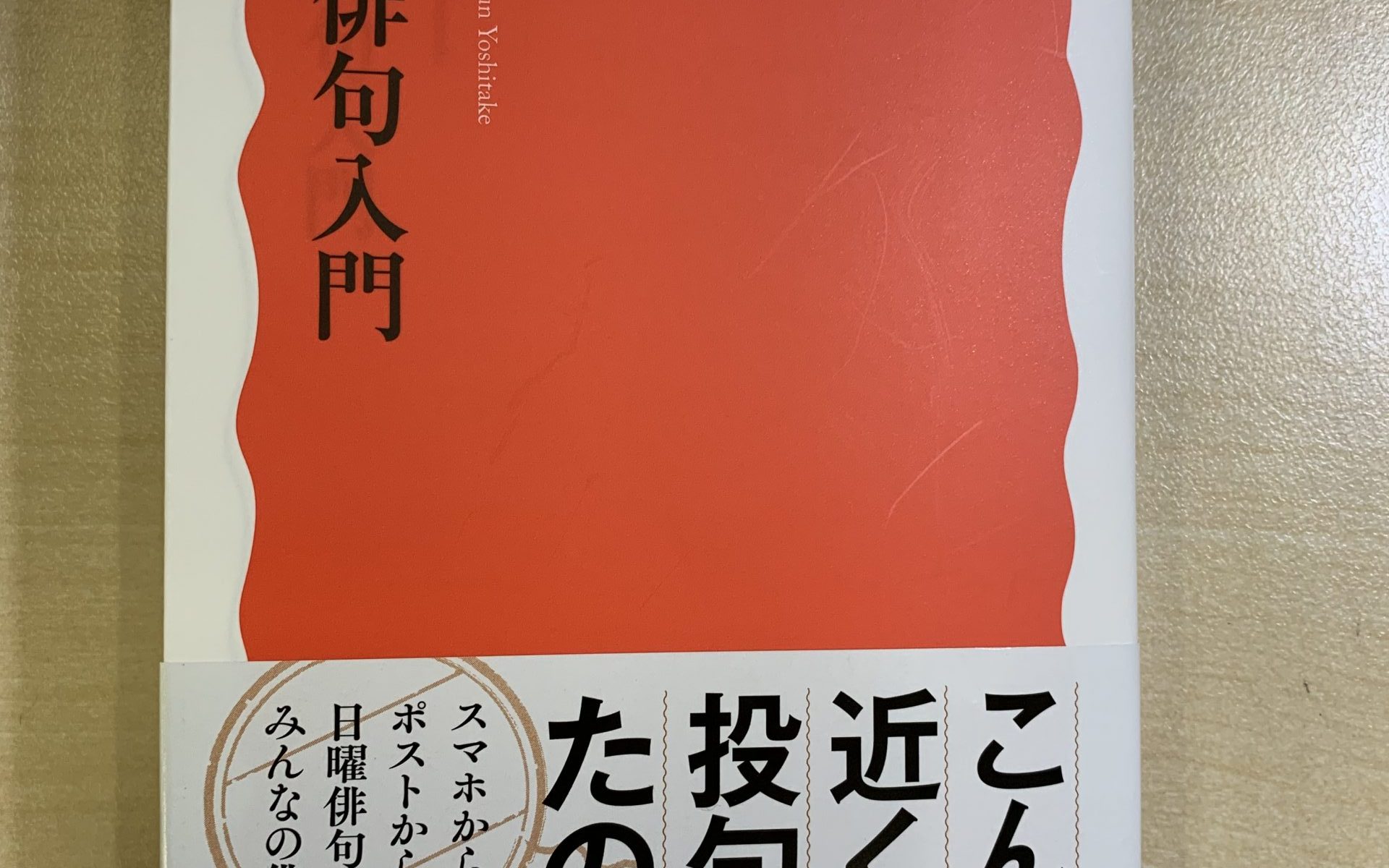私は、どちらかと言えば、桑原武夫の「第二芸術」派で、俳句や短歌といった短詩型に関しては、敬して遠ざかっておりました。特に、結社というものは、偉い三太夫みたいな髪を生やした巨魁と呼ばれる大先生がピラミッドの頂点に君臨、もしくは世襲していて、会費という名の上納金を納めさせて、下々を睥睨しているように部外者からは見えました。
でも、俳句や短歌自体には罪がないわけですよね。(もちろん結社も)立派な文藝という名の芸術で、第一とか第二とか序列を付けられるのは、甚だ不本意なことでしょう。
このブログを愛読してくださっている皆様にはお分かりの通り、今、私は吉竹純著「日曜俳句入門」(岩波新書、2019年10月30日初版)を読んでいます。何故、短詩型嫌いの私がこの本を読むことになったのか、については、今日は説明致しません。お時間がある方は、小生が先日の11月26日に書いた「コピーライターから歌人・俳人に」をお読みください(笑)。
私は、人間的に随分単純に出来ているのか、この本を読んで、桑原武夫的束縛というか、桎梏からほんの少し脱却できました。「結構、面白そうじゃん」といった軽いノリです(笑)。
俳聖と呼ばれる偉い人の句を「詠む方」ではなく、「作る方」のことです。新聞などに投稿することを「投句」というそうで、この本の帯にも書かれている「こんな近くに投句のたのしさ」は、前回もご紹介しました。著者の吉竹氏は、「日曜大工」のノリで、忙しいサラリーマンの方でも休日に暇を見つけて、新聞や広報誌やコミュニティー雑誌でも何処でもいいから、投句してみませんか、と薦めているのです。(もう何年も前から、有名なプロ中のプロの俳人でさえも、新聞に投稿しているそうです!)
そして、この本には、選者に選ばれる極意というかテクニックを教えてくれているのです。前回にも書きましたが、著者の吉竹氏は、電通のコピーライターを経てフリーになり、俳句だけでなく、短歌も新聞等に投稿し、ついには頂点ともいうべき天皇陛下の「歌会始」に入選しています。
その極意というのは、ごくごく簡単に言えば、選者の句集を熟読吟味して、社会派か、花鳥風月派かといった「選者のクセをつかめ」という結論に落ち着くのではないでしょうか。東京で発行されている主要6紙の掲載日は、日曜日が朝日と東京、月曜日が毎日と読売、木曜日が産経、土曜日が日経というのは基本中の基本。朝日俳壇だけは、投句は葉書だけでしか認めていません。それは、毎週1回、選者が朝日新聞東京本社に集まり、同じ葉書に目を通すという共選システムだからだといいます。ネット投句を最初に解禁した新聞俳壇は、意外にも選者を年功序列で配し、レイアウトを固定している読売俳壇で1989年9月から。「俵万智さんが1996年6月に史上最年少の33歳で読売歌壇の選者に就任しており、私はこれを契機に始まったとばかり思っていましたが、それより7年も前から実施されていたとは驚くばかり」と吉竹氏は書いています。
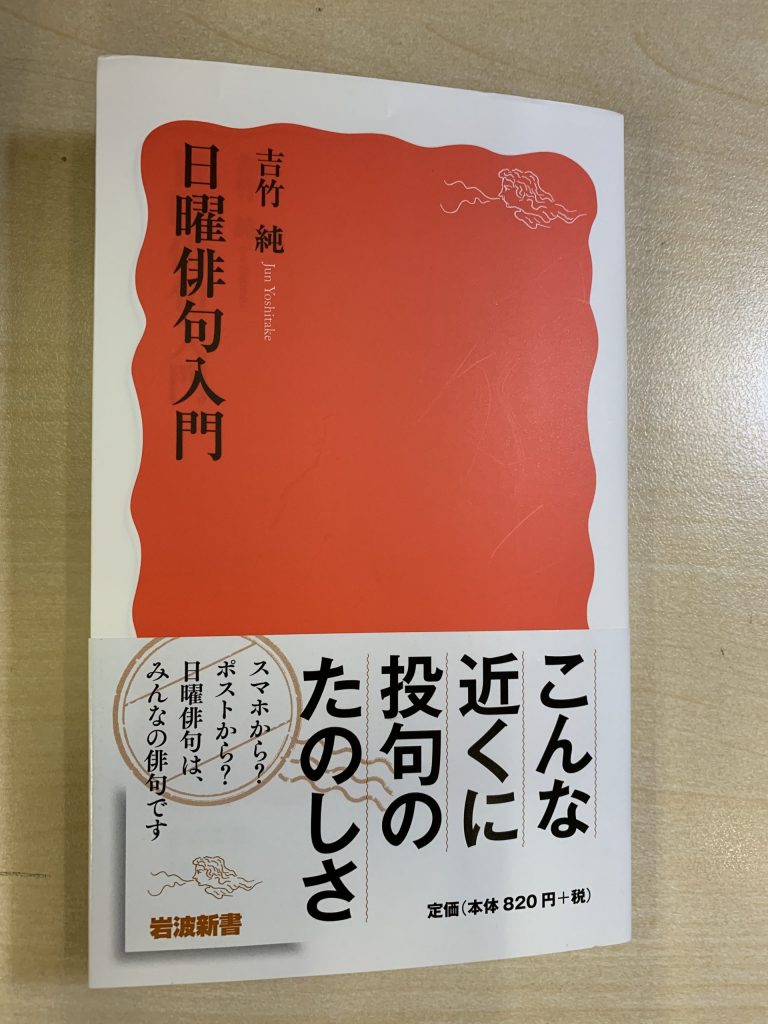
投句者にとって、掲載されることは名誉であり、これほど嬉しいことはありません。それには、メールがいいのか、葉書の方がいいのか? 手書きがいいのか、ワープロ字の方が採用の確率が高いのか?句の背景説明である「前書き」を書いた方がいいのか?季語がなくてもいいのか?自分で季語をつくってもいいのか?-まあ、色んなことが書かれています。
◇間違いでは?
前回、岩波書店の校正は日本一と言えるぐらい厳格だ、といったことを書きましたが、えへへ、この本の中で、間違いを見つけてしまいました。38歳で夭折した画家有元利夫(1946~85)のことを著者の吉竹氏が詠んだ一句に
花降りぬ有元利夫笛吹けば
があります。この句は、産経俳壇2007年4月に小澤實選で掲載されました。
有元利夫は、宮本輝の小説「錦繍」などの表紙も担当したバロック風の絵を描く知る人ぞ知る天才画家ですが、そもそも、彼を知らない選者だったら、この句は掲載されなかったわけです。これ以上、作品について踏み込むのは置いといて、実は、彼は、吉竹氏の電通時代の1年後輩のデザイナーだったというのです。ただし、彼は東京芸大美術学部には4年浪人して入ったので、「年齢は一つ上でした」(91ページ)と著者は書きます。でも、有元利夫は1946年9月23日生まれ、吉竹氏は48年生まれ(一浪して72年に大学卒業ですから早生まれではない)ですから、「年齢は二つ上でした」の間違いではないかなあ、とフト思ったのです。我ながら、嫌な性格ですねえ(笑)。
ま、私も仕事で校正も、やっているので、職業病みたいなもんですよ。