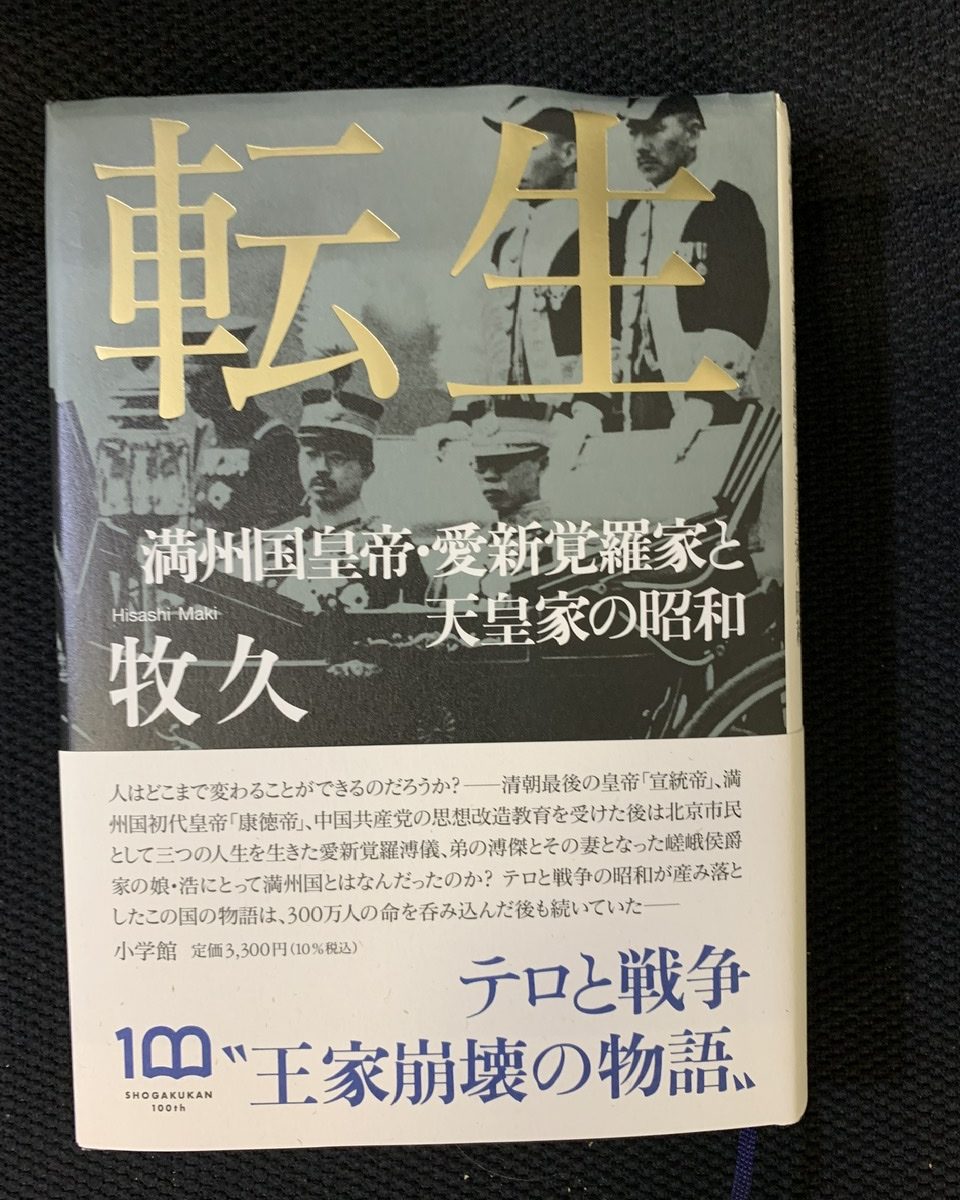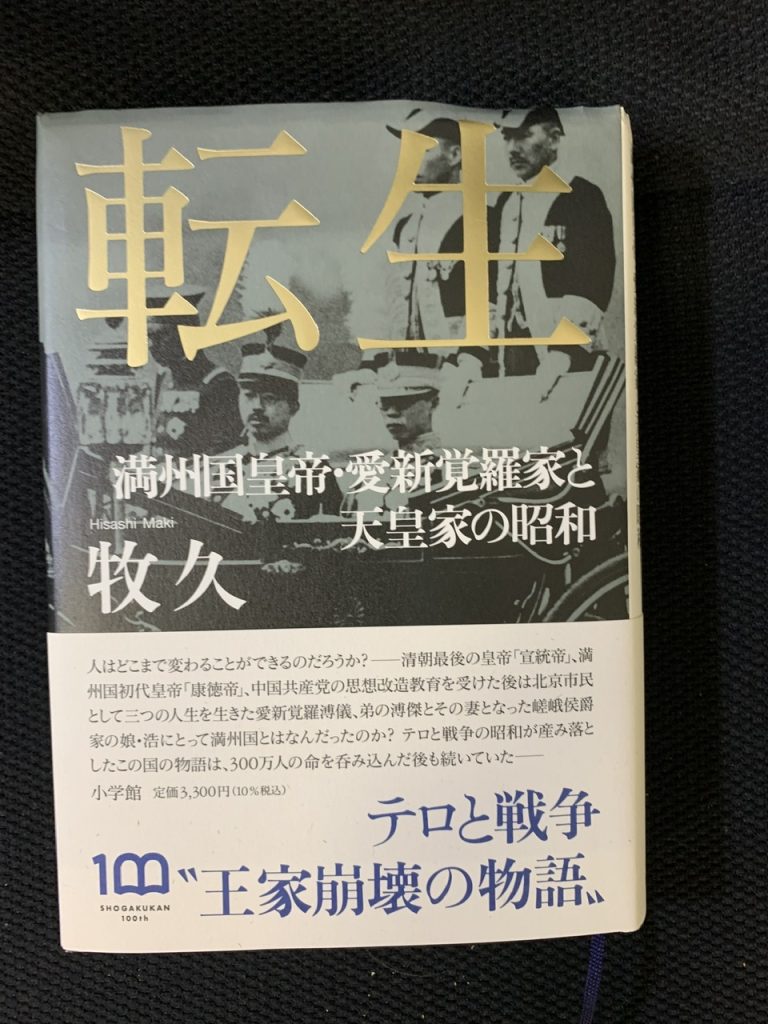8月9日は今年77回目の長崎原爆忌ですが、忘れてはいけないのは、ソ連軍が「日ソ中立条約」を一方的に破棄して満洲(現中国東北部)に侵攻した日でもあることです。
関東軍の精鋭部隊が南方に転戦したため、「もぬけの殻」になった満洲に、独ソ戦に勝利して勢いに乗るソ連軍兵約150万人、戦車等約5500台、戦闘機約3500機が怒涛のようになだれ込み、日本人は民間人を中心に約8万人が死亡し、シベリア抑留や「中国残留孤児」の悲劇も生みました。
ソ連が日ソ中立条約を破棄して侵攻したのは、昭和20年2月4日、米ルーズベルト大統領、英チャーチル首相、ソ連スターリン首相の間で行われたヤルタ会談での密約によるものでしたが、国際条約を平気で反故して侵攻する様は、現在のロシア軍によるウクライナ侵攻を見るようです。77年経っても、少しもロシア人気質が変わっていないようにみえます。会談が行われたヤルタは、ロシアが2014年に併合したクリミア半島にあるというのも何か皮肉か、偶然の一致にさえ思えてきます。
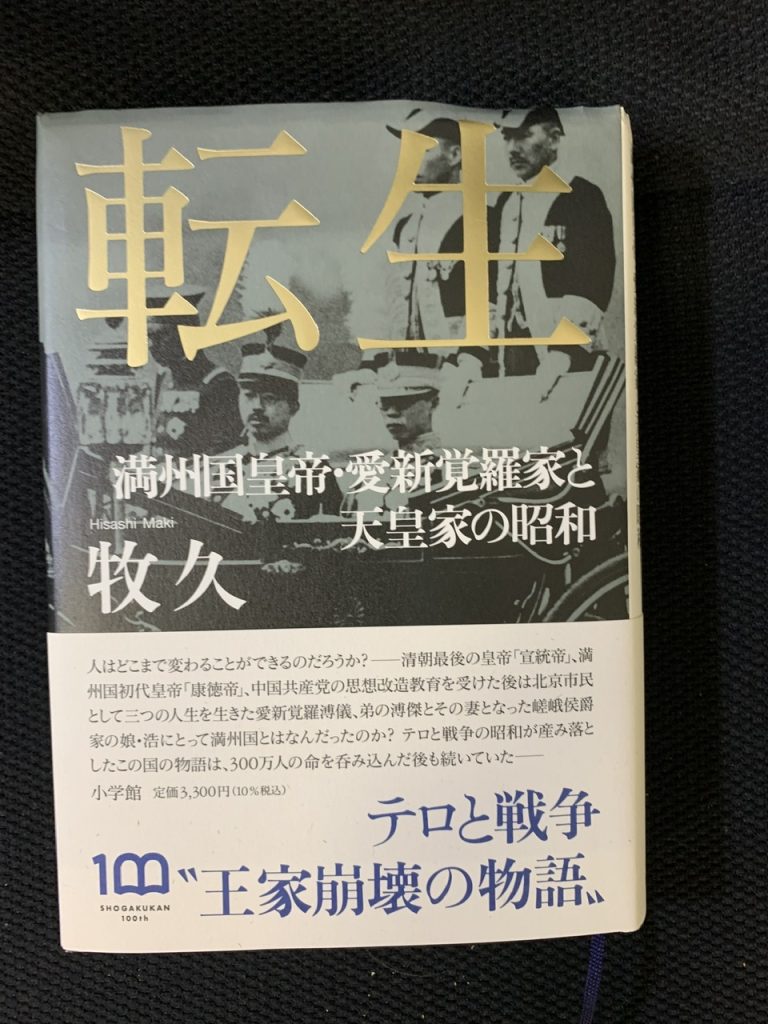
今、ちょうど、献本して頂いたジャーナリスト牧久氏の最新作「転生 満州国皇帝・愛新覚羅家と天皇家の昭和」(小学館、2022年8月1日初版、3300円)を読んでいるところです。著者牧氏にとって、「不屈の春雷 十河信二とその時代」「満蒙開拓 夢はるかなり」(ウエッジ)に続く「満洲物語」第三弾です。日本経済新聞社の副社長等を歴任された牧氏は1941年生まれですから、今年81歳。著者の筆は全く衰えず、個人的感想ながら、いまだに書き下ろしで新作を何冊も書き続ける同氏に対し、尊敬するとともに、腰を抜かすほど驚いてしまいました。
「転生」は、巻末の年表等も入れて493ページという大作です。すぐ読めるかと思ったら、もう読み始めて10日も経っています。それだけ内容が濃いといいますか、牧氏らしい目利きの膨大な文献調査と関連証言等から引き出す的確な推論には説得力があり、読んでいて圧倒されます。
一言で言えば、中国が言うところの「傀儡政権」満洲帝国の興亡を描いた大河ドラマです。主人公を一人挙げるとすれば、清朝のラストエンペラー(宣統帝)であり、満洲国の初代皇帝(康徳帝)に就いた愛新覚羅 溥儀ということになります。
私もこれまで満洲国関連の書籍は結構読んできたつもりですが、溥儀が主人公の本は少なかったでした。そのせいか、中国が断定するような満洲が傀儡政権だったというのは、少し割り引いて考えなければならず、むしろ、溥儀が、日本を利用して、積極的に滅亡した清朝の復辟(ふくへき=退位した君主がまた君位につくこと)を目指していたことをこの本で初めて知ることになりました。
何と言っても、私が一番驚いたことは、昭和10年4月に初めて来日して昭和天皇やその母である貞明皇太后らに拝謁した溥儀皇帝が、すっかり天皇制に心酔してしまい、昭和天皇の困惑にも関わらず、天照大神を満洲国の「元神」とし、帝国内に建国神廟を建立したことです。(「回鑾=かいらん=訓民詔書」)私はてっきり、関東軍の脅迫と圧力によって満洲国内に多くの日本の神社が創建されていたと思っていたのですが、史実はむしろ逆で、皇帝溥儀が率先垂範して積極的に取り入れていたのです。在留邦人でさえ、驚いたり、天照大神が異民族に祀られるのは筋違いと考えたりする者もいたというのですから。
皇帝溥儀は、東京裁判で証人として呼ばれた際、関東軍によって脅迫されて仕方なく皇帝に即位し、単なる操り人形で何の権限もなかった、といった趣旨の証言を、ソ連の筋書き通りに繰り返しましたが、史実は、結構な部分で、清朝復活を願う溥儀が、日本を利用して自分の意志を反映させていたことがこの本を読むとよく分かります。

この本を読む前の今年5月に、私はたまたま平山周吉著「満洲国グランドホテル」(芸術新聞社)を読んでいたので、同じ「満洲もの」では少し切り口が違うなあ、と感じました。「グランドホテル」は、満洲国(1932~45年)で活躍した人物の評伝と相関図に多く紙数を費やし、例えば、「『満洲国のゲッベルス』武藤富男」とか「『満洲の廊下トンビ』小坂正則」といったように、言わば週刊誌的な見出しが並びます。著者の平山氏は、文藝春秋の「文学界」の編集長も務めた経験があるということなので、「グランドホテル」は出版社系ジャーナリズムと言えるかもしれません。
一方のこの「転生」は、著者牧氏が日経社会部記者出身ということで新聞社系ジャーナリズムと言えるかもしれません。歴史学者のように、時系列に淡々と筆致を抑えて叙述し、余計な形容詞は省き、武藤富男は何度も登場しますが、「満洲国のゲッベルス」といった修飾語は出てきません。ただ、筆致が抑えられているとはいえ、内容は通化事件をはじめ、戦争の悲劇の話ですから、涙なしには読めません。
著者の牧氏がこの本を書くきっかけになったのが、千葉市稲毛の自宅近くに、溥儀の実弟で日本の陸軍士官学校に留学した愛新覚羅溥傑と「政略結婚」した侯爵嵯峨実勝(さねとう)の長女浩が新婚時代を過ごした「ゆかりの家」があり、よく訪れ、「激しく移り変わる歴史の荒波の中で、その愛を生涯貫き通した二人の人生ドラマを書き残したいと思った」からだといいます。
溥傑と浩との結婚や二人の娘の慧生(えいせい)、嫮生(こせい)の哀しい物語については、山崎朋子著「アジア女性交流史」(岩波書店)や本岡典子著「流転の子 最後の皇女・愛新覚羅嫮生」(中央公論新社)などを通して私自身も知っておりましたが、改めてその凄惨な波乱万丈の生涯を読んで、自分たちの意志が反映されないまま、歴史に翻弄された被害者のような気がしました。
確かに、著者の牧氏が仰る通り、彼らの人生は、書き残して後世に伝えるべきドラマであり、本書も多くの人に読み継がれなければならないと思いました。