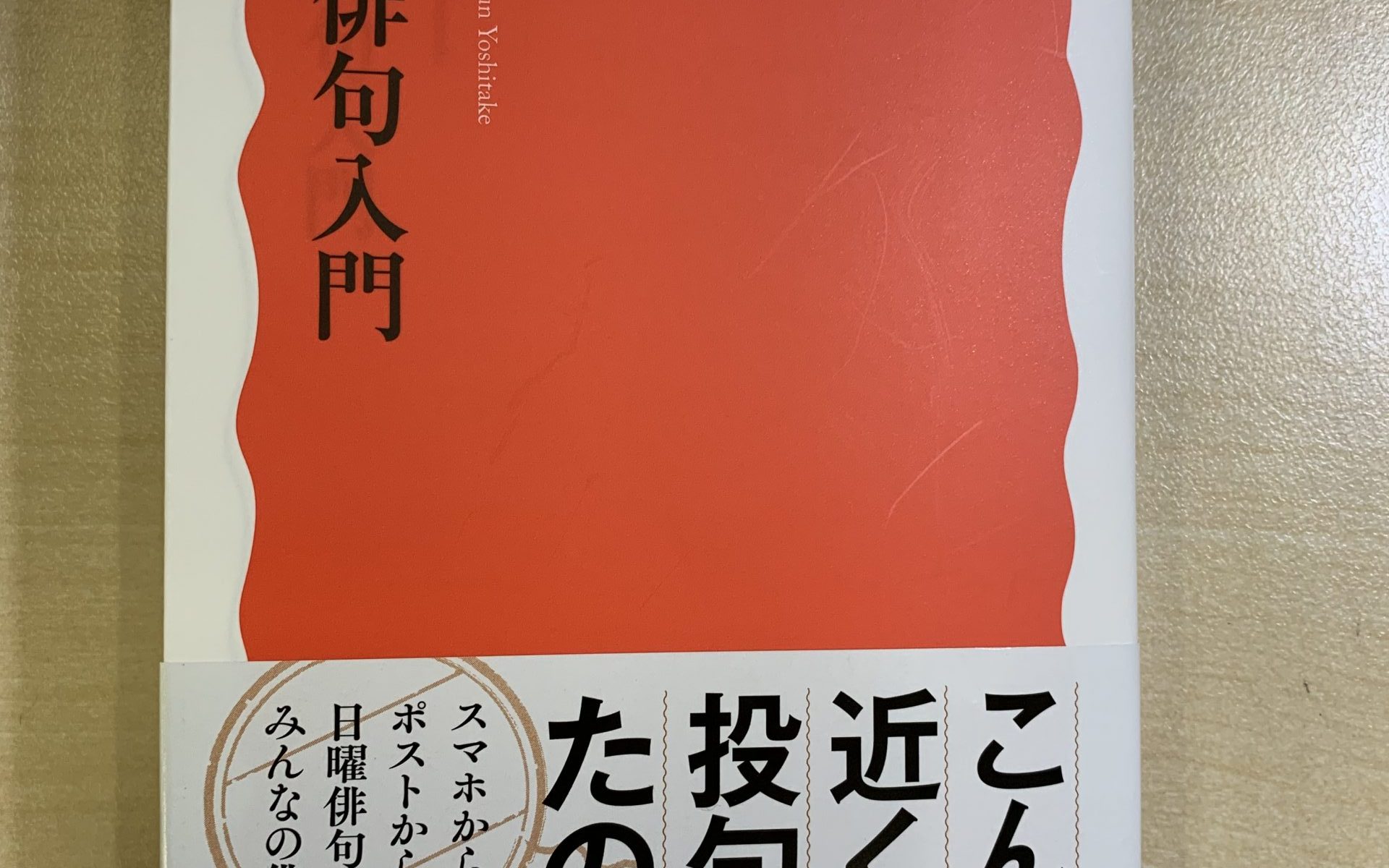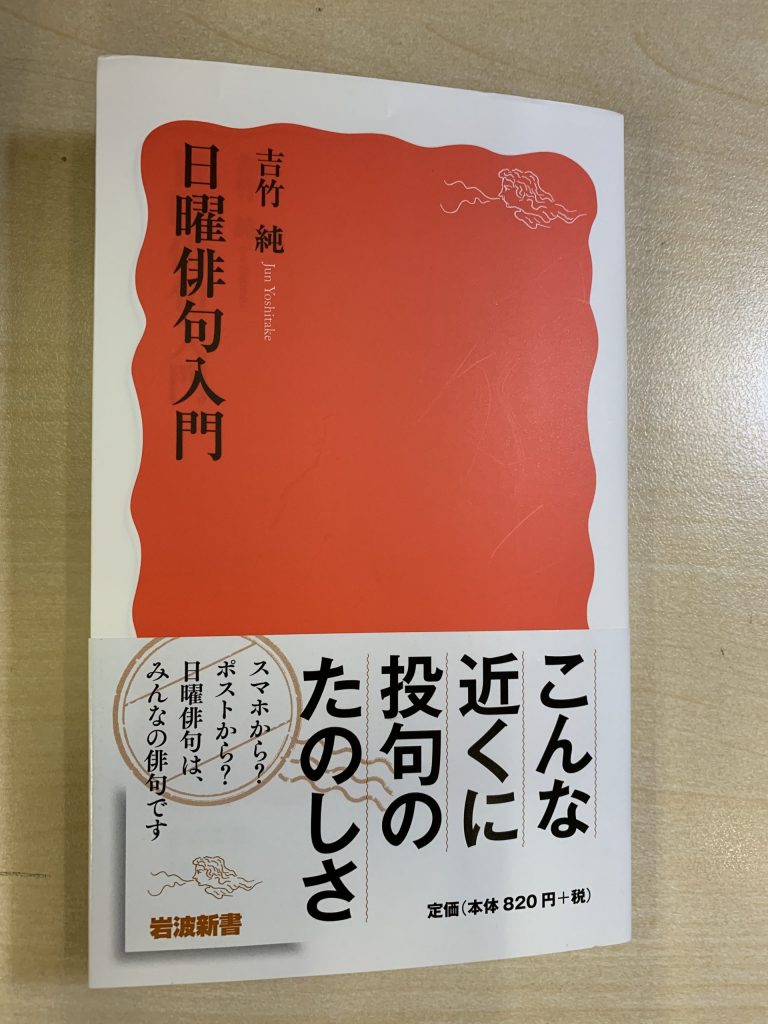WST National Gallery Copyright par Duc de Matsuoqua
先月11月29日に投稿した「こんな近くに遠くの楽しさ=吉竹純著『日曜俳句入門』」 のお話を覚えていらっしゃる方はいないと思われますが、その本を、金子兜太の弟子である俳人の会社の後輩に貸したところ、逆に彼から「この本読んでください」と、借りをつくってしまいました。
それは、小林恭二著「俳句という愉しみ」(岩波新書)という本で、1995年2月20日の初版ですから、もう25年近い昔の本でした。
以前にも書きましたが、小生は、短詩型に関しては「食わず嫌い」ですからね。あまり、読む気がしなかったのですが、「それじゃあ悪い」と思い直して、読み始めたら止まりません。「めっちゃくちゃ面白かった」と正直に告白します。もう四半世紀も前ですから、登場した俳人の中には鬼籍に入られた方も多いですけどね。
吉竹氏の「日曜俳句入門」は、どこの結社にも入らなくても、新聞や雑誌に投句して、腕を挙げて掲載される喜びを楽しめ、といった内容でしたが、この本は真逆で、結社というか、句会に参加して、散々、お互いの句を品評し合って、点数まで付けて、楽しみましょ、といった内容でした。
著者の小林氏はこう書きます。
…俳句は師系を重視する文芸である。…なんとなれば、俳句は個人が独力で生む文芸というよりは、関係性から生まれる文芸だからである。…俳句は詠む人間と読む人間がいて初めて俳句たりうる。そうした場を共にするというところに師系の意味がある。…俳句が成立するためには、座といういわば横の関係だけでなく、時間という縦の関係もまた必要になってくるのである。…(144ページ)
なるほど、そういうわけで、俳人は集団になって、徒党を組んで、吟行したり、合評したりするんですね。
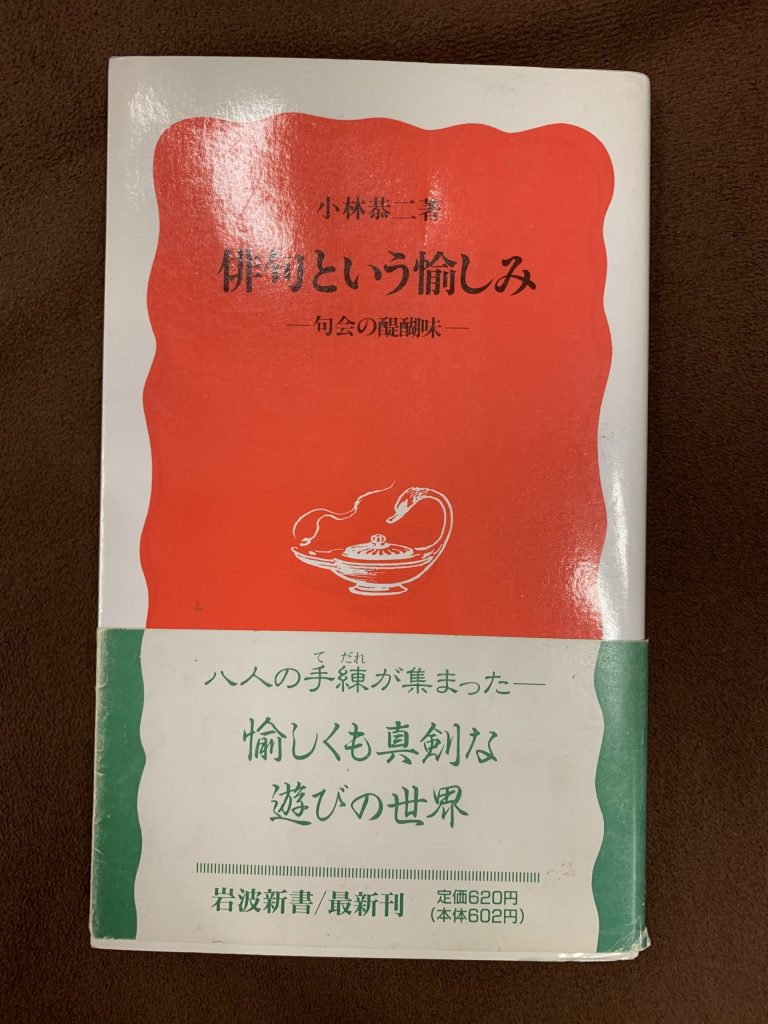
で、この本では、三橋敏雄、藤田湘子、有馬朗人、摂津幸彦といった巨匠ともいうべき俳人8人が句をひねり、合評の面白さを存分なく発揮してくれます。
やり方については、簡略しますが、お題に沿って各自が句作した後、どなたの句か分からないように清書して、ワイワイ、ガヤガヤと選評し合うのです。最も面白かったのは、散々貶した張本人がその句の作者だったりして、一堂大爆笑。「役者やのお~」といった感じで、小芝居を観ている感じになれます。もっとも、かなり真剣勝負ではありますが。
座が開かれた東京都下の御岳の「河鹿荘」には、戦前から活躍していた三橋俊雄先生や前衛短歌の騎手でもある岡井隆先生も参加し、短歌と俳句の違いや、「短歌の方が戦争に協力していた」といった時局的な話も盛り込まれていました。
今さらながらですが、入門書としてはピッタリでしょう。
ちなみに、この句会で最多得点で優勝したのは大木あまり先生。先日もこのブログに書きましたが、詩人の大木惇夫の三女だそうで、言語感覚が冴え渡りました。
30年近い昔、彼女とは2度ほど、何にも分からずに、東京・新橋の居酒屋「均一軒」で10人ほど集まった句会でお会いしたことがありました。会社の先輩に誘われたまま、その場で、俳句の基本も分からず、句をつくり、箸にも棒にも掛からなかったことが苦い思い出として残っています。この本が出版される前の話で、あまり先生も今や大家になられたということですが、当時は、何も知らずに接してしまい、大変失礼致しました。
この本では、例の桑原武夫の「第二芸術論」も出てきて、当然のことながら、桑原武夫のことを俳句のハの字も知らない「フランスかぶれの日本人」と断罪しておりましたが、そう言われると、自分にも矢を向けられているようで、冷やっとしました。
多分、これから、投句したり、句会に参加したりしないと思いますが(ブログを書くのに忙しい!!)、もう、俳句や短歌を「第二芸術」と言いませんから勘弁してください。