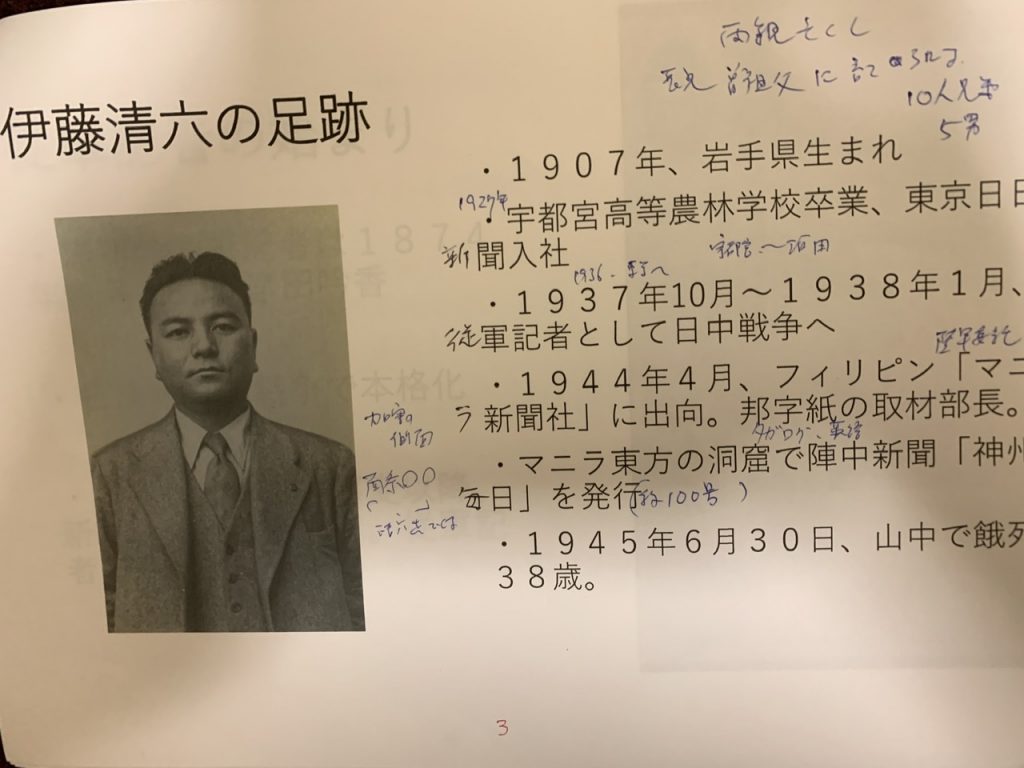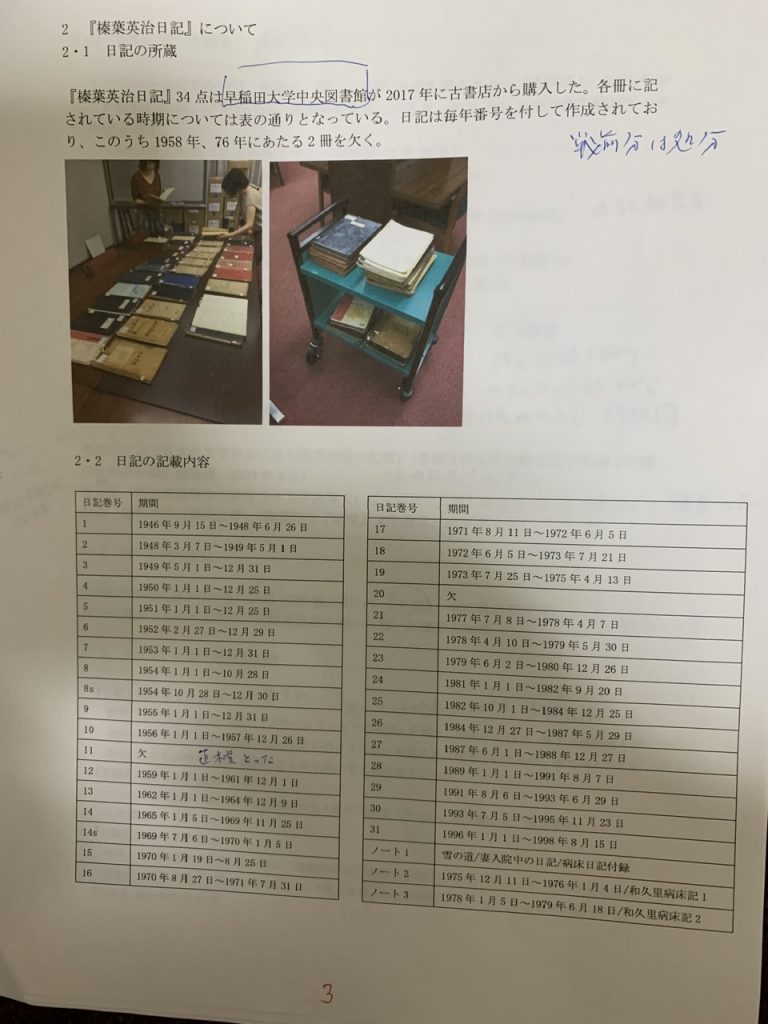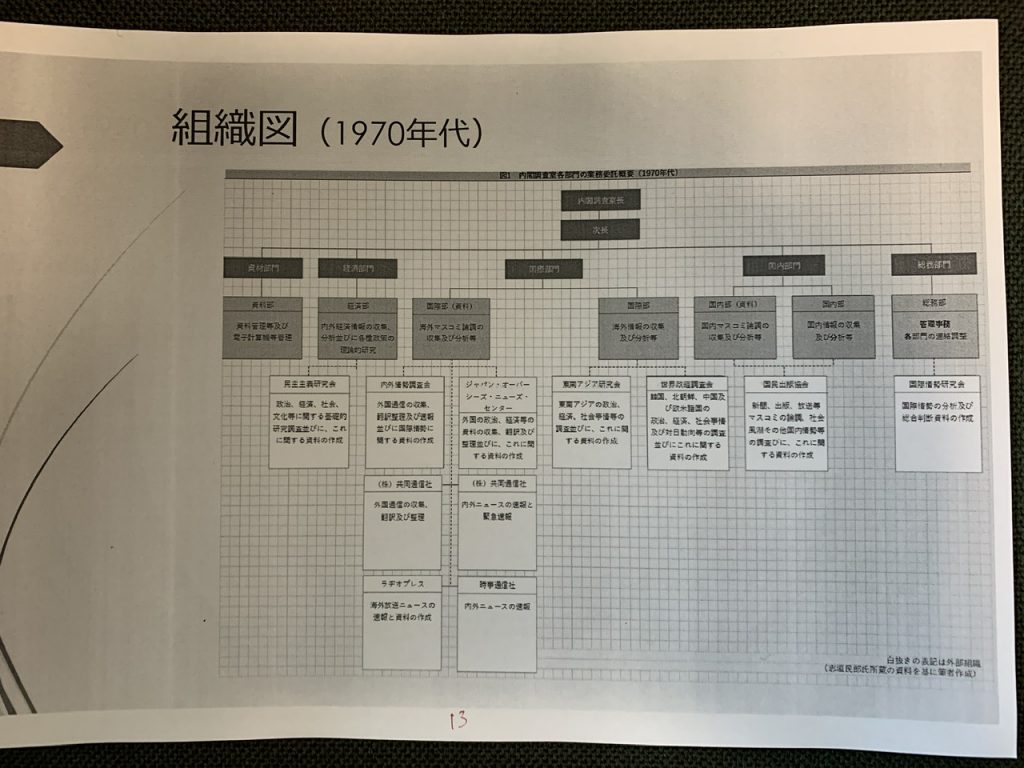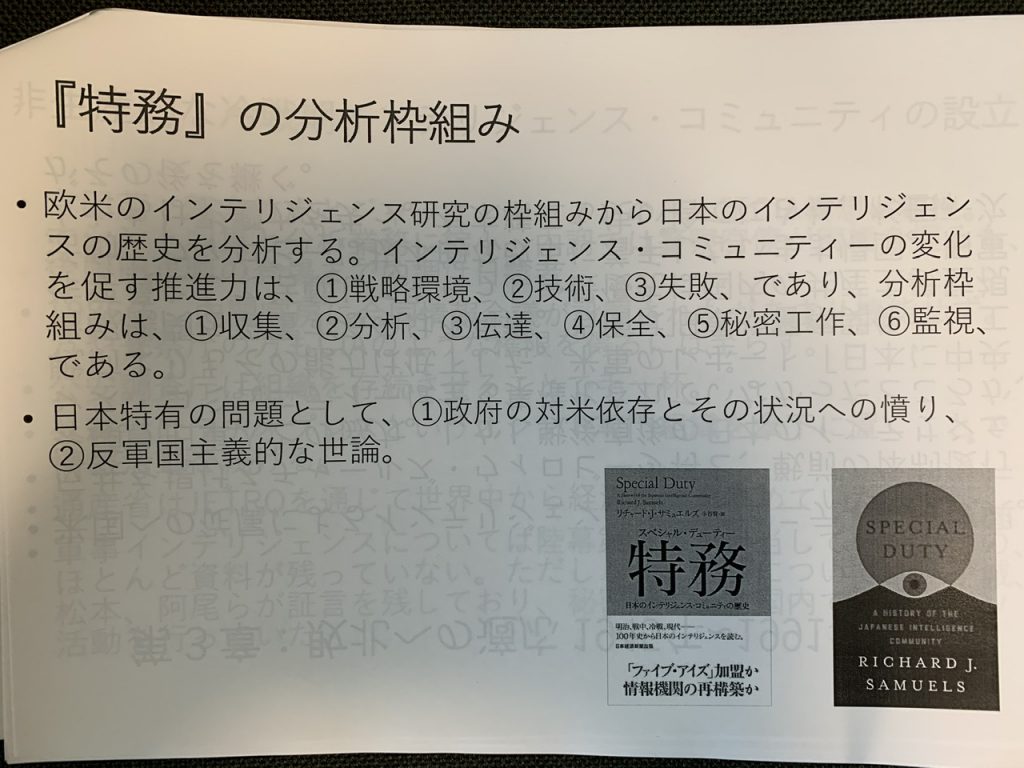3月19日(土)、第41回諜報研究会(NPOインテリジェンス研究所主催、早稲田大学20世紀メディア研究所共催)にオンラインで参加しました。テーマが「日ソ情報戦とゾルゲ研究の新展開―現在のロシア・ウクライナ侵略の背景分析の手がかりとして」ということで、大いに期待したのですが、こちらの機器のせいなのか、時折、画面が何度もフリーズして音声が聞き取れなかったり、チャットで質問しても届かなかったのか、無視、いや、見落としされたりして、途中で投げやりになって内容に集中できなくなり、ブログに書くのもやめようかなあ、と思ったぐらいでした(苦笑)。
ZOOM会議はこれまで何度か参加したことがありますが、フリーズしたのは初めてです。まあ、気を取り直して感想文を書いてみたいと思います。
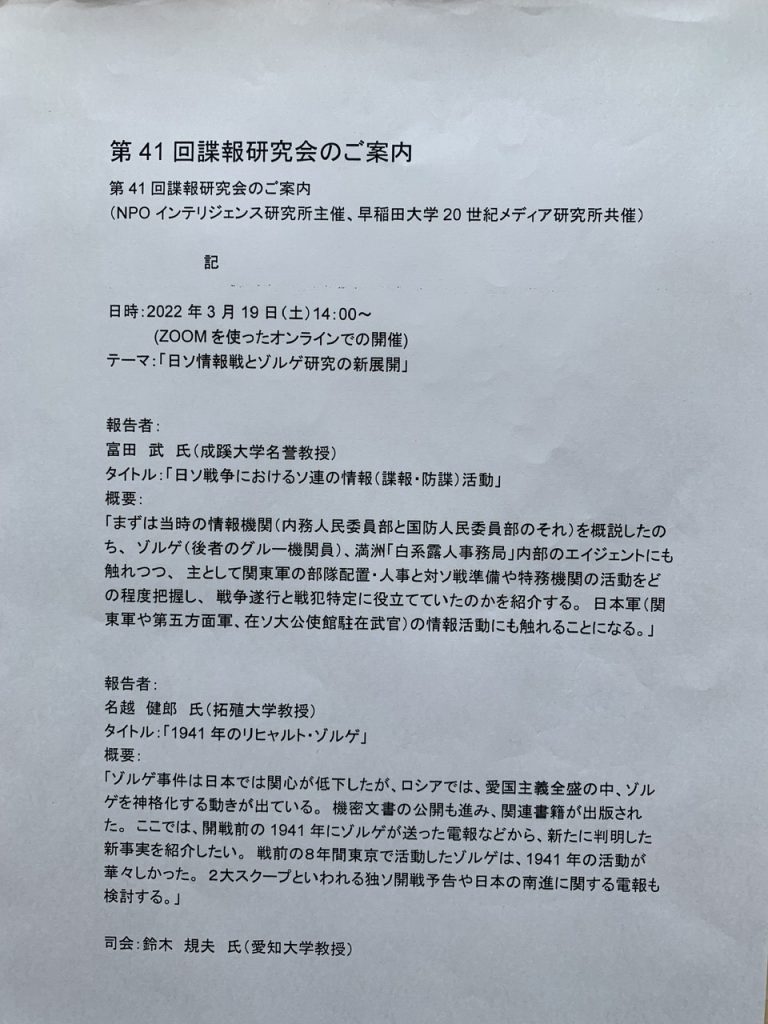
お二人のロシア専門家が登壇されました。最初は、名越健郎拓殖大学教授で、タイトルは、「1941年のリヒャルト・ゾルゲ」でした。名越氏は、小生の大学と会社の先輩で、大学教授に華麗なる転身をされた方ですので、大変よく存じ上げております。…ので、御立派になられた。「でかしゃった、でかしゃった」(「伽羅先代萩」)といった気分です…。現在進行中のウクライナ戦争のおかげで、今やテレビや週刊誌に引っ張りだこです。モスクワ特派員としてならした方なので、他のコメンテーターと比べてかなり説得力ある分析をされています。
ゾルゲ事件に関しては、私自身も、15年以上どっぷりつかって、50冊近くは関連書を読破したと思います(でも、恐らく500冊ぐらいは出ているのでほんのわずかです)。この渓流斎ブログにもゾルゲに関してはかなり書きなぐりました。が、残念なことに、それらのブログ記事は私自身の手違いでほぼ消滅してしまいました。ちょうど、元朝日新聞モスクワ支局長の白井久也氏と社会運動資料センター代表の渡部富哉氏が創設し、私もその幹事会に参加していたゾルゲ研究会の「日露歴史研究センター」も解散してしまい、最近では関心も薄れてきました。(決定的な理由は、ゾルゲ事件に関して、当初と考え方が変わったためです。)
それが、名越教授によると、日本での関心低下に反比例するようにロシアではゾルゲの人気が高まっているというのです。本日のブログ記事の表紙写真にある通り、モスクワ北西にゾルゲ(という名称が付いた)駅(左上)ができたり、ウラジオストックにもゾルゲ像(右下)が建立されたりしたというのです。
また、今や、バイデン米大統領から「人殺しの悪党」呼ばわりされているロシアのプーチン大統領は、2年前のタス通信とのインタビューで「高校生の時、ゾルゲみたいなスパイになりたかった」と告白しており、ロシア国内では愛国主義教育の一環としてゾルゲが大祖国戦争を救った英雄として教えられているようです。
ロシア国内では、GRU(ロシア連邦軍参謀本部情報総局)公文書館や国防省中央公文書館などが情報公開したおかげで、ここ数年、ゾルゲ関係で新発見があり、多くの書籍が出版されています。その中の1冊、アンドレイ・フェシュン(NHKモスクワ支局の元助手で、名越氏も面識がある方だといいます!)編著「ゾルゲ事件資料集 1930~45」(電報、手紙、モスクワの指示など650本の文書公開)の中の1941年分を名越教授は目下翻訳中で、年内にもみすず書房から出版される予定だといいます(私の聞き間違えかもしれませんが)。ゾルゲは独紙特派員を装いながら、実は、赤軍のGRUから派遣されたスパイで、東京に8年滞在しましたが、ゾルゲの2大スクープといわれる「独ソ開戦予告」と「日本の南進に関する電報」は1941年のことで、名越教授が「それ以前は助走期間のようだった」と仰ったことには納得します。
フェシュン氏の本の中で面白かったことは、「ゾルゲの会計報告」です。1940年11月の支出が4180円で、尾崎秀実に200円、宮城與徳に420円、川合貞吉に90円支払っていたといいます。当時の大学卒業初任給が70円といいますから、200円なら今の60万円ぐらいのようです。情報提供料で月額60万円は凄い(笑)。これで、尾崎は上野の「カフェ菊屋」(現「黒船亭」)など高級料理店に行けてたんですね(笑)。もっとも、モスクワ当局は、41年1月に「情報の質が低いので2000円に削減する」と通告してきたので、ゾルゲは「月3200円が必要」と反発したそうです。
もう一つ、GRUはゾルゲ機関以外に5人の非合法工作員を東京に送り込んでおり、そのうちの一人、イリアダは在日独大使館で働く女性で、ウクライナ西部のリヴォフ(現在、戦争難民で溢れている)でスパイにスカウトされ、日本の上流階級にも溶け込んでいたといいます。
在日独大使館のオットー大使と昵懇だったゾルゲとイリアダとは面識があったでしょうが、当然ながら、スパイ同士横の繋がりは御法度で、お互いに諜報員だとは知らなかったと思われます。GRUとは「犬猿の仲」だったロシアの保安機関NKVD(内務人民委員部)も非合法の工作員を送り込んでおり、その一人でコードネーム「エコノミスト」で知られる人物は、天羽英二外務次官ではないかという説がありますが、天羽は1930年、モスクワ赴任中、ハニートラップに掛かり、スパイを強要されたいう理由には、思わず、「あまりにも人間的な!」と思ってしまいました。
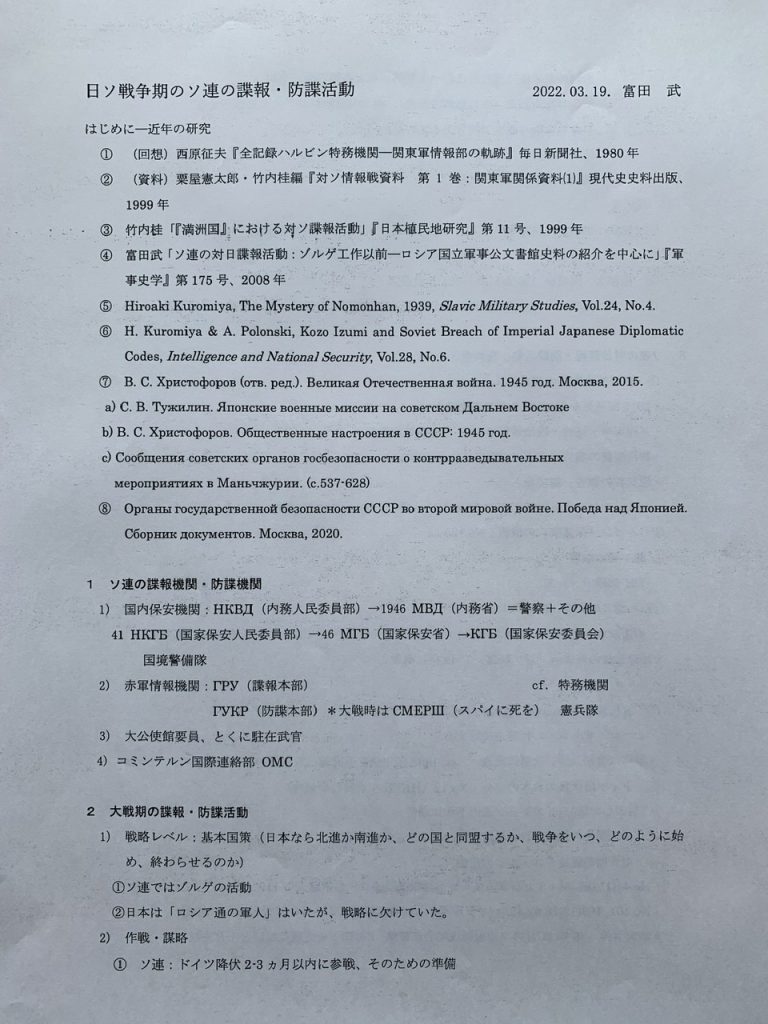
続いて、登壇されたのは、富田武成蹊大学名誉教授で、テーマは「日ソ戦争におけるソ連の情報(諜報・防諜)活動」でした。
大変勉強になるお話でしたが、読めないロシア語が沢山出て来た上、最初に書いた通り、ちょっといじけてしまったのと、加齢による疲れで、内容が頭に入って来なくなってしまい、申し訳ないことをしたものです。(オンラインは嫌いです)
とにかく、ソ連・ロシアの組織はすぐ名称を変えてしまうので、あまりにも複雑で難し過ぎます。諜報機関なら、KGBならあまりにも有名で、それに統一してくれれば分かりやすいのですが、ソ連が崩壊してロシアになった今は、FSB(ロシア連邦保安庁 )というようです。と思ったら、FSBは防諜の方で、対外諜報はSVR(ロシア対外情報庁)なんですね。
いずれにせよ、ゾルゲが活動したソ連時代、ゾルゲは赤軍情報機関のGRUに所属していました。赤軍情報機関の防諜本部の方はスメルシ(スパイに死を)と呼ばれ、満洲(現中国東北部)に工作員を送り込んで、早いうちから「戦犯リスト」を作成していたようです。(だから、8月9日にソ連が満洲に侵攻した際、スムーズに日本兵を捕獲してシベリアに送り込むことができたのです)。日本は当時、「対ソ静謐」政策(日ソ中立条約を結んだ同盟国として、諜報活動も何もしない弱腰外交。ヤルタ会談等の存在も知らず、大戦末期は近衛元首相を派遣して和平工作までソ連にお願いしようとしたオメデタさぶり!)を取っていましたから、その狡猾さは雲泥の差で、既に情報戦では、日本はソ連に大敗北していたわけです。
富田氏によると、ソ連の諜報・防諜機関はほかに、警察組織も兼ねる内務省系の内務人民委員会(NKVD)と1943年までコミンテルンの国際連絡部OMC、それに現在でも「公然の秘密」として存在する大公使館の駐在武官がいるといいます。
KGBから党書記長、大統領に昇り詰めたアンドロポフ、プーチンの存在があるように、ソ連・ロシアは諜報機関の幹部が国家の最高責任者になるわけで、いかにソ連・ロシアは「情報戦」を重視しているかがよく分かりました。
【追記】
ありゃまー、吃驚仰天。
これを書いた後、主催のインテリジェンス研究所のS事務局長からメールがあり、小生がチャットで質問していたこと、それを司会者の方が見落としていたことを覚えてくださっていて、わざわざ、名越教授に直接問い合わせて頂きました。
小生の質問は「ゾルゲが二重スパイだったという信憑性はどれくらいありますか」といったものでした。
これに対して、名越教授から個人宛にお答え頂きました。どうも有難う御座いました。
それにしても、何かあるとすぐに捻くれてしまう(笑)私の性格を見抜いたS事務局長、先見の明があり、恐るべし!