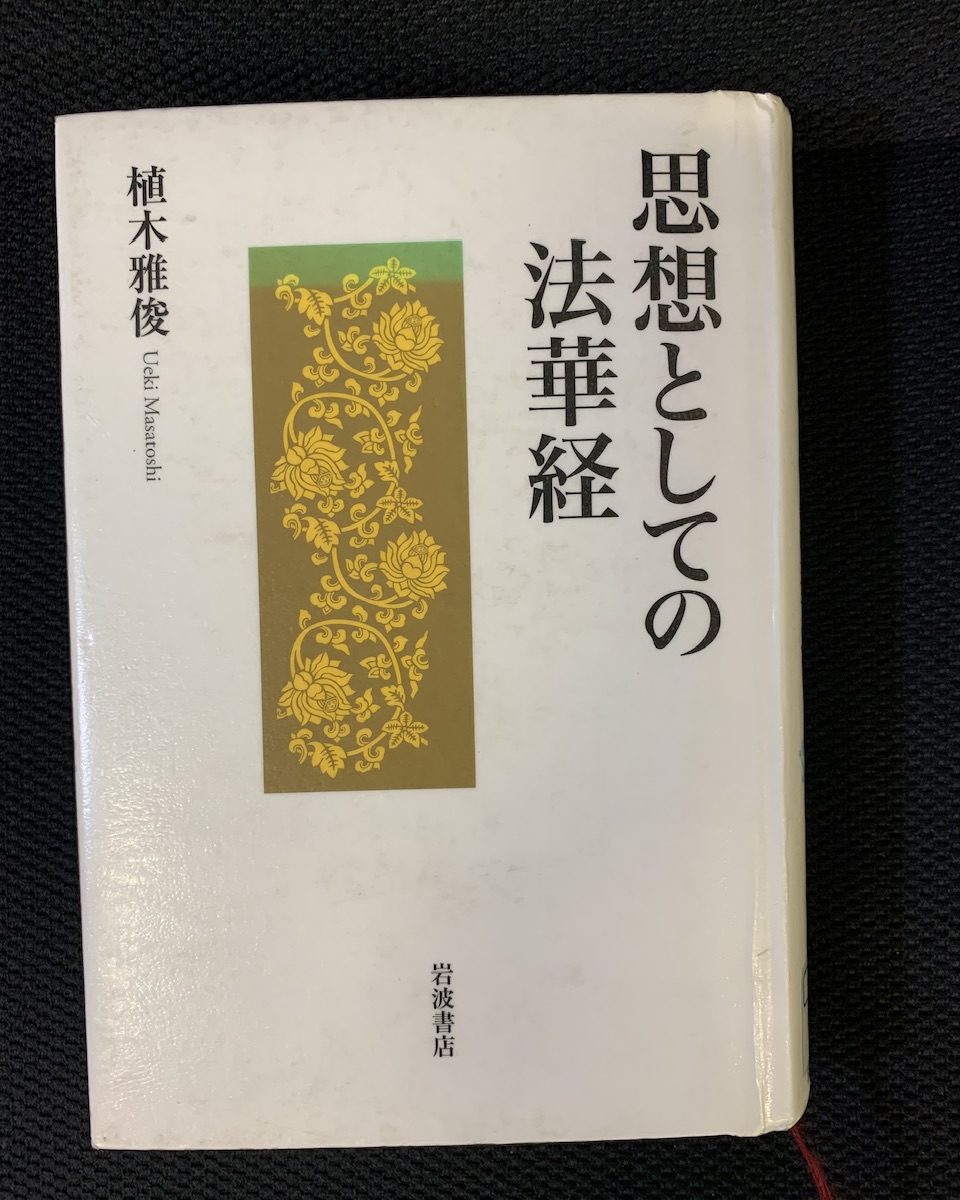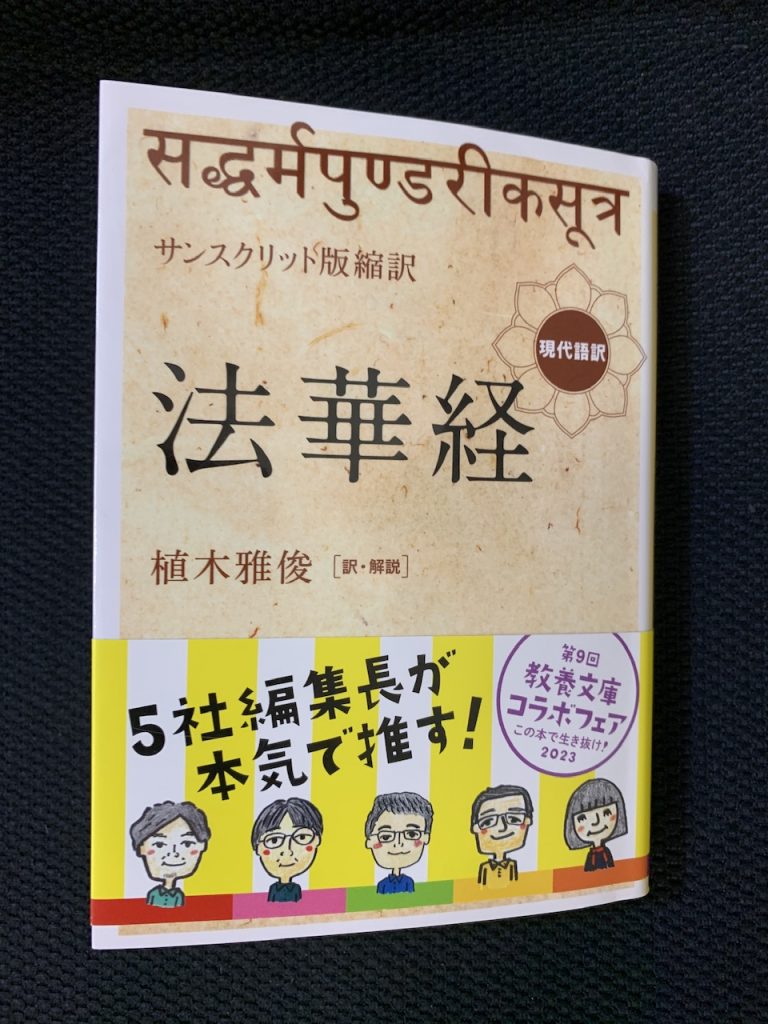植木雅俊著「思想としての法華経」(岩波書店、2012年9月26日初版)を少しずつ読んでおります。個人的に必要に迫られて読んでいるだけですから、特に、他の皆様にお勧めするつもりはありません。宗教(書)となりますと、最近ではどうも⇒教団勧誘 ⇒多額の布施、寄付 ⇒家庭崩壊 ⇒宗教二世といった、人の弱みにつけ込む悪いイメージばかり、拡散されていますからね。
でも、この本はどちらかと言いますと、宗教書ではありますが、哲学書、思想書に近いです。(だから、書名が「思想としての」となっています!)植木雅俊氏のはサンスクリット語と漢訳を参照して「法華経」や「維摩経」を平易な現代日本語に翻訳された仏教思想研究家で、「法華経」の翻訳本「サンスクリット版縮訳 法華経」(角川ソフィア文庫)に関しては、この《渓流斎ブログ》でも何度か取り上げさせて頂きました。(「老若男女、身分の差別なく覚りを啓くことが出来る思想」、「心の安寧を求めて法華経に学ぶ」、「観音さまは古代ペルシャの神様だったのか?」など)
この本は、植木氏御本人が、悩める若き頃、九州大学で物理学を専攻しながら、何故、全く畑違いの法華経に惹かれていったのかといった経緯や、翻訳に際しての苦労話、そもそも釈迦が説法した仏教とは何なのか、そして仏教はどのように変遷していったのか、時系列に解説してくれているので入門書として丁度いいかもしれません。特に、植木氏は自然科学者ですから、良い意味で枝葉末節に非常に拘り、原本であるサンスクリット語を丹念に参照しないで、「推定」で論を進める東京大学出身などの権威者による先行研究に対する批判が度を超すほど妥協がなく、その舌鋒の鋭さは常軌を逸するほどです。サンスクリット語の複雑な文法や用例も例証して論破しているので、植木氏の方に軍配が上がると私も思います。

特に、「法華経」というタイトルです。サンスクリット語で「サッダルマ・プンダリーカ・スートラ」と言います。「サッダルマ」は、「サット」(正しい)と「ダルマ」(法、教え)の複合語で「正しい教え」、「プンダリーカ」は「白蓮華」、「スートラ」は「経」を意味します。これを、月支系帰化人の末裔として敦煌に生まれた竺法護(じく・ほうご=239~316年)は「正法華経」と漢訳し、西域の亀茲(きじ)出身の鳩摩羅什(くま・らじゅう=350~409年)は「妙法蓮華経」(略して「法華経」)と漢訳しました。
日本では、岩本裕博士によって「正しい教えの白蓮」と現代語訳され、長年、この訳が大半で採用されましたが、植木氏は異議を唱え、サンスクリット語の文法からも「白蓮華のように最も勝れた正しい教え」と訳すのが正しいと主張されたのでした。詳細はこの本に譲りますが、確かに説得力があり、植木氏翻訳の方が良いと私も思います。ただし、新聞協会の用語では、「勝れた」は「常用漢字表にない音訓」ということで使えず、「優れた」を使います。ということで、法華経とは、「白蓮華のように最も優れた正しい教えのお経」ということになります。
何故、数多あるお経の中で、法華経なのかに関しては、日本の歴史上の人物がかなり多く影響を受けていることを本書で取り上げています。例えば、「源氏物語」の紫式部、「更級日記」の菅原孝標の女、「梁塵秘抄」を編纂した後白河法皇、歌人藤原俊成、俳人松尾芭蕉、文楽の近松門左衛門、それに私も大好きな長谷川等伯や本阿弥光悦らもです。近代になると宮沢賢治や石原莞爾辺りになるでしょうか。また、法華経に影響を受けた宗教家として天台宗の最澄と日蓮宗の日蓮(それに「国柱会」の田中智学や血盟団事件の井上日召も入れますか?)はあまりにも有名ですが、曹洞宗の道元もそうだということで自らの不勉強を恥じました。主著「正法眼蔵」に引用された経典は「法華経」が最も多いというのです。
このように、法華経は経典だとはいえ、特定の教団や宗教家の専有物ではなく、人類の知的遺産として誰のものでもある、というのが私の考えです。人間というものは、か弱く、生きているだけで、苦しみや悩みが尽きません。稀にみる平等思想を説いた法華経には、必要とする誰もが簡単にアクセスする権利があると思っております。

物理学を専攻する学生だった植木氏は、中村元著「ブッダ最後の旅」の中で目を見開かされる文章に出合います。それは原始仏典の「自帰依」「法帰依」に書かれたもので、
「この世で自らを島とし、自らを頼りとして、他人を頼りとせず、法を島とし、法を拠り所として、他のものを拠り所とせずにあれ」というフレーズです。植木氏はこれを読んで「虚栄心の塊で毀誉褒貶にとらわれ、他人の視線ばかり気にしていた自分が恥ずかしくなった」といいます。
この「自帰依」「法帰依」は、釈尊亡き後に、誰を頼って生きていったらよいのか不安を抱く弟子のアーナンダ(阿難)に対して、釈迦が遺言のように説いたものだといいます。
植木氏はこう言います。「これは、他者に依存しようとすることを戒めた言葉である。…一人の人間としての自立した生き方は、他者に迎合したり、隷属したり、依存したりするところから生まれてこない。自らの法(ダルマ、理法)に目覚め、それを拠り所とするところに一個の人間としての自立と尊厳が自覚される。それが仏法の目指したものである。」
この本の中で、この箇所を私も大変感動して読みました。人はか弱いので、どうしても他者とつるんでしまいがちです。それが人間ですから。しかし、他者に迎合したり、隷属したり、依存したりせず、自らの法に目覚めること。それが覚りだとしたら、断食やら千日回峰やらの苦行をせずとも、在家でもできそうです。
私がもう一つ付け加えるとしたら、「他者を支配しない」ことですね。国家を名分として他国を侵略することも含まれます。他者に依存しないということは、同時に他者を支配しないことであり、孤立無援を恐れないということにつながると思います。
ということで、この本は必要に迫られた人が読む本であり、思想書としてよく考えさせられ、良書だと思います。
【追記】2023年5月18日
やっと読了できました。正直、かなり難解な本でしたが、個人的には、大変信頼できる、これから仏教を学ぶ上での羅針盤のような本だと思いました。筆者の植木氏によると、法華経とは釈尊が多くの衆生に分け隔てなく分かってもらえるように比喩を多用して平易に述べた言葉(お経)だというのですから、斜に構えたりせず、そのまま純真に受け止めたいと存じます。
補足したいことは釈迦(紀元前463~383年)入滅後の流れです。まず、原始仏教では、在家や女性も排除されていなかったのに、紀元前3世紀末頃、「部派仏教(小乗仏教)」が起き、釈尊が神格化されます。そして、苦しい修行を経た出家した男子だけしか覚りを開けないという思想となり、在家や女性を軽視するようになります。代表的なのが「声聞」と「独覚(縁覚)(辟支仏=びゃくしぶつ)」です。声聞は、声聞乗(シャラーヴァカ・ヤーナ)に乗り、目的地「阿羅漢果」を目指しますが、「仏陀」にまでは到達しません。独覚は、独覚乗(プラティエーカ・ブッダ・ヤーナ)に乗り、「独覚果」を目指しますが、やはり仏陀にまで到達しません。声聞と独覚を二乗と言います。紀元前2世紀頃、小乗の有力教団だった「説一切有部」などが菩薩という言葉を使い始めます。
この後、紀元前後に「釈尊の原点に帰れ」という復興運動が始まり、「大乗仏教」が起こります。大乗は、菩薩の立場から、在家と出家の男女が覚りを開くことができますが、小乗仏教の声聞と独覚の二乗は除きました。菩薩は、菩薩乗(ボーディサトヴァ・ヤーナ)の乗って、仏陀を目指します。つまり、出家しようがしまいが、男だろうが女だろうがいずれも覚りを開くことができるという思想です。
しかし、これでもまだ足りない。そこで、紀元1~3世紀初めに生まれたのが法華経です。植木氏が翻訳した「白蓮華のように最も優れた正しい教えのお経」です。大乗仏教が排除した声聞、独覚の二乗も含む一切衆生(出家、在家の男女)を「一仏乗」(ブッダ・ヤーナ)に乗せて覚りを開くことに止揚した、誰一人差別のない究極の思想(皆成仏道=かいじょうぶつどう)が法華経だったのでした。