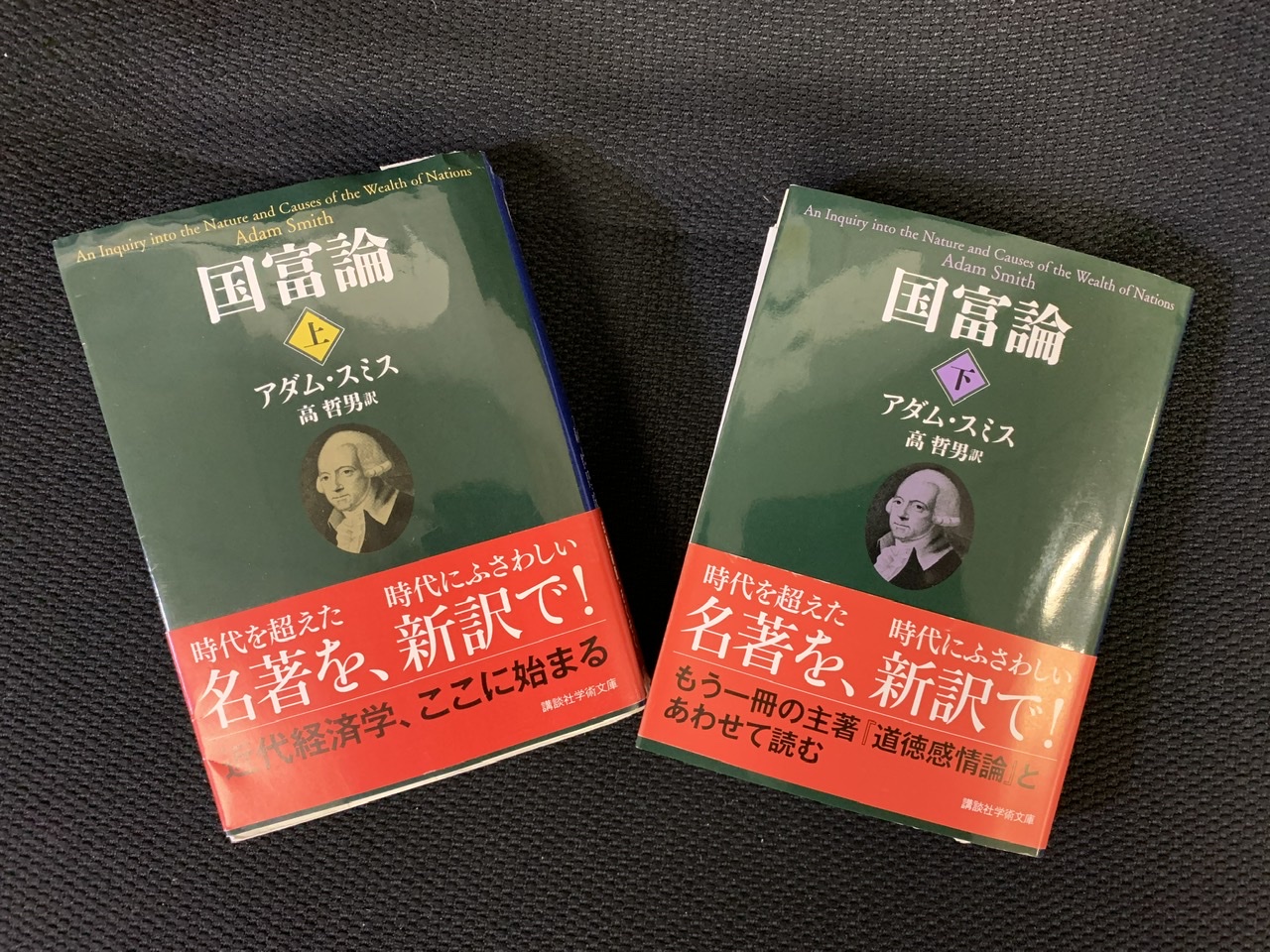渓流斎ブログ昨年12月3日付で「予想外にも超難解な書=アダム・スミス『国富論』」を書きましたが、やっと高哲男・九州大名誉教授による新訳(講談社学芸文庫)の上巻(727ページ)を読了し、下巻(703ページ)に入りました。上巻を読むのに2カ月かかったということになります。
もっとも、毎朝通勤電車の中で10ページほど読むのが精一杯でしたから、それぐらい時間がかかるのは当然です。でも、我ながら、途中で投げ出さず、よくぞここまで我慢して読破したものだと感心しています。
できれば読書会にでも参加して、専門家の皆さんに色んな疑問に応えてもらえれば、読解力も深まることでしょうが、いかんせん、独学ですから仕方ありません。
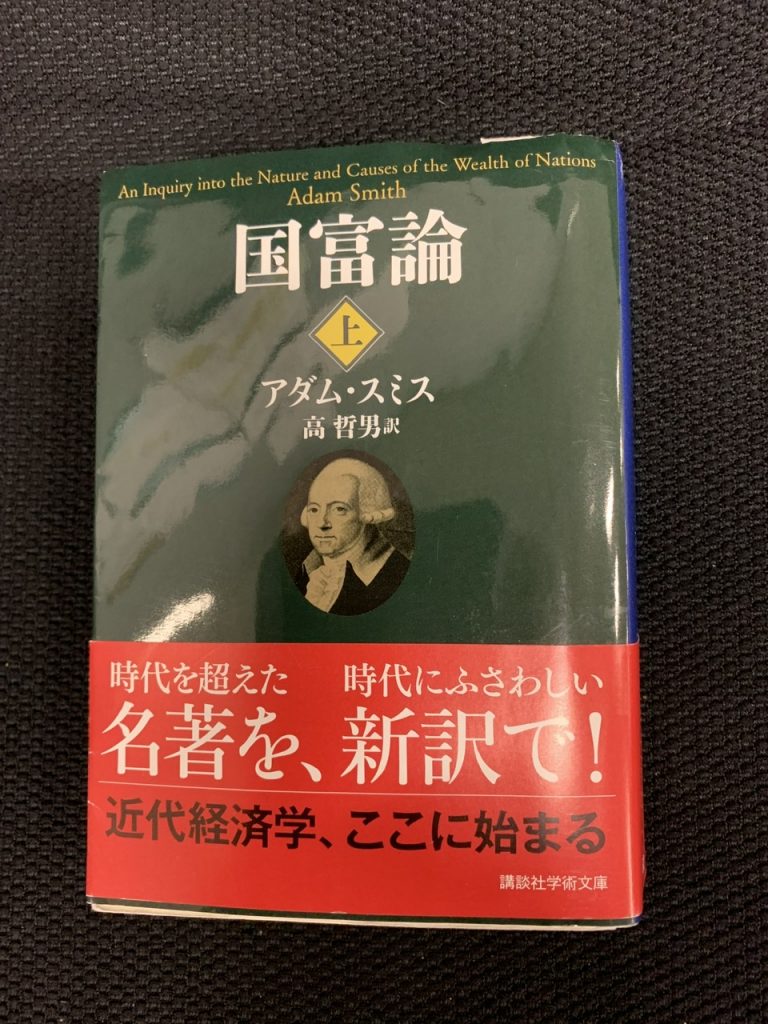
それでも、下巻の巻末にある「訳者解説」は非常に役に立ちます。「なあんだ、スミス先生はそういうことを言いたかったのか」と分かります。この訳者解説に触れる前に、アダム・スミスの「国富論」で最も有名なフレーズで人口に膾炙している「見えざる手」を上巻で発見することができました。
それは上巻653~654ページの「第四編 政治経済学の体系について」の「第二章 自国で生産可能な財貨の外国からの輸入制限について」の中にありました。引用すると以下のように書かれています。
つまり、すべての個人は、労働の結果として、必然的にそれぞれ社会の年々の収入の可能なかぎり最大にするのである。事実、個々人は、一般的に公共の利益を促進しようと意図しているわけではないし、それをどの程度促進するか、知っているわけでもない。外国産業よりも国内産業の維持を選択することによって、彼は、たんに自分自身の安全を意図しているにすぎず、その生産物が最大の価値を持つような方法でその産業を管理することにより、彼は、自分自身の利益を意図しているのであって、彼はこうするなかで、他の多くの場合と同様に、見えない手に導かれて、彼の意図にはまったく含まれていなかった目的を促進するのである。
どうですか? これを読んで、即、頭にすっと入って理解できる方は秀才ではないでしょうか? 煩悩凡夫の私は何度か繰り返し読んで、何となくおぼろげに分かったような分からないような感じです。「国富論」はこのような「名文」に溢れているのにも関わらず、古典として長い間、世界中の人類によって読み継がれてきたわけですから、襟を正して読むしかありません。

そんな秀才になれなかった人たち向けには「訳者解説」が大いに役に立ちます。国富論の初版が出たのは1776年のことです。第六版が出たのが1791年ということですから、まさに、余談ながら、ちょうど天才モーツァルト(1756~91年)が活躍した時期とピッタリ合うのです。訳者の高哲男氏によるとー。
・18世紀末に「国富論」が高く評価された最大の理由は、スミスが重商的な経済政策、保護主義政策(関税や助成金など)を根本的に批判したからだ。
・19世紀になると農業保護政策が放棄され、英国は自由貿易の旗印の下で世界市場を席捲。基本的に「自由放任」「自由競争」の時代となり、自由競争こそが最も効率的で急速な経済発展を可能にすると主張する「国富論」はもう当たり前の話でお役目御免となり、注目されなくなる。
・19世紀末から20世紀になると、慢性的な低賃金と周期的に襲う不況により、労働組合運動や社会主義運動が高まり、理論的支柱として「国富論」が再度注目されるようになる。
・20世紀半ばになると、「市場の効率性」を強調する産業組織論として解釈されるようになる。やがて市場万能主義に利用され、有効需要創出など政府の完全雇用政策は、インフレを引き起こすだけでなく、労働者に与えた既得権に役立つだけだ、という批判が人気を呼ぶ。
・効率性の観点から「規制緩和」や、自由競争の復権を唱えるネオ・リベラリズムが台頭し、スミスの思想は、市場経済は自由競争にしておきさえすれば、神の「見えざる手」に導かれておのずと最大かつ効率的な生産を実現するから、皆ハッピーとなる、という解釈が施される。
ということで、「めでたし、めでたし」という話になりますが、訳者の高氏は、「これは全く嘘ではないが、それほど単純ではない」と強調しています。
私自身は、そんな単純ではない複雑な内容を解明したいがために、下巻を読み続けていきたいと思っています。
【追記】
カトリーン・マルサル著「アダム・スミスの夕食を作ったのは誰か?」(河出書房新社)が最近売れているそうですね。「我々が食事を手に入れられるのは、肉屋や酒屋やパン屋の善意のおかげではなく、彼らが自分の利益を考えるからである」と論じたスミスは、生涯独身で、母や従姉妹に周りの世話をしてもらっていたと、著者は指摘。私自身は未読ですが、経済学は万能の科学ではないし、何でも(愛さえも)軽量化して我々を統治するな、といった主張に近いようです。
これでは、スミス先生も形無しですね。