やっと、浜田義一郎著「大田南畝」(吉川弘文館)を読み始めています。この本は、6月に東京都墨田区の「たばこと塩の博物館」で開催された「没後200年 江戸の知の巨星 大田南畝の世界」展の会場で販売(2200円)されていたものでした。初版が1963年2月20日となってますから、60年ものロングセラーです。大田南畝に関する伝記・評論本は、この本を超えるものがあまり出ていないせいなのかもしれません。
兎に角、この本は6月に最初に15ページほど読みましたが、他の本に取り掛かっていたら、内容をすっかり忘れてしまい、もう一度最初から読み始めています。というのも、登場人物の名前がなかなか頭に入って来ないからなのです。
例えば、大田南畝の師匠に内山賀邸(1723~88年)という人がいました。名は敦時(あつとき)、号は陳軒(ちんけん)、牛込加賀屋敷に住んだので賀邸(がてい)とも号しました。私塾を開いて、漢学も教えましたが、国学が主で、和歌は当時江戸六歌仙の一人に数えられたといいます。その賀邸の門人、つまり南畝の同門に小島謙之(けんし)という四谷忍原横丁に住む幕臣がおりました。通称は源之助。年は南畝より6歳上。和歌が得意で、20歳ごろから狂歌をつくり、橘実副(たちばな・みさえ)という狂名を名乗っていました。それが、師の賀邸から狂歌を褒められ、唐衣橘洲(からごろも・きっしゅう=1743~1802年)と師によって改名されたといいます。小島謙之は、小島源之助であり、橘実副でもあり、唐衣橘洲でもあるわけです。
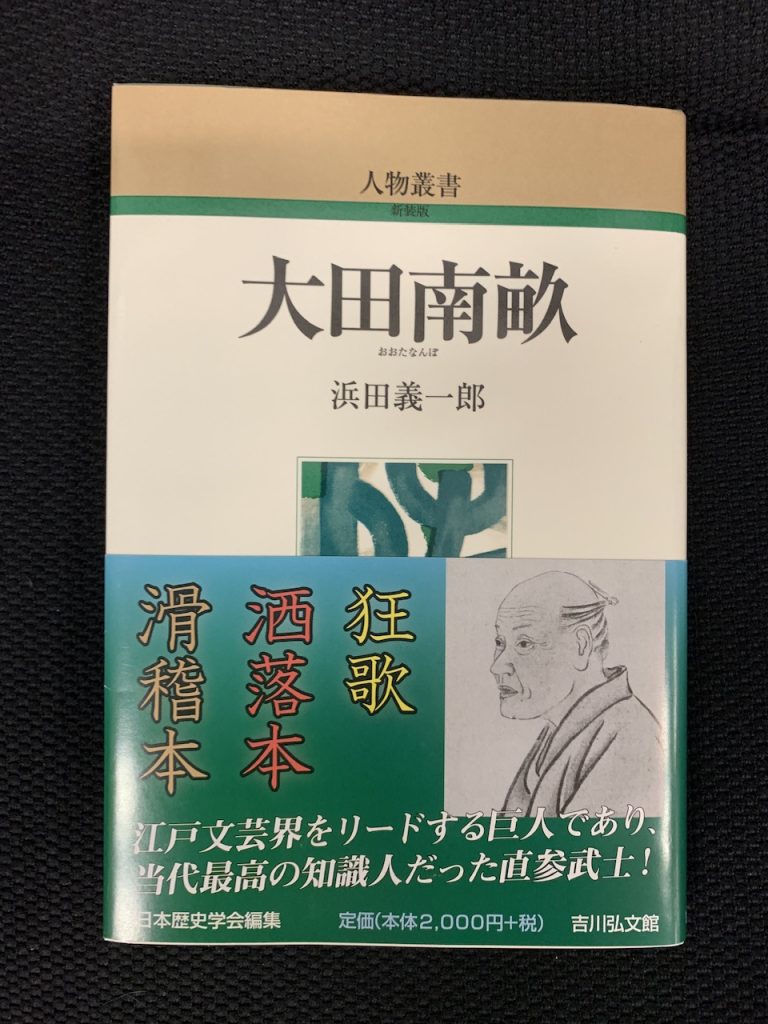
このように、同一人物なのに、本名(諱)の他に、通称や雅号や狂名や字(あざな)まで出てきて、頭がこんがらがってしまうのですよ。日本人は古来から、本名をあけすけに言われることを忌み嫌いました。そこから、本名のことを諱(いみな)と言われます。(だから、目上の人に対しては、官職名や住んでいる所=例えば、鎌倉殿=などで呼び掛けしたのでした)通称というのは綽名(あだな)のような別名のことです。一方、字(あざな)となると、中国で始まった風習で、元服して本名以外に正式に付けられた名前のことを言います。特に漢学の素養のある日本人は好んで付けたといいます。最後に、雅号は、文人や画人が自称した名前ですね。
こうなると、一人の人間が幾つもの名前を持つことになります。でも、こういうのは個人的には大好きですね。ですから、私も、渓流斎と号し、複数の名前や雅号を持っているわけです(笑)。
この本の主人公である大田南畝(おおた・なんぽ=1749~1823年)は、江戸牛込仲御徒町生まれで、御徒(おかち)職の幕臣です。御徒職というのは、文字通り、将軍らが公用や鷹狩りなどで出掛ける際に、徒歩で側に仕える一番下っ端の直参のことです。本名が直次郎で、南畝は号です。中国の古典「詩経」の「大田(だいでん)篇」から取られたといいます。同時に、ここから、子耜(しし)を字(あざな)として取っています。でも、これだけでは済みません。19歳の時に出版した詩文集のタイトル「寝惚先生」は晩年になるまで呼ばれ、22歳の頃に狂名として名乗った四方赤人(よもの・あかひと)、後に四方赤良(あから)もあります。また、30歳代後半から、幕臣としての仕事に専念するためいったん文芸の筆を折りますが、乞われて断り切れずに再開した際、匿名として名乗ったのが蜀山人でした。他に、風鈴山人、山手馬鹿人、姥捨山人などの筆名も使っています。
幕臣大田直次郎は知られていなくても、大田南畝も四方赤良も蜀山人も歴史に名を残しています。一人でこれだけ複数の名前を残す偉人も多くはいません。
大田南畝は19歳から本格的に文芸活動を始め、いわゆる文芸サロンのようなものを開催したり参加したりしますが、その幅広い交際には目を見張ります。江戸時代は、士農工商のガチガチの身分社会と思われがちですが、南畝は幕臣なのに、町人とも気軽に交流します。特に平秩東作(へずつ・とうさく=1726~89年)という町人は、南畝に多大なる影響を与えた戯作者であるといいます。南畝より23歳年長で、内山賀邸の同門でした。東作は、稲毛金右衛門という町人で、内藤新宿で煙草屋を営み、文学を好んで立松東蒙と称し、字は子玉。「書経」から取った平秩東作を筆名にしたといいます。この東作の親友に川名林助という漢詩人がおり、大田南畝はこの川名を通して、あの平賀源内と相知ることになります。

有名どころとの交際と言えば、ほかに、戯作者の山東京伝、版元の蔦屋重三郎、絵師の鈴木春信、勝川春章(北斎の師)、葛飾北斎、谷文晁、歌舞伎役者の五代目市川團十郎(写楽が描いた有名な「市川鰕蔵の竹村定之進」)、それに塙保己一らがおり、大田南畝は、華やかな江戸文化の中心人物だったとも言われています。
ところで、狂歌というのは、私自身、江戸時代に大田南畝によって開始された文芸だと勝手に誤解していたのですが、史実は、鎌倉時代初期(平安時代という説も)から、既に歌会や連歌会の余興として行われていたといいます。和歌と同じ五七五七七ですが、和歌とは違って、風刺や諧謔に富んだものです。そのせいか、当初は、座興による読み捨てにするべきものとされていたようです。大田南畝の時代である江戸中後期が全盛期のようで、明治以降は廃れてしまったようです。
本日はこれだけ書いて、いっぱい、いっぱいになりました。続きはまた次回に。

