あまり自己主張しない会社の同僚の本岡君が珍しく、「Eテレの『フランケンシュタインの誘惑』という番組、観てますか?面白いですよ。木曜夜10時からです。もし、まだでしたら是非。お勧めです」と言うではありませんか。そこまで言うならということで、私も見てみました。
科学は人類の進歩の面で、大きな恩恵をもたらすと同時に、人間を大量に殺戮する兵器を発明したりする負の面を持っています。善良な人造人間を作ろうとして失敗して怪物を作ってしまったフランケンシュタイン博士のような「マッド・サイエンティスト」を毎回取り上げた番組でした。私は見逃しましたが、私が子どもの頃に「偉人」として崇められていたラジウムを発見したキュリー夫人なんかも取り上げられ、実はラジウム光線を浴びて顎が突出するなど人体に影響を受けた実験学生なんかも登場し、「負の面」も映し出したようでした。
さて、先週、この番組を観たのですが、主人公は、今何かと話題になっている人工知能(AI)の概念を人類で初めて考案した英国のアラン・チューリング(1912~54年)でした。私は彼の名前を何かの本で、チラッと拝見した程度で、どんな人が知りませんでしたが、この番組を観て初めて分かりました。
アラン・チューリングは今でこそ、「コンピュータ科学の始祖」と崇められています。しかし、存命中は、ナチス・ドイツの暗号「エニグマ」(謎)を解読するのに貢献しながら、軍事機密の「ウラトラ・シークレット」とされたことから、業績が秘匿され、悲運のまま41歳の若さで自ら命を絶ってしまうのです。
アラン・チューリングの本職は、名門ケンブリッジ大学を出た数学者でしたが、生い立ちから悲運といってもいいでしょう。両親は当時英国の植民地だったインドに赴任する際、小さいアランを知人に預けます。そのせいか、アランは、子どもの頃から孤独で、学校では友達もいなくていじめられます。科学に興味を持ち始め、やっと話が合う1年先輩の友人クリストファー・モーコムと知り合い、二人でケンブリッジ入学を目指します。しかし、モーコムは大学に合格するものの、18歳の若さで結核で亡くなってしまうのです。
ケンブリッジ大学に入学したアラン・チューリングは、数学を専攻し、ニューマン教授から「人間が行う計算は機械が行うことになる」という教えに刺激を受けて、1936年に「機械でプログラムを動かす」という今では当たり前になったソフトウエアの概念を展開する論文を世界で初めて発表して注目されます。まだ、コンピューターができる前の時代で、アランは、当時は誰にも理解されなかった「人間の脳に匹敵する機械をつくりたい」という研究をするつもりでしたが、ちょうど、第2次世界大戦が勃発し、政府暗号学校にスカウトされて暗号解読に時間を取られてしまうのです。
ようやく戦後の1947年、アランは数学学界で「経験から学習する機械」という人工知能の概念を発表しますが、ほとんど相手にされません。エニグマを解読した天才科学者だったことは、秘匿されたため、奇人変人扱いされました。その後、1952年、アランは、当時違法だった同性愛行為で逮捕されて有罪判決を受け、12カ月の保護観察処分を受け、失意のうちに2年後の54年に亡くなります。
人工知能(AI)という言葉が世界で初めて公になったのは、アランが亡くなった2年後の1956年、米ダートマス大学での学会ででした。
1974年、英情報部の元大佐が出版した「ウルトラ・シークレット」で初めて、アラン・チューリングがエニグマを解読した偉大な数学者だったことが公にされ、チューリングはやっと「コンピュータ科学の始祖」と呼ばれるようになったのです。
ここまでが前段です。
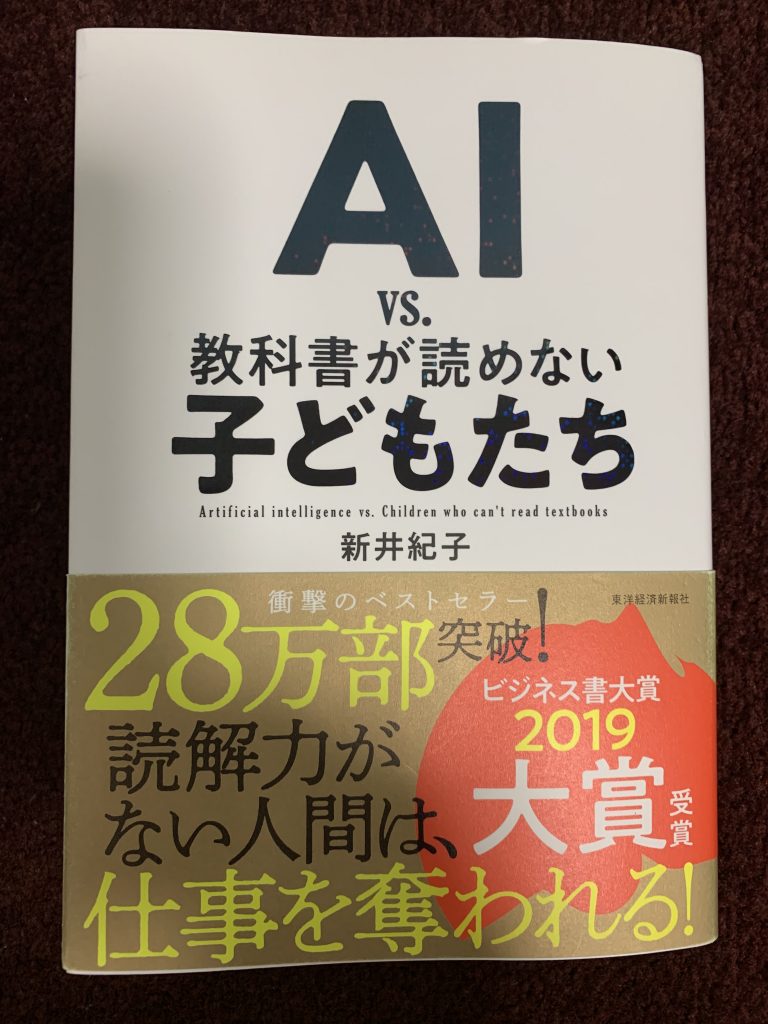
このアラン・チューリングの生涯をテレビで観たおかげで、今話題の新井紀子著「AI vs 教科書が読めない子どもたち」(東洋経済新報社)を読んで、その内容がよく分かりました。この本は、実は読むつもりはなかったのですが、最近、人工知能に凝っている本山君が私に貸してくれたのです。2018年2月15日初版ですが、2019年のビジネス書大賞を受賞し、28万部突破というベストセラーです。
テレビ番組を観ていて、最初、何で数学者のアラン・チューリングが人工知能の概念を考え出したのかよく分かりませんでした。この本の著者で、2011年に「ロボットは東大に入れるか」と名付けた人工知能プロジェクトを始めた新井紀子氏も数学者です。
この本を読んで初めて分かりました。今では自明の理ながら、コンピューターというのは計算機なのでした。逆に言うとコンピューターは計算しかできないのです。AIが言葉をしゃべったり、動いたりしているように聞こえたり見えたりしますが、実は、機械の中で複雑な計算をしているというのです。
新井氏は、この本で、もう少し細かく説明します。4000年以上の長い歴史を通して、数学は、人間の認識や、人間が認識している事象を説明する手段として、「論理」と「確率」と「統計」という言葉を獲得してきた、あるいは、獲得できたのはその三つだけだった、いうのです。長くなってしまうので、この「論理」「確率」「統計」とは何かについては茲では詳しく触れず、同書に譲ります。
人工知能(AI)の話に集約します。新井氏はこう書きます。
「真の意味でのAI」とは、人間と同じような知能を持ったAIのことでした。ただし、AIは計算機ですから、数式、つまり、数学の言葉に置き換えることのできないことは計算できません。では、私たちの知能の営みは、すべて論理と確率、統計に置き換えることができるでしょうか。残念ですが、そうならないでしょう。
ということなどから、新井氏は、ロボットが人間の知能を追い越す「シンギュラリティ」は到来しない、と断定するのです。将棋や囲碁などでコンピューターが人間に勝ってもです。
つまり、この本には書いてませんが、単なる私見によると、人間の持つ非論理的な曖昧さとか、矛盾、優柔不断さ、義理人情で忠誠心がありながら、裏切りや背信する行為、利己的である一方、利他的であったりするつかみどころのない不可解さは、AIではとてもできないということなのでしょう。何故なら、AIは論理的な計算機だからです。スーパーコンピューターがいくら過去の膨大なビッグデータを蓄積しても、人間は過去の歴史に学ばず、痛い目に遭わなければ忘れますから(笑)、人間は、天下のスパコンが思いもつかない挙動不審な行動を取るということなんでしょう。
ただし、シンギュラリティが来ないとはいっても、著者の新井氏は楽観してません。ホワイトカラーの50%の仕事は、今から20年後以内でAIに取って代わる、つまり、半分の仕事が奪われるというか、なくなってしまうと予想しているのです。なくなる職業として、電話販売員、不動産登記の審査・調査のほか、スポーツの審判員や銀行の窓口などがあります。新聞記事も既にAIが書いていますからね。
うーん、これからの現役世代は大変だなあ。。。でも、確かにこの本は面白い。ベストセラーになるはずです。

