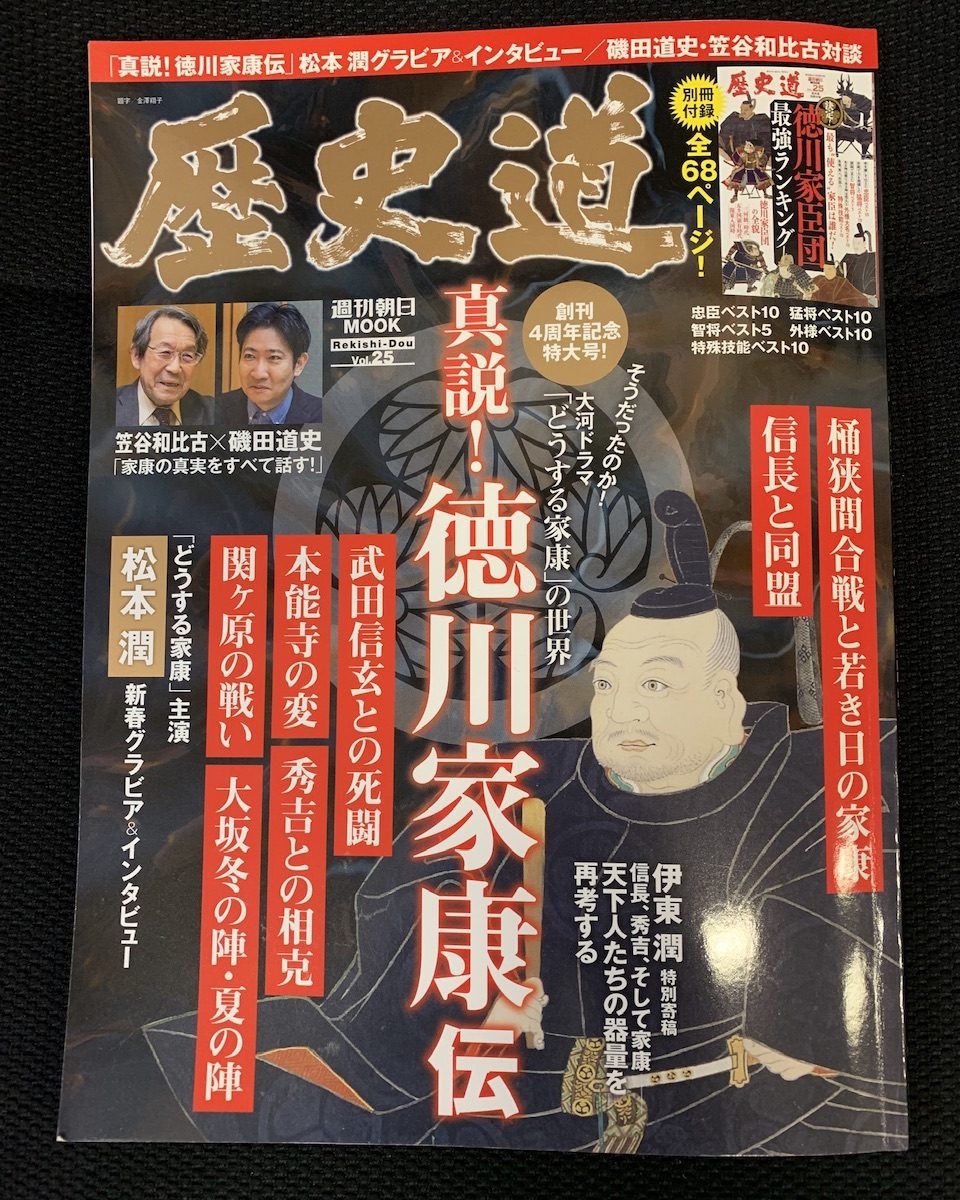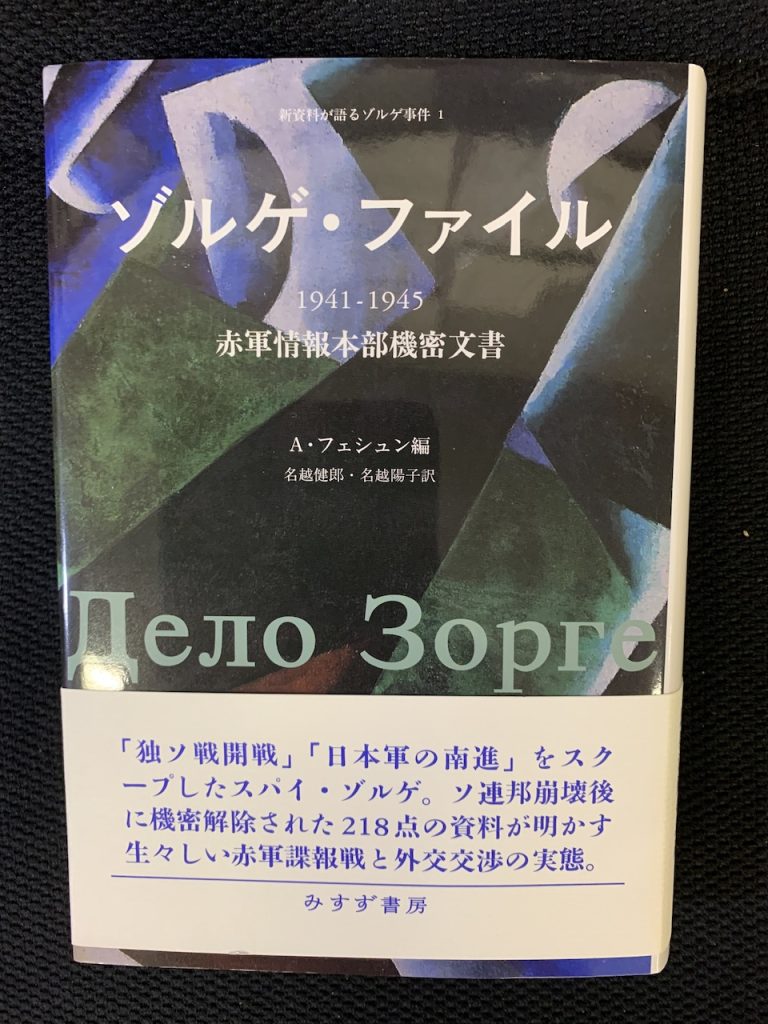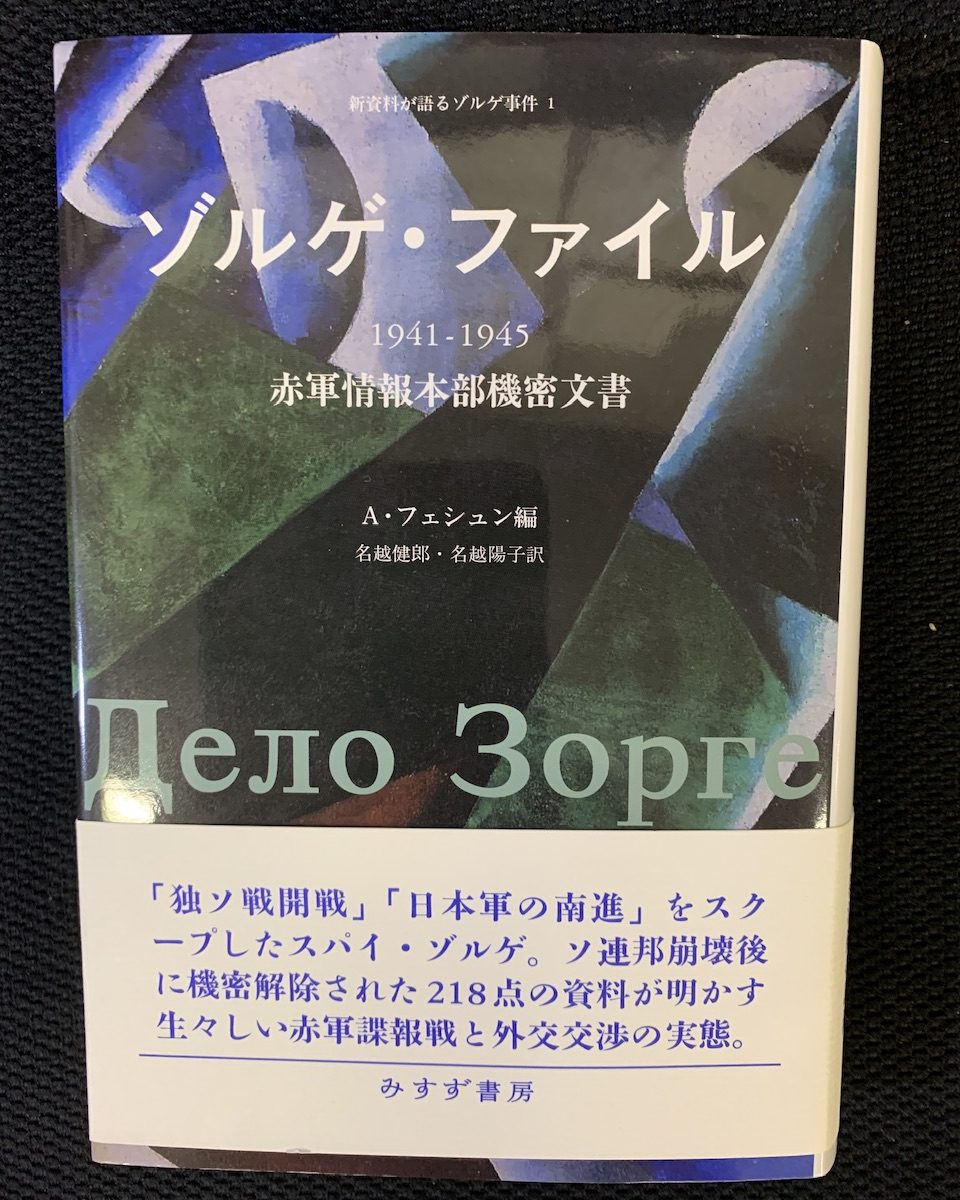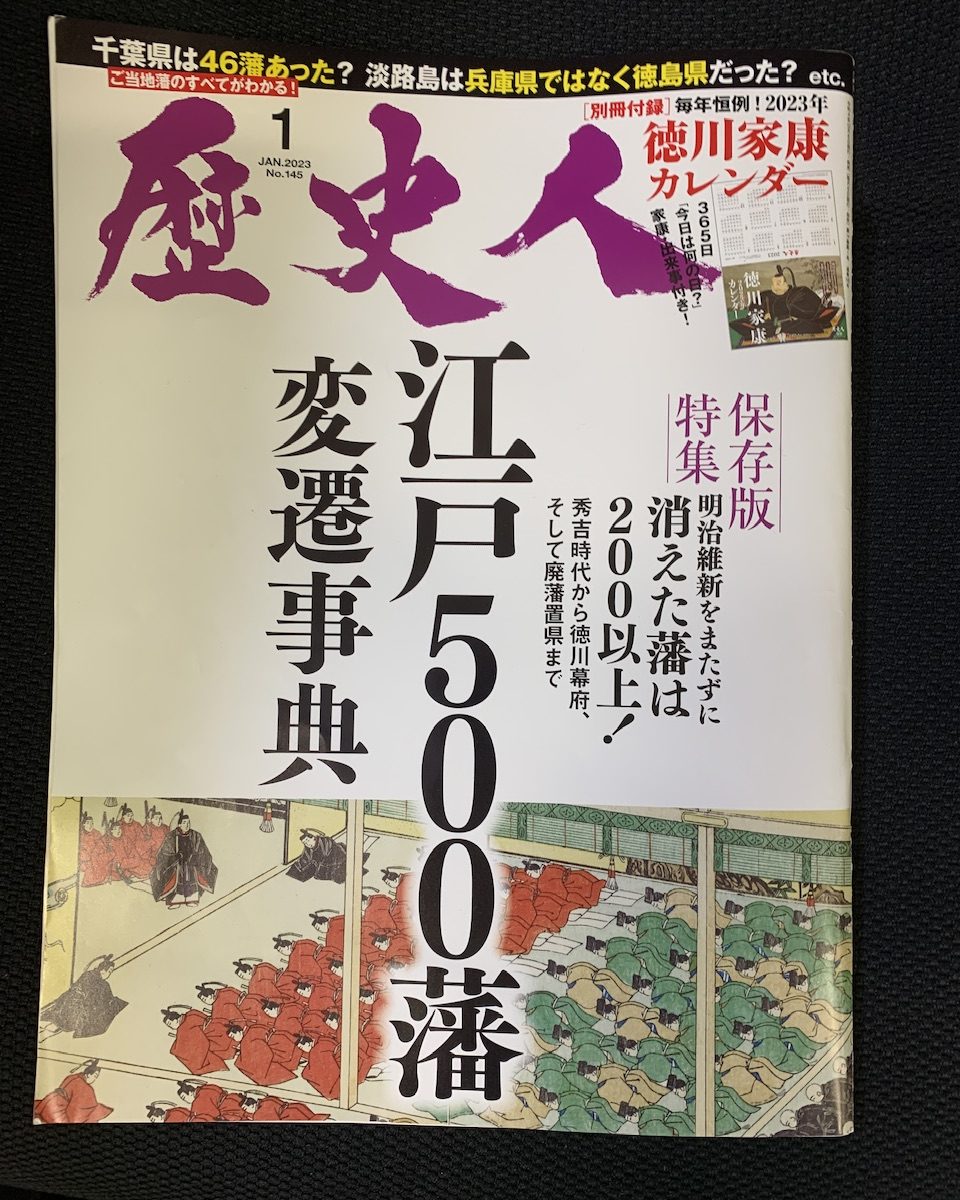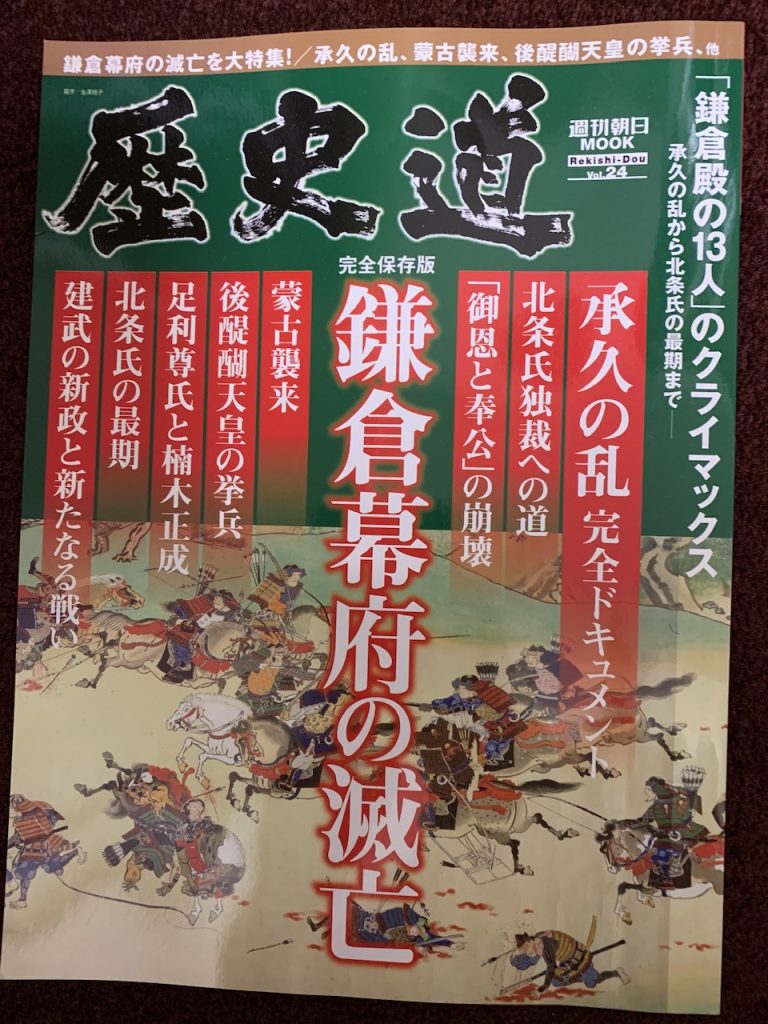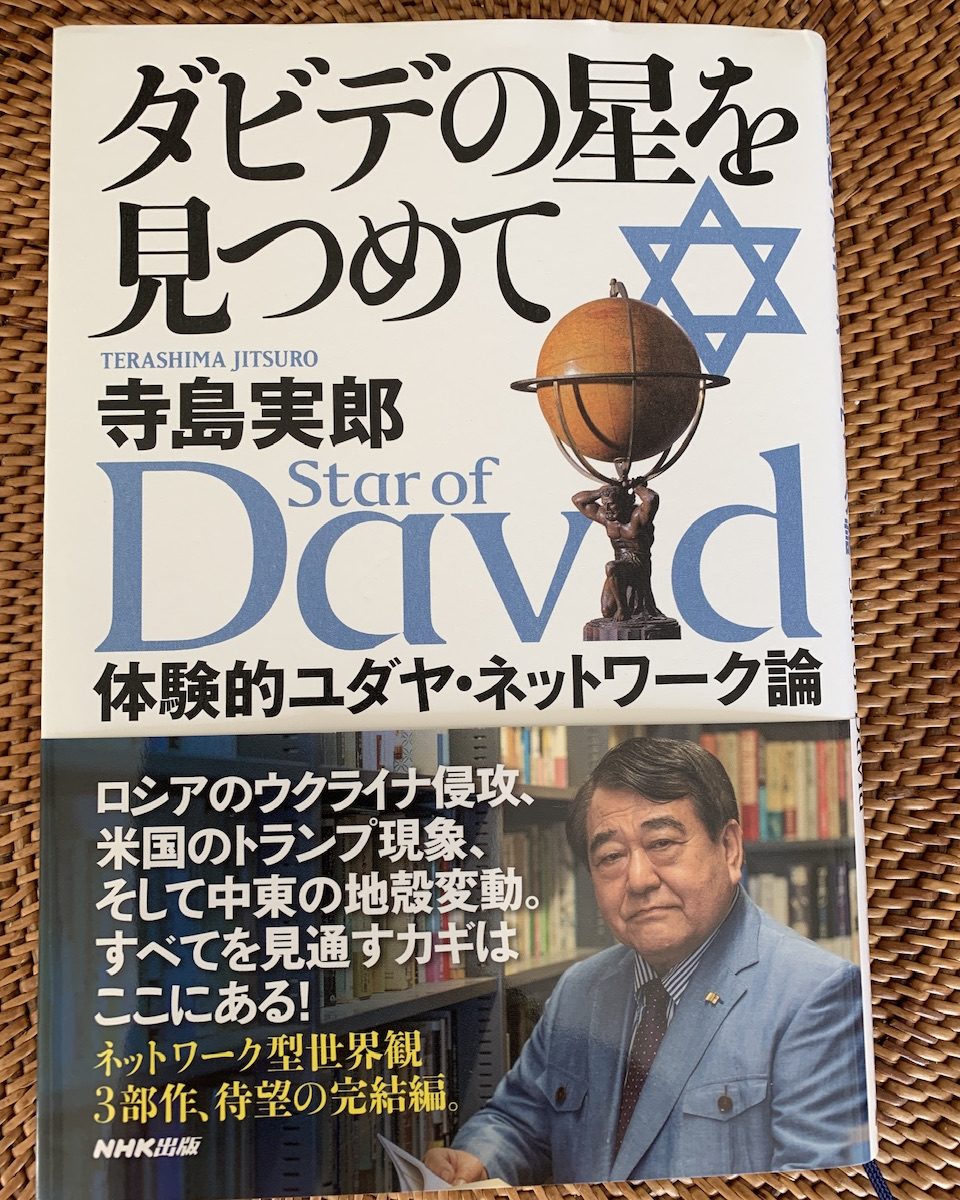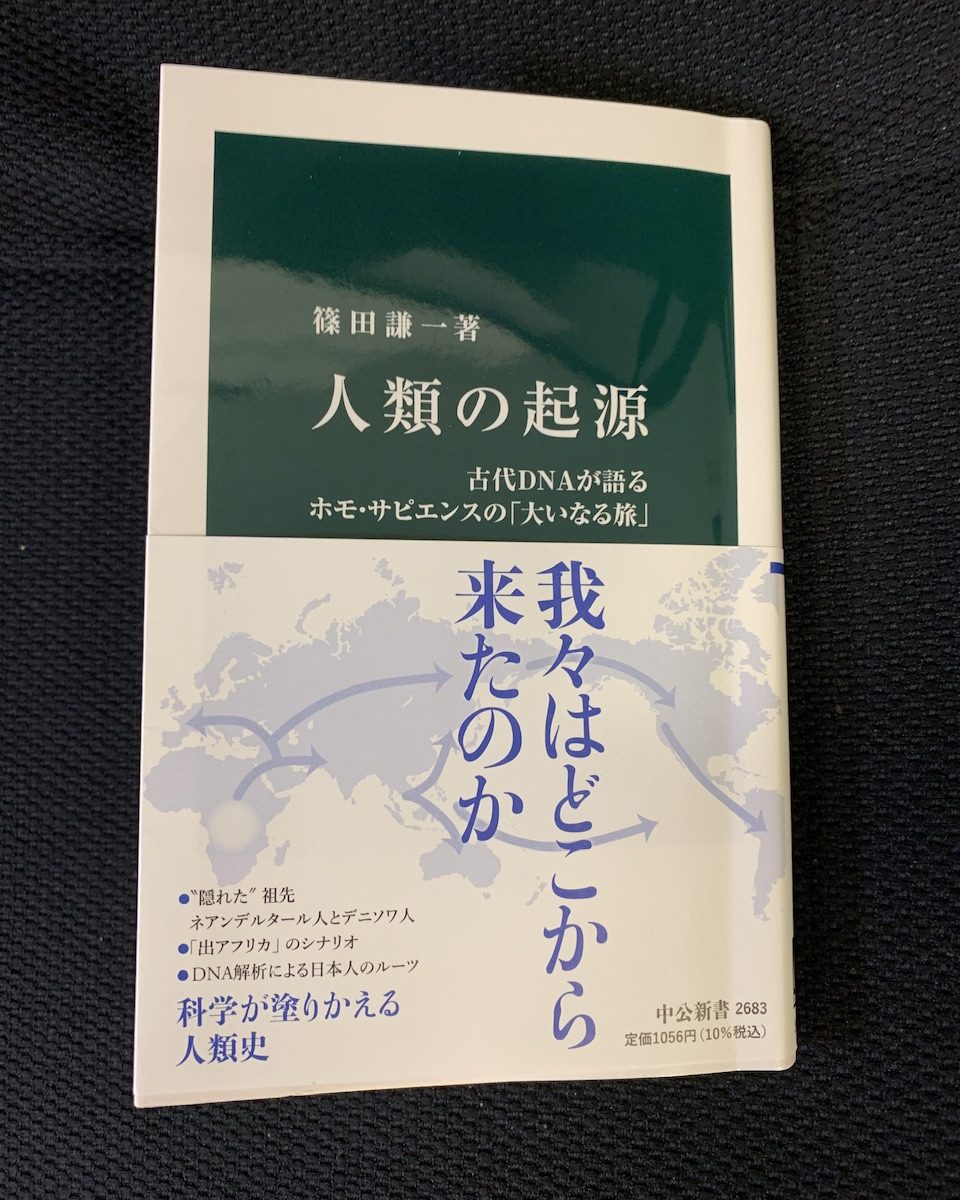1922年創刊と日本で一番古い週刊誌で、101年の歴史を持つ「週刊朝日」(朝日新聞出版)が今年5月末で休刊になる、という超メガトン級のニュースが飛び込んで来ました。時代の趨勢を感じます。100年以上も歴史あるメディアが事実上廃刊になるのです。ピーク時は、150万部に達していたそうですが、昨年12月の平均は7万4千部程度。将来の部数と広告収入の減少を見込んだことが休刊の表向きの理由ですが、同社は週刊誌は他に「AERA」も発売しており、2誌同時発刊は経営的に厳しいと判断したようです。まあ、一番の理由は若い人が紙媒体を読まなくなり、ネット情報に依存するようになったからなのでしょう。
私は古い世代なので、やはり紙媒体が一番です。残念としか言いようがありませんが、何を言っても始まらないでしょう。

でも、その週刊朝日ムックとして隔月刊で発行されている「歴史道」は続けてほしいなあ、と思っております。1月発売の第25号は「真説! 徳川家康伝」特集で、あからさまなNHK大河ドラマ「どうする家康」とのタイアップ記事もありましたが、雑誌存続のためには仕方がないということで御同情申し上げます。
ムックなので、写真や図解が豊富というのが特徴ですが、テレビに出たがりの、特に見たくもない、勝ち誇ったような学者様のアップした顔写真を何枚も掲載するのはそれほど必要なものか、と苦言だけは呈しておきます。その学者様の洞察力と業績は尊敬しますけど、まさかアイドル雑誌?これも売るために仕方ないのかなあ?
先日、やっと読了しましたが、徳川家康というまさに日本史上燦然と輝く「日本一の英傑」の生涯がこの本で分かります。人には功罪がありますが、戦国時代の最終勝者で、その後、260年間もの太平の世を築き挙げた家康の手腕は、やはり、罪より功の方が遥かに上回っていると認めざるを得ません。3歳での実母との別離、幼少時代の人質生活、そして16歳(1558年の鱸氏攻め)から合戦に次ぐ合戦で、最晩年の大坂の陣(死の1年前)を入れれば、戦争に明け暮れた波乱万丈の一生と言えるでしょう。
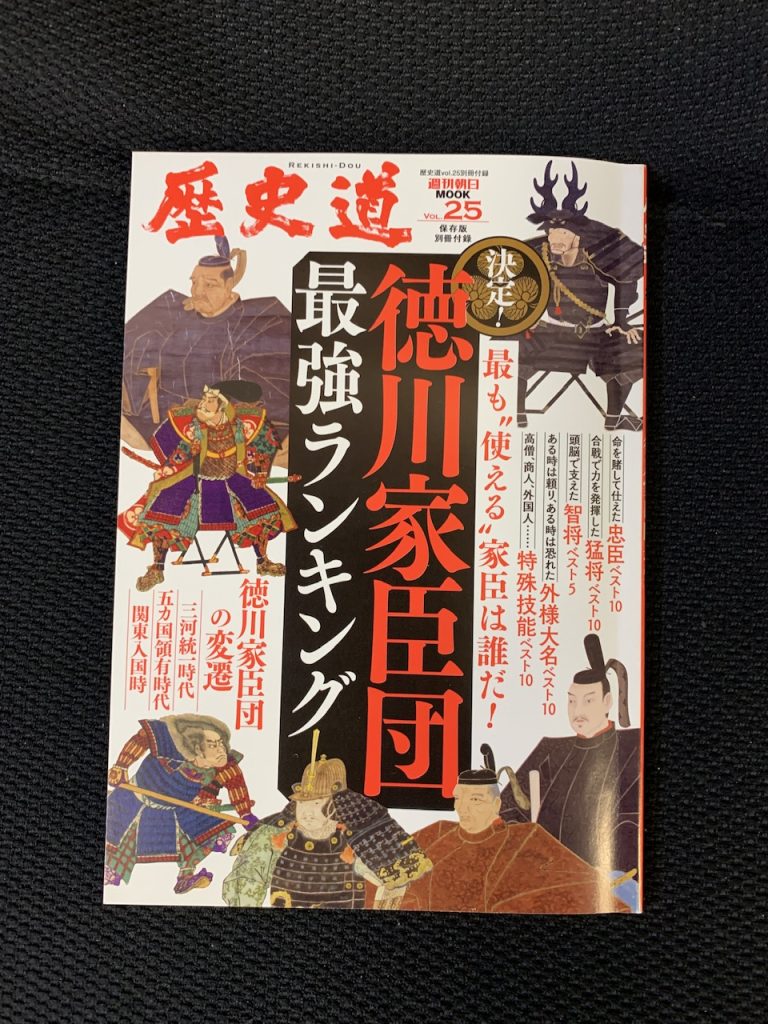
渓流斎ブログ2023年1月11日付「水野家と久松家が松平氏の縁戚になったのは?=NHK大河ドラマ『どうする家康』で江戸時代ブームか」でも書きましたが、この本を買ったのは、付録として「徳川家臣団 最強ランキング」が付いていたからでした。つまり、私には徳川家臣団の知識が不足しておりました。260年続く幕藩体制を築いた家康ですが、家康一人の力で天下を獲ったわけではありません。優秀で有力な家臣団がいたからこそ成就できたのです。その家臣団のほとんどが、幕末まで続く藩主(大名)になっているので、そのルーツを知りたかったこともあります。1月11日付のブログでも書きましたが、上総鶴巻藩主などの水野家は家康の実母於大の方の実家であり、下総関宿藩主などになった久松家は、その於大の方が離縁後に嫁いだ先でしたね。
家臣団の中で、徳川四天王が一番、人口に膾炙しておりますが、それ以外に、この本では詳述されていませんでしたが、「徳川十六神将」とか「徳川二十四将」「徳川二十八神将」とかあるようです。特に二十八神将となると、後世になってつくられたものなので、人物名の誤記などもあるというので、よほどの通の人でなければ覚える必要はないかもしれませんが、この本の付録「徳川家臣団 最強ランキング」では「三河統一時代」と「五カ国領有時代」「関東入国時」と時代別に家臣団の変遷が詳述されています。例えば、三河統一時代の「三奉行」が高力清長、本多重次、天野康景だったことが分かります。私も含めて、知る人ぞ知る武将なので、彼らがその後、どうなったのか、子孫が幕末まで生き残って何処かの藩主になっていたのか調べたりすると本当にキリがありません。

そこで、有名どころとして、徳川四天王の筆頭、酒井忠次を今回取り上げますが、この人は、家康より15歳年長で家康の義理の叔父に当たる人でした。(酒井忠次の正妻碓井姫は家康の父広忠の妹。酒井氏は、鎌倉幕府の公文所初代別当大江広元の末裔とも言われている。また、酒井氏は松平氏と同族の兄弟(同祖)で、三河の国衆の中で酒井氏の方が有力だった時もあった。家康時代の酒井氏は、忠尚家、忠次家、正親家の3家から成る)。左衛門尉(さえもんのじょう)酒井忠次は、特に天正3年(1575年)の長篠の戦では、武田軍の背後に回る奇策を演じて、織田・徳川連合軍の勝利に導きました。いくら信長、家康といった目上の人に対してでも物怖じせず、率直に物を申す人柄で、酒井家の代々の藩主の家風として伝えられています。酒井忠次の孫に当たる忠勝から庄内藩主として幕末まで十二代続きます。あくまでも徳川家の臣下として誠意を尽くした庄内藩は、幕末の戊辰戦争でも最後まで善戦したため、過酷な処分が予想されましたが、比較的軽い処分で済みました。それは西郷隆盛の配慮だったことを後で知った旧庄内藩士によって明治初期に「西郷南洲翁遺訓」がまとめられた、という話につながります。
歴史とは、現代との「つながり」ですから、そのルーツを知れば知るほど興味が増していきますね。