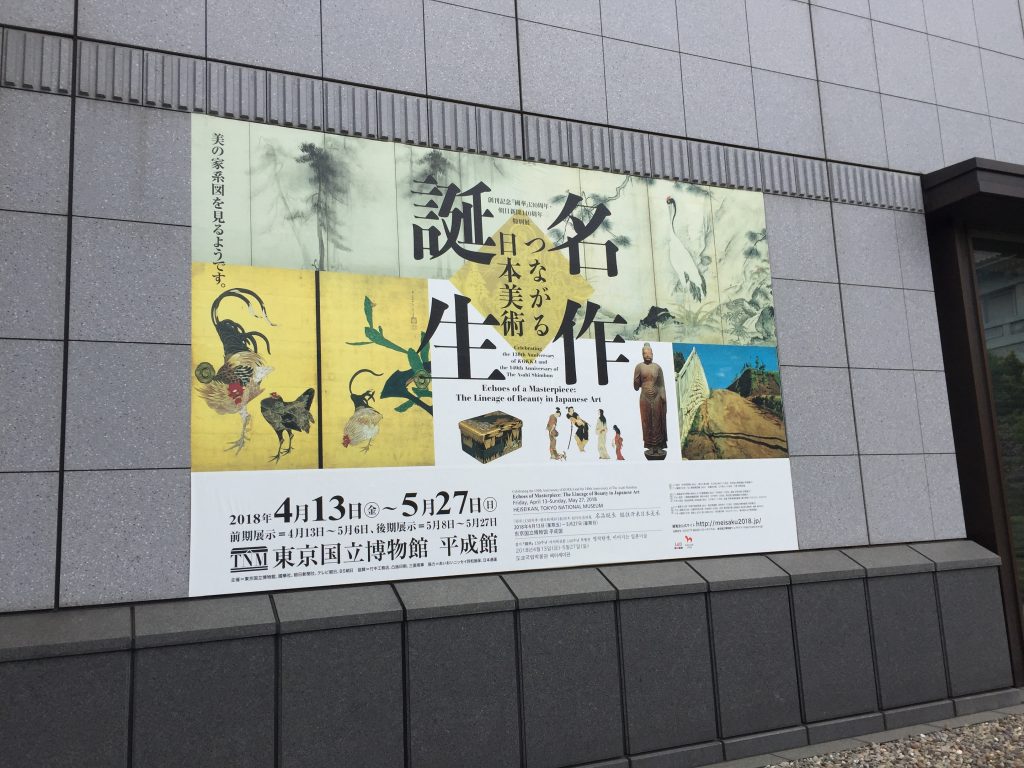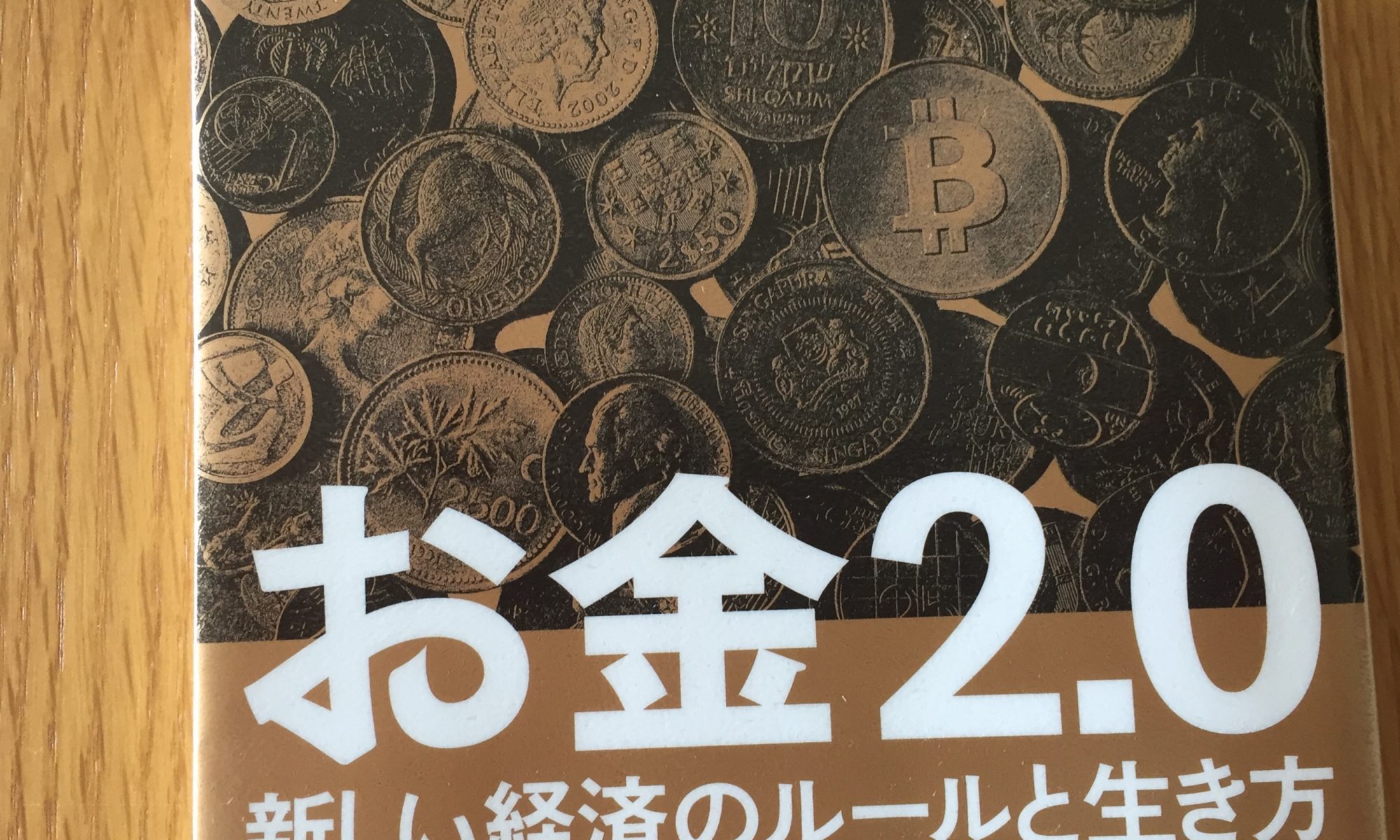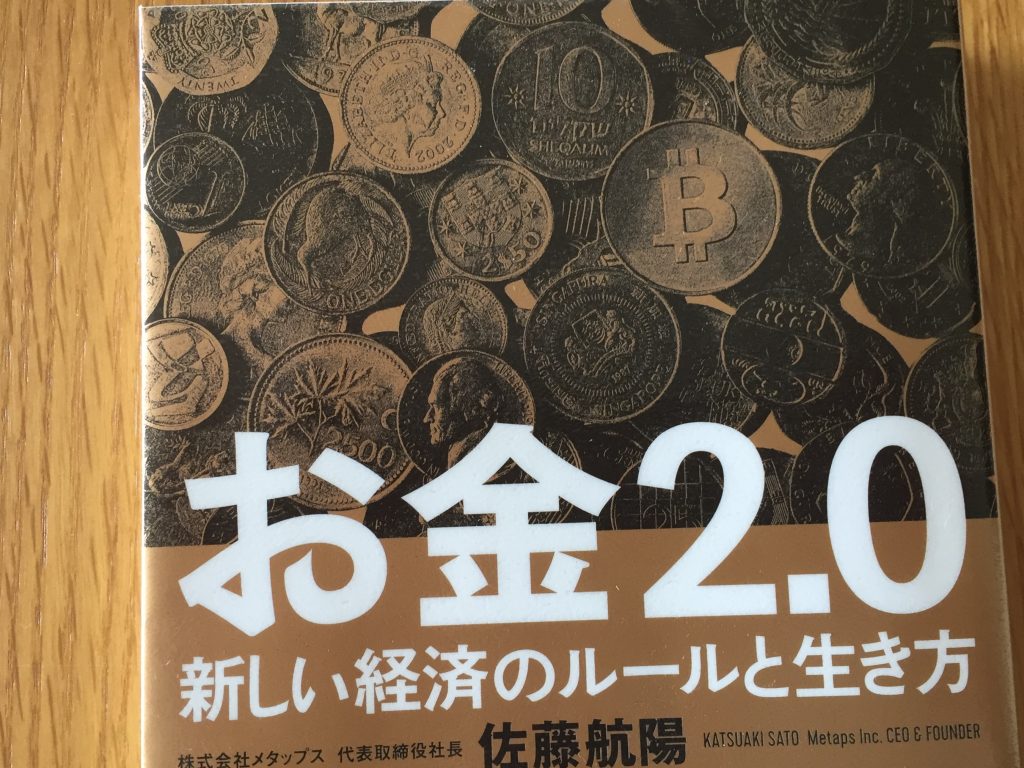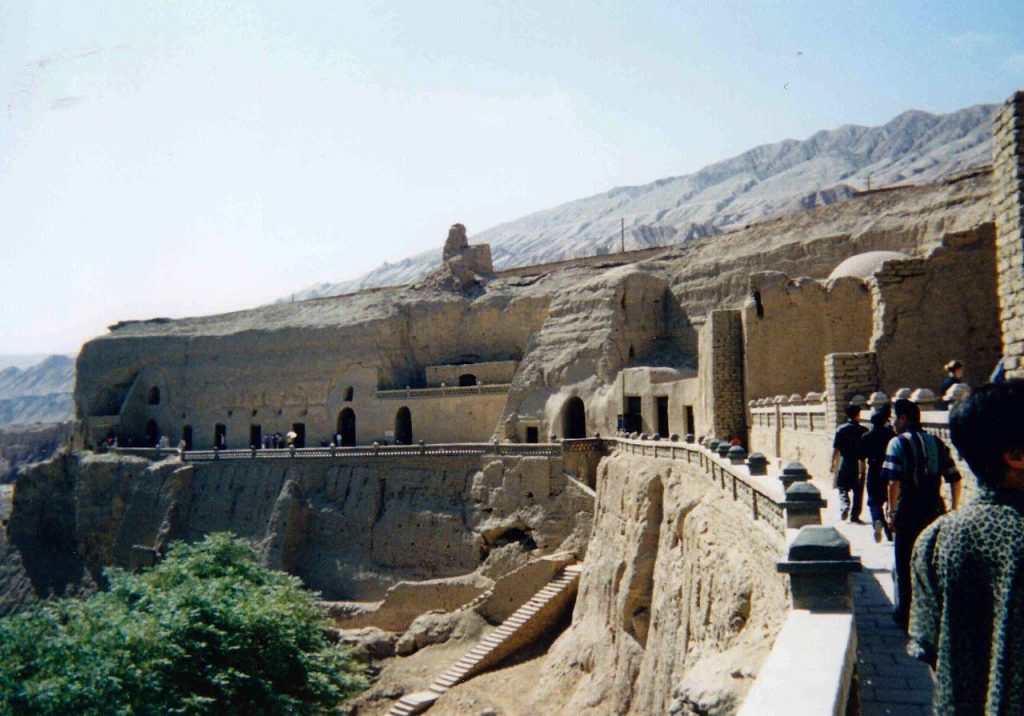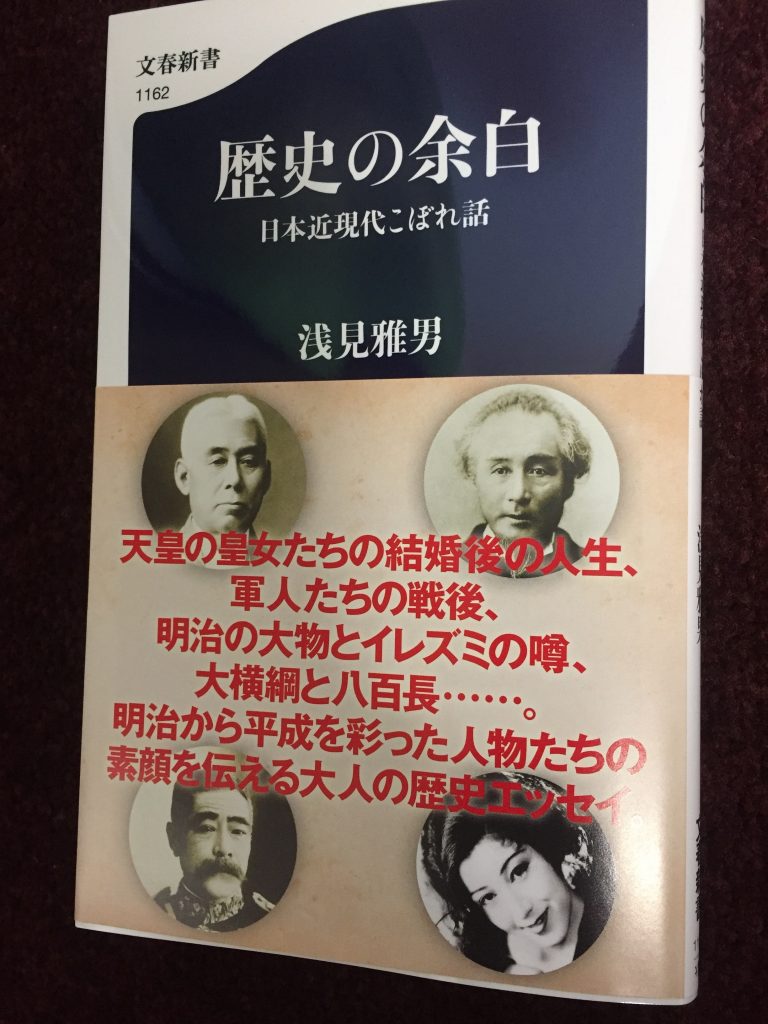残念なことに、歴史小説家の加藤廣さんが4月7日に都内の病院でお亡くなりになっていたことが分かりました。今朝(16日)早く、京都にお住まいの京洛先生がメールで知らせてくれました。
享年87ですが、加藤さんが、デビューしたのは2005年の75歳の時。「本能寺の変」を独自の解釈で描いた「信長の棺」(日経出版)が、時の小泉純一郎首相の「愛読書」として注目され、瞬く間に大ベストセラーに。その後、松本幸四郎(現白鸚)主演でテレビドラマ化されました。
このあと、「秀吉の枷」「明智左馬助の恋」を完成させ、「本能寺三部作」と呼ばれました。この他、代表作に、週刊新潮に連載されて単行本化された「謎手本忠臣蔵」などがありますが、厚労省が言うところの、後期高齢者になってからこれだけの量と質を伴った作品を書き続けた作家は、日本文学史上、初めてではないでしょうか。
加藤さんは、少年の頃からの作家志望でしたが、大学卒業後、銀行員(中小企業金融公庫)になります。しかし、「作家になる夢」を諦めきれず、経済関係の本を現役時代から出版しておりました。
その才能に目を付けたのが、新聞社に勤務していた頃の京洛先生でした。エッセイやインタビューや連載企画物の執筆をお願いし、彼が主宰する勉強会「おつな寿司セミナー」にもゲスト講師として参加してもらったりしました。
小生渓流斎も加藤さんと謦咳を接したのも、この渋谷のおつな寿司の席でした。もう四半世紀以上昔のことで、当時はまだ加藤さんは無名で、エリートではありましたが、幼少の時から大変苦労されてきたようで、筋の通った古武士の雰囲気を醸し出してました。
加藤さんとしても、おつな寿司セミナーは、自分のメジャー・デビュー作を発表することになる日経文藝記者の浦田さんと知り合う場でもあったし、京洛先生には作品のテレビドラマ化に当たってコーディネーターになってもらったりしたので、相当思い入れがあった会合だったようで、ほとんど毎回出席されてました。
そういう小生も、加藤さんにはインタビューなどで大変お世話になりました。特に、銀座の超高級おでん屋さん「やす幸」のご主人が加藤さんの御学友とかで、すっかりご馳走になったりしました。
「やす幸」のおでんを食してしまうと、もう他のおでんは絶対口にできないほどの絶品で、今まで食べてきたおでんは一体何だったのか、と思うほどかけ離れた美味しさでした。
もう消滅してしまった《渓流斎日乗》には、かなり加藤さんが登場していたと思います。
加藤さんが中小企業金融公庫の京都支店長時代、当時、ベンチャー企業で、海のものとも山のものともつかぬ変な会社がありました。他の銀行は相手にしなかった変わったその経営者の素質を加藤さんは見抜いて、積極的に融資し、今や誰もが知る世界的な企業に成長した会社があります。
それは、今では飛ぶ鳥を落とす勢いの日本電産です。一風変わった経営者とは、お正月の午前中以外、1年365日働きまくる、あの永守重信氏です。
【追記】
どういうわけか、加藤さんの訃報記事は16日付日経、毎日、産経、東京の朝刊に載ってますが、朝日と読売は、朝夕刊ともに載らないのです。不思議です。