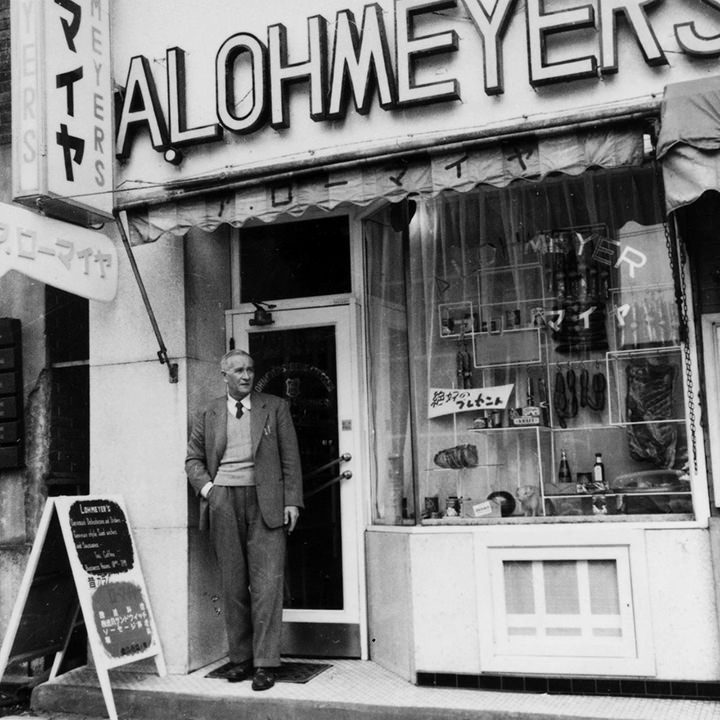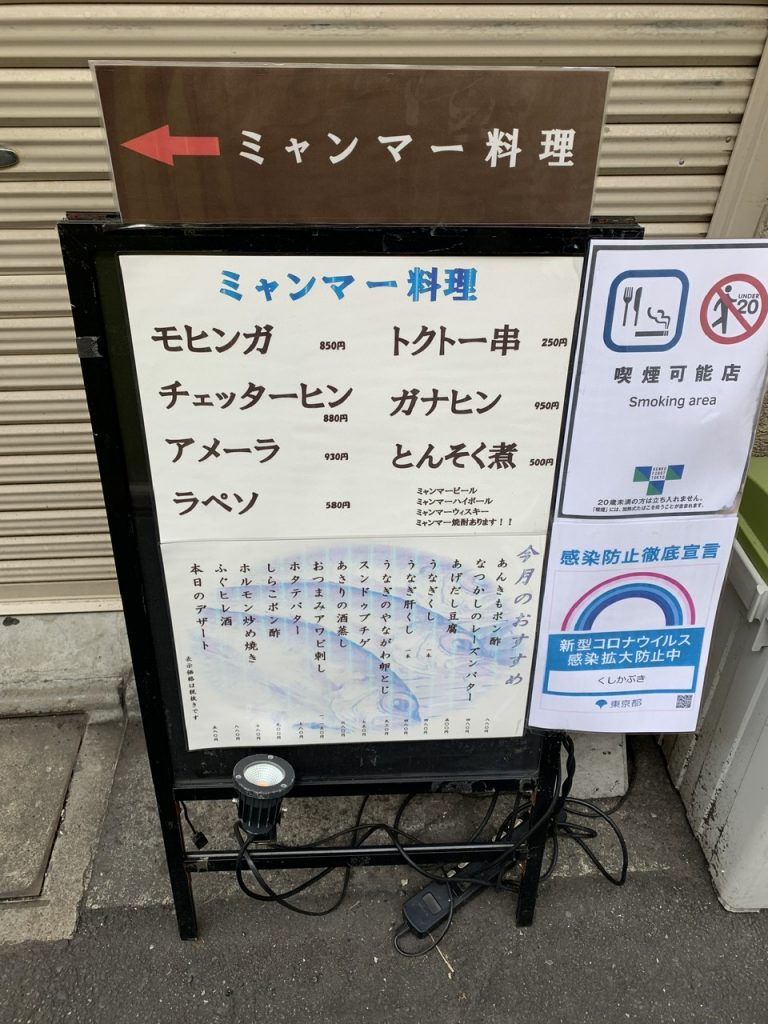Jardin de Karatsu Copyright par Y Tamano
戦国時代の大名蒲生氏郷(がもう・うじさと、1556~95年)は、その知名度といい、人気度といい、残念ながらトップ10には入らない知る人ぞ知る武将なのですが、これがとんでもなく凄い戦国武将だったことを最近知りました。
渋沢栄一が「日本近代資本主義の父」なら、蒲生氏郷は「日本の商業の父」と言えるかもしれません。
私は会津贔屓ですから、蒲生氏郷といえば、織田信長、豊臣秀吉に仕え、会津若松城(福島県)を築城したキリシタン大名だという認識が大きかったのですが、もともとは、近江蒲生郡(滋賀県)の日野城主だったんですね。
近江日野といえば、近江日野商人の所縁の地として有名です。

滋賀県日野町のHPによると、「近江商人」の中でも日野地方出身の商人は特に「日野商人」と呼ばれ、日野で造られた漢方医薬や上方の産物を天秤棒一本で地方へ行商して財をなしたといいます。他の近江商人と比べ出店数においては群を抜き、この形態は今の総合商社の始まりだとも言われています。近江商人の心得である「三方よし」(「売り手良し」「買い手良し」「世間良し」の三つの「良し」)は有名ですね。
近江商人の流れを汲むと言われる現代の企業に、武田薬品工業や東レや伊藤忠商事、双日、西武グループ、高島屋などがあることは皆様ご案内の通りです。蒲生氏郷が移封された後、近江日野は衰退してしまい、新しく日野商人が独自で切り開いたという説もありますが、蒲生氏郷が近江日野に商業の種を蒔いたことは間違いないことでしょう。

信長の死後、羽柴秀吉の家臣となった蒲生氏郷は、小牧・長久手の戦いや九州征伐などで戦功をたて、天正16年(1588年)に伊勢・松ヶ島12万石に移封され松坂城を築城します。松ヶ島の「松」と秀吉の大坂の「坂」から字を取って「松坂」(後に松阪)と命名したのは蒲生氏郷です。この時、城下町に移住してきたのが、蒲生氏郷の地元の日野商人で、これが名高い「松阪商人」になったというのです。半ば強制的に移住させられた商人もいましたが、大半は、商業の発展に力を注いだ武将の蒲生氏郷を慕って移住してきたと言われています。
松阪商人で最も有名な人物は三井グループの祖である三井高利です。高利の祖父である三井高安は、もともと近江の守護大名六角氏に仕える武士でしたが、織田信長との戦いに敗れて伊勢の地に逃れてきたといいます。蒲生氏郷が松阪に移封される20年も前のことですが、三井高安は越後守を名乗っていたため、「三井越後屋」(今の三越)の屋号が生まれたと言います。
松坂城主蒲生氏郷は、楽市楽座を進め、街道を整備して商業発展に力を入れたといいます。伊勢商人の流れを汲む現代の企業には、イオンや伊藤ハムや岡三証券などがあります。

蒲生氏郷は、天正18年(1590年)の小田原征伐の後、陸奥会津42万石(後の検地加増で91万石)に移封されます。黒川城(城主伊達政宗は、小田原遅参などを理由に会津を没収され、米沢72万石に減封)を蒲生家の舞鶴の家紋ににちなんで「鶴ヶ城」と改名し、黒川の地名も出身地の近江日野の「若松の森」から会津「若松」と変更します。
勿論、城下町には日野商人や松坂商人も移住させて商業発展に力を入れますが、どういうわけか、あまり「会津商人」は全国的に有名ではありませんね? でも、近江日野の漆器を、「会津塗」として名産にしたのが蒲生氏郷だと言われています。
蒲生氏郷は1592年、秀吉の朝鮮出兵(文禄の役)の際、前線部隊が集結した肥前名護屋城(佐賀県唐津市)にまで参陣しますが、ここで病を得たのが遠因で、この3年後に伏見で39歳の若さで亡くなります。

蒲生氏郷が会津に移封されたのは、表向きは伊達政宗ら東北の有力大名を抑えるためという理由ですが、秀吉が氏郷の武勇と領地経営の才覚を恐れたためだとも言われ、毒殺されたのではないかという噂さえあります(病死説が有力)。
現代の最優良企業である伊藤忠や武田薬品や三井財閥やイオンなどの祖が、蒲生氏郷が種を蒔いて発展させた近江商人や伊勢商人だったと思うと、改めて蒲生氏郷の偉大さを感じませんか?