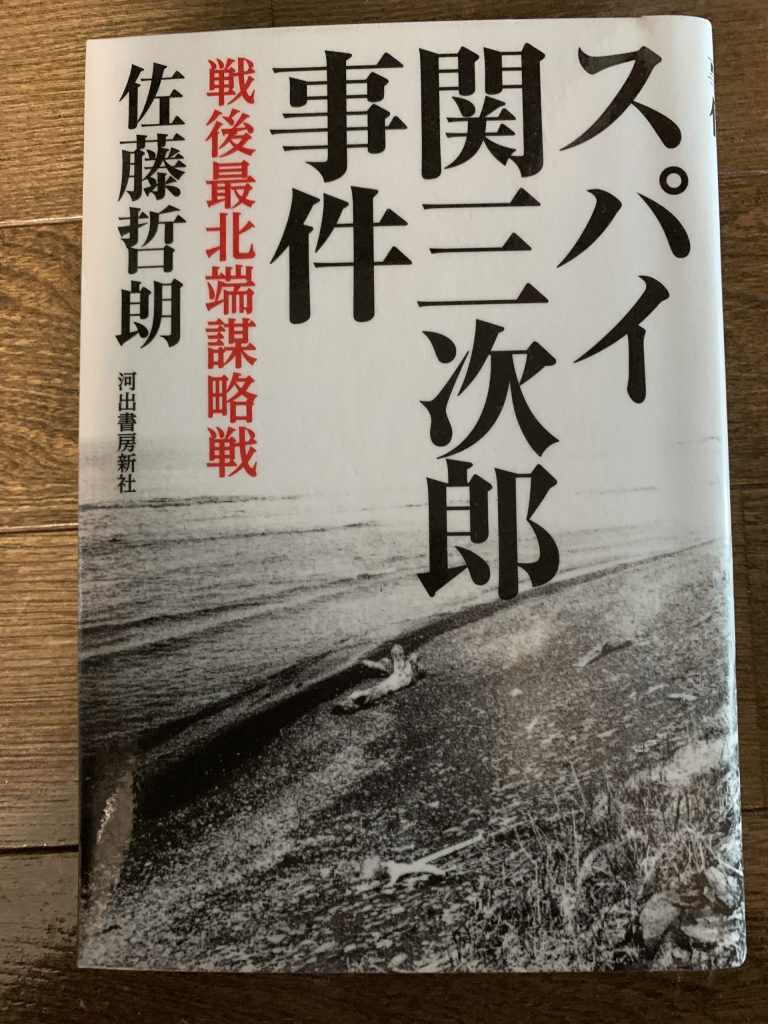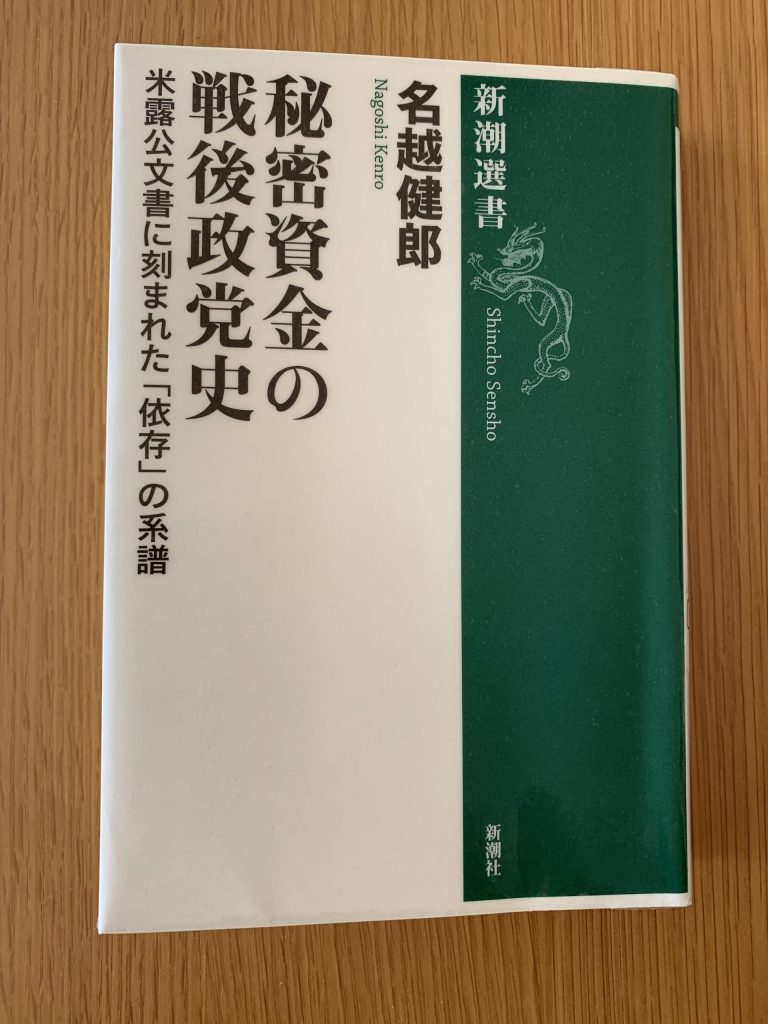2月24日に始まったウクライナ戦争は「長期戦」となるというのが目下、世界の専門家の一致した見解のようです。フランスの歴史学者エマニュエル・トッド氏のように、「第3次世界大戦」と呼ぶ人も現れました。
ロシアとウクライナの二国間の戦争ではなく、武器を貸与している欧米諸国と、ロシアを支援する中国も含まれているからだといいます。
何と言っても、侵略戦争を起こしたロシアのプーチン大統領による民間人殺戮などの戦争責任が問われることが先決ではありますが、米国際政治学者ジョン・ミアシャイマー氏のように「ウクライナ戦争を起こした責任はアメリカにある!」と主張する人もいます。同氏は、ウクライナ戦争をロシアと米国の代理戦争とみなし、米国はウクライナの被害をそれほど重視しておらず、むしろ、ロシアの大義の方が米国より上回るので、この戦争はロシアの勝利で終わると予測しています。
ミアシャイマー氏(74)は、米空軍元将校で、現在、シカゴ大学教授ですが、敵国の肩を持つ発言と捉えられかねないのに、敢えて冷静に、現代史と国際情勢から分析した勇気のある発言だと言えるでしょう。米国も、湾岸戦争では、ロシアがウクライナでしているのと同じように、イラクの都市を徹底的に破壊し、太平洋戦争では、日本の都市を爆撃して、無辜の民間人を虐殺したというのです。(米国の元軍人が、日本への無差別爆撃のことを触れるとは驚きです。そんな人がいるとは!)
そう言えば、ドローンによる撮影で、ウクライナの都市で破壊された建造物が毎日のように、テレビで映し出されますが、湾岸戦争では、ドローンもなく、イラクも国力がないので破壊された戦地はそれほど国際社会に公開されませんでした。

ウクライナ戦争が始まって、アフリカ諸国からそれほどロシアに対する非難や批判が巻き起こらないのは不思議でした。よく考えてみれば、アフリカ諸国は18世紀から20世紀にかけて、特に英国、フランス、イタリア、ドイツ、オランダ、ベルギー、スペイン、ポルトガルなどの植民地となり、徹底的に搾取され、奴隷のように抑圧された歴史があったわけです。それなのに、ロシアは「大国」だったはずなのに、英仏等と比べるほどの植民地はありません。そのせいで、ロシアに対するアレルギーが少ないのかもしれません。
アフリカ諸国としては、欧州列強に対して、「お前たちが過去にやったことを思い出してみろ。ロシアを非難する資格があるのか?」とでも言いたいのでしょうか。

私は、国際法を無視して戦争犯罪をし続けるロシアを非難する側に立ちます。それでも、原因をプーチン大統領の狂気とだけ決めつけて思考停止するつもりはありません。ロシアの大義を知ったとしても、非難の度合いは変わりませんが、知ることは需要だと思っています。
ロシア史研究の第一人者塩川伸明東大名誉教授によると、スラブ系でウクライナ正教徒の多いウクライナは一時期、カトリック教徒が多いポーランドに支配され、単一の行政区域が存在しなかったといいます。それなのに、ソ連時代に「ウクライナ共和国」が誕生したため、今のロシアの指導部には、ウクライナとはソ連が人為的に作ったという認識があるといいます。(毎日新聞6月3日付夕刊)
つまり、ウクライナが出来たのは、ロシアのお蔭だというわけです。それなのに、NATOの東方拡大か何か知らないが、ウクライナは、西側にすり寄って、親分のロシアに歯向かとは何事だというのが、ロシアの大義なのでしょう。
ヨーロッパの歴史は、地続きですから、戦争に明け暮れ、国境も複雑です。「21世紀にもなって、何で戦争?」と私は思いましたが、「欧州の火薬庫」とは、バルカン半島だけでなく、至る所にあるということなのでしょう。