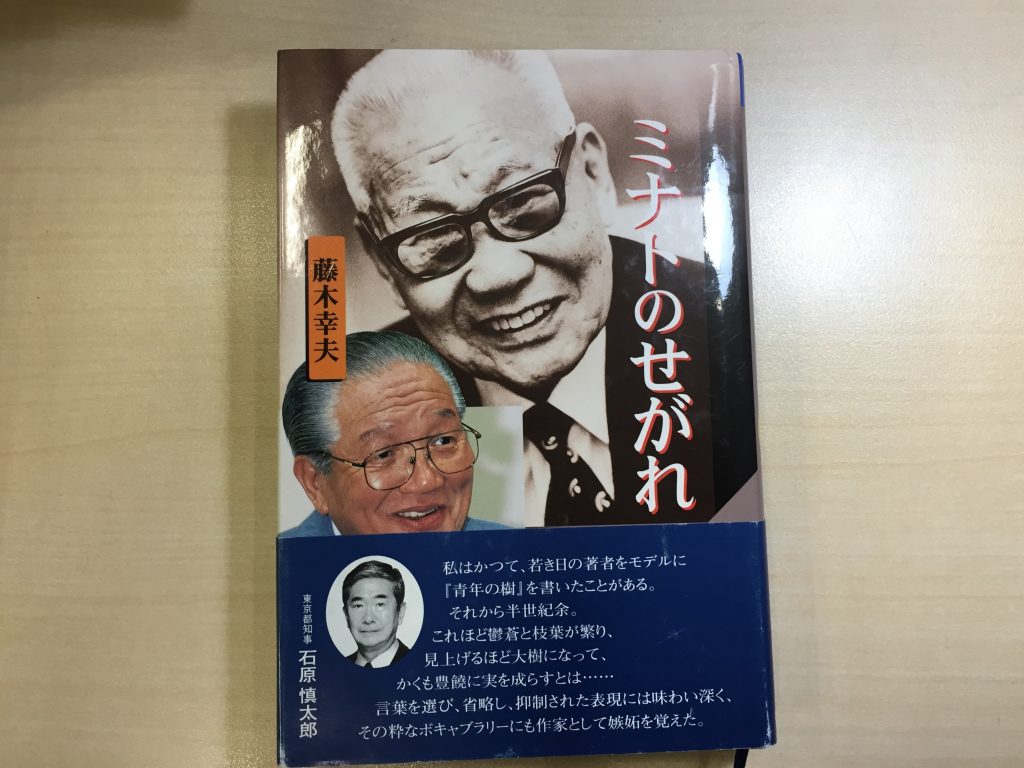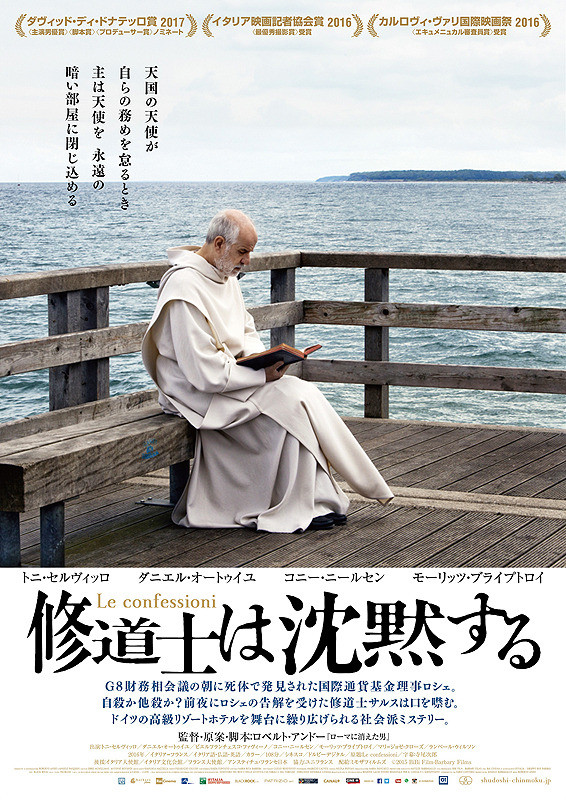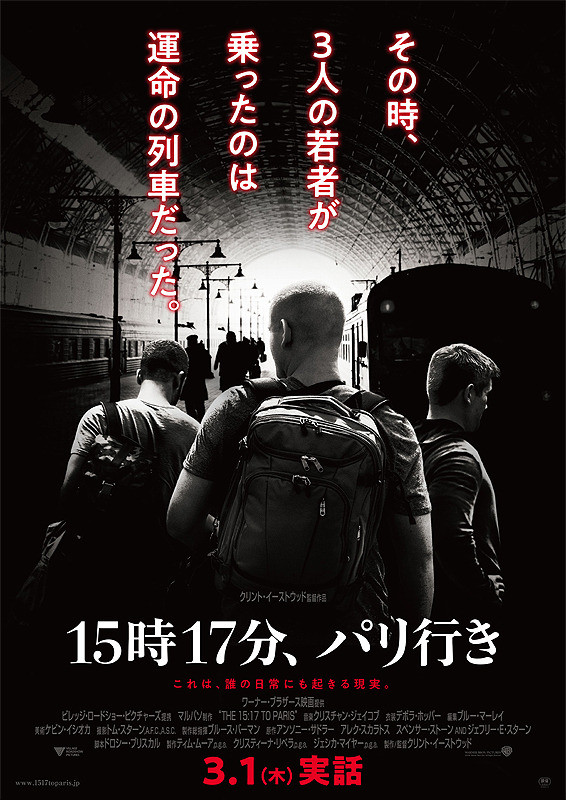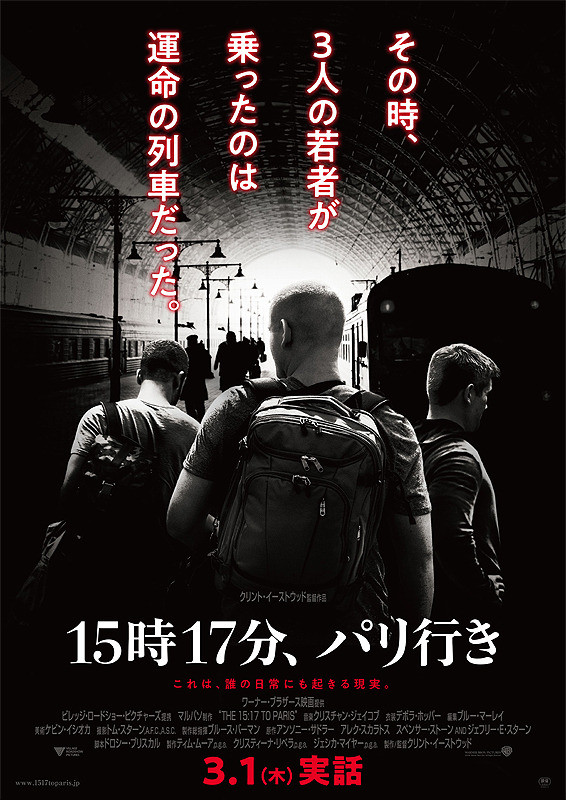久し振りに映画を観てきました。伝説のバンド、クイーンの「ボヘミアン・ラプソディ」(ブライアン・シンガー監督作品)です。
当初は全く観るつもりはなかったのですが、あまりにも話題が先行したため、つい、観ざるを得なくなってしまったのです。それに、やっと昨日、仕事納めで解放され、気晴らしに映画でも観ようかと思ったら、ほとんどお子ちゃま向けで、他に観るのがなかったからでした(苦笑)。
なぜ、クイーンの映画を最初観るつもりはなかったのかと言いますと、その理由の第一が、クイーンは、1970年代、私が学生の頃に全盛期だったため、新譜が出る度にLPレコード(CDさえなかった)を買い集めて熱中したからでした。1974年頃に、ラジオで「キラー・クイーン」を初めて聴いて、「何て、洗練された面白い曲なんだ」と感動してすっかりファンになってしまいました。この曲は、彼らの3枚目のアルバム「シアー・ハート・アタック」に入ってましたから、それ以降の新譜を発売の度に買っていたのですが、その前の彼らの2枚目のアルバム「クイーンⅡ」は、大学の同級生の熱烈なファンの女の子から借りたことを思い出しました。(その後、CDを買い揃えましたが)
さすがに、バンドでコピーするのはとてもレベルが高すぎて、あのフレディ・マーキュリーの美声は誰にも真似できるものではなかったでしたね。

だから、ドキュメンタリーならともかく、どんなそっくりさんが演じようが、作り物の映画は観る気がしなかったのです。フレディがバイセクシュアルで、最期にエイズで45歳の若さで亡くなってしまう「物語」は、同時代人として共有してきましたし、当時の私は、クイーンに関しては音楽誌や評伝なども読んでましたから、自分の知らない物珍しい話などないと思ったからでした。それは、ブライアン・メイのギターは手作りのカスタムメイドだといった類の話ですが、随分傲岸不遜でしたね(苦笑)。

しかし、観た途端、すっかり40数年前の昔の若い頃に戻ってしまい、鳥肌が立って、年甲斐もなく感涙してしまいました。映画では、フレディ・マーキュリーを中心に回ってましたが、フレディ役のエジプト系米国人俳優ラミ・マレックがなかなか健闘し、魂が入ってましたね。もう、そっくりさんとは言わせないとばかりの迫真の演技で、フレディ本人にさえ見えてきてしまいました。

大変失礼致しました。クイーンを全く知らない若い世代が競って観ているというのは、やはり、時代を超えた共通の何かがあり、映画作品としても完成度が高かったということなんでしょうね。
でも、最後まで見てて、辛くなってしまいましたね。フレディは、若い頃から容姿で「パキスタン野郎」と差別され、何と孤独で不幸だったんだ、と単純に思ってしまいました。それが、スーパースターになってしまった代償だとすれば、あまりにも厳しくて切ない話です。
家に帰って、手元にあったクイーンのアルバムを久しぶりに聴きまくりました。最近は、落ち着いたベートーベンの弦楽四重奏曲ばかり聴いていたので、ロックはもう重くて聴けなくなっていたのですが、映画を観たせいで、激しいリズムとビートが心の奥深くに染み渡ってしまいました。