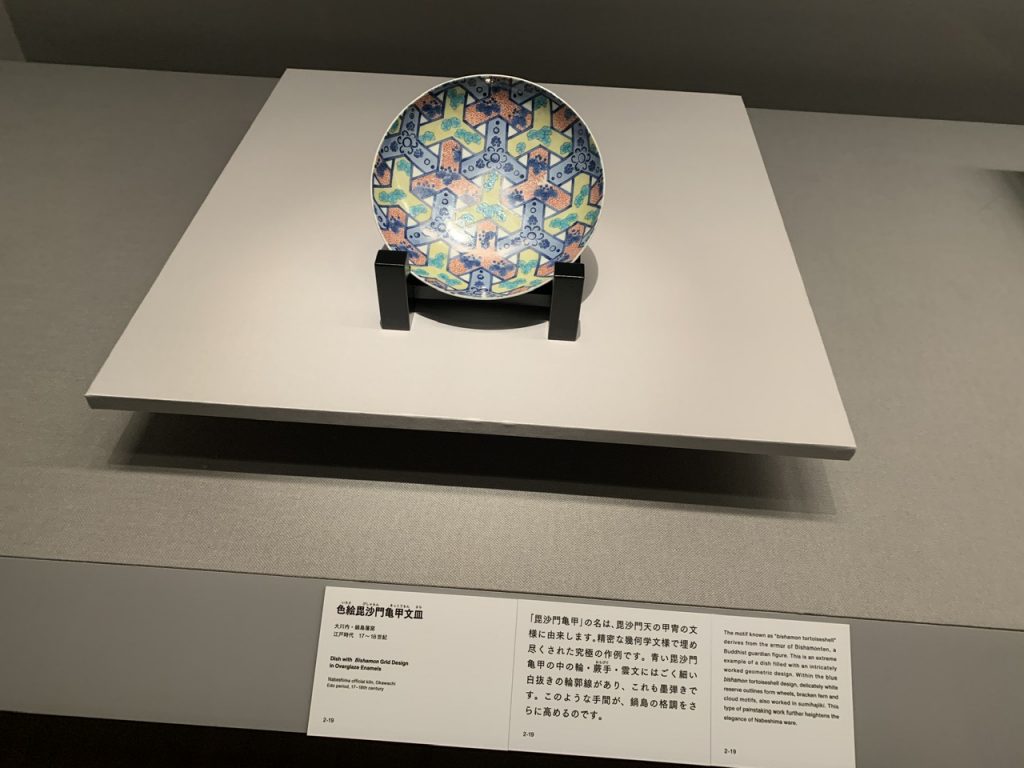富士山 Copyright par Duc de Matsuoqua
昨日のこのブログで「予想が裏切られた時、深い情報処理が起こる=『英語独習法』」のタイトルで、映画の字幕を活用した英語独習を紹介(というか引用)させて頂きました。
自分では易しく、つまり分かりやすく書いたつもりだったのですが、皆さま御存知の釈正道老師から早速反応がありまして、「私には難解です。貴兄の原稿は、素人にはチンプンカンプンでした。」とのコメントを頂きました。
あれえ~?私には大した学も教養もないので、小生のようなレベルの文章は朝飯前のはずです。しかも、釈正道老師は現役時代、誰でも知っている大手マスコミのエリート幹部としてブイブイ言わせた御仁です。難解、なんて言ったら御卒業された福沢先生が泣きますよ。
その一方で、フェイスブックで繋がっているK氏から「我が意を得たり!」と同感して頂きました。私の嫌いなフェイスブックのサイトでこのブログをお読みの方は10人ぐらいでしょうから、敢て「本文」に再録させて頂きます(笑)。ちなみに、K氏は謙遜されておられますが、東京外国語大学英米語学科を卒業された「英語の達人」です。
(すみません、勝手ながら、引用文は少し加筆、改変してます)
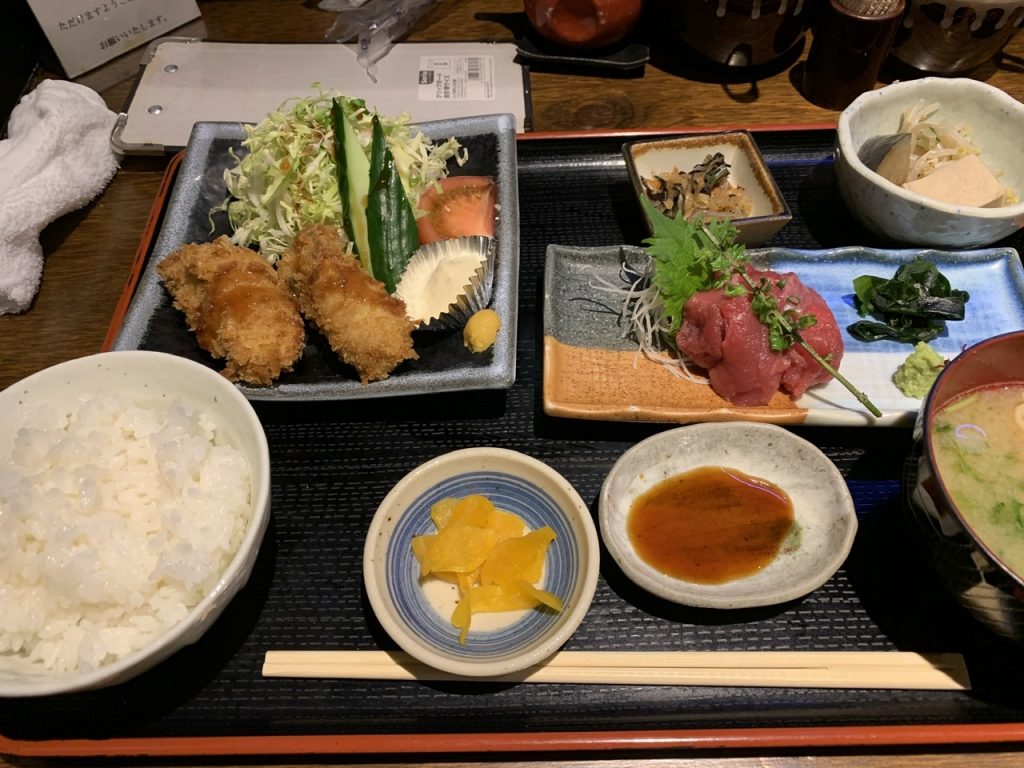
…「英語独習法」の著者今井むつみ氏の提唱される「映画熟見」は、まさに僕が貧弱な英語力を落とさないよう細々と続けているメソッドとよく似ており、一番効果的と感じるものの一つです![]() 何たって、楽しみながら謎解き気分で熱中できるところがいいですね。コロナ禍で、NHK BS や Amazon Prime の名画を楽しむ機会も格段に増えましたが、まさに目からウロコの連続です。
何たって、楽しみながら謎解き気分で熱中できるところがいいですね。コロナ禍で、NHK BS や Amazon Prime の名画を楽しむ機会も格段に増えましたが、まさに目からウロコの連続です。
予期せぬ副産物もあります。例えば、「カサブランカ」のボギーの名セリフとされる「君の瞳に乾杯」Here’s looking at you, kid.は、続けて観た「旅情」では、キャサリン・ヘプバーンが宿屋の女主人、つまり同性から言われており、男女のロマンとは関係ないことが分かりました。(ちなみに、「君に乾杯」は、Here’s to you, とも言うらしい。おお、サイモン&ガーファンクルの「ミセス・ロビンソン」の出だしに出てきますね!=この項、渓流斎)
また、「マイ・フェア・レディ」でオードリー・ヘプバーンが使うコックニー(英労働者階級が使うとされる英語)には、女性が普通使わない表現や、文法上おかしい表現が混じっていることを発見したりして、とてもここには書き切れません。(中略)貴兄のおかげで、英語へのアプローチで同じような楽しみ方をなさっている方がいるのがよく分かりました。…
いやはや、勝手に引用されて、K氏も怒っておられるかもしれません。こうして、私もブログで何人もの大切な友人を失って来ました…。「日乗」と銘打っている関係上、ほぼ毎日更新しているため、どうかお許しを。