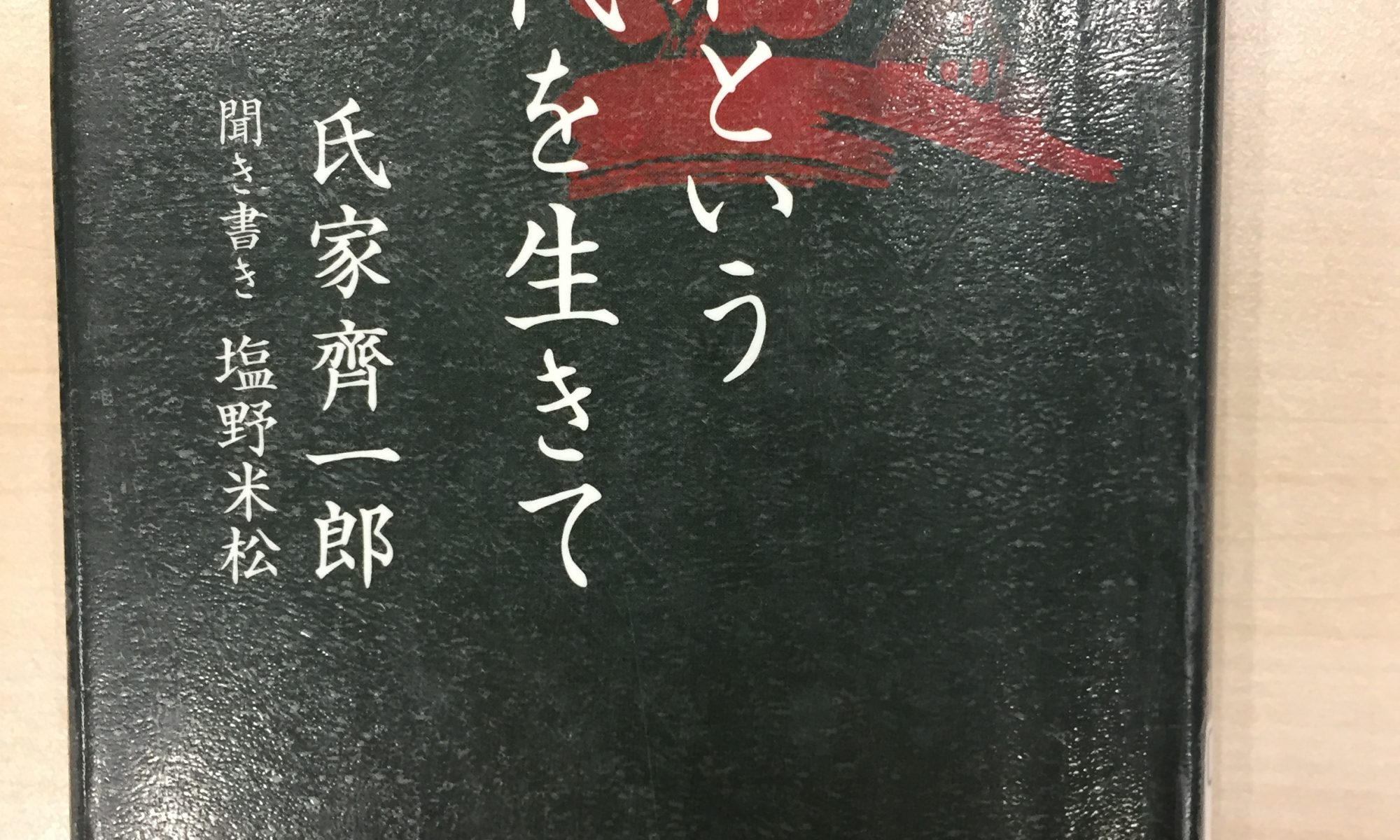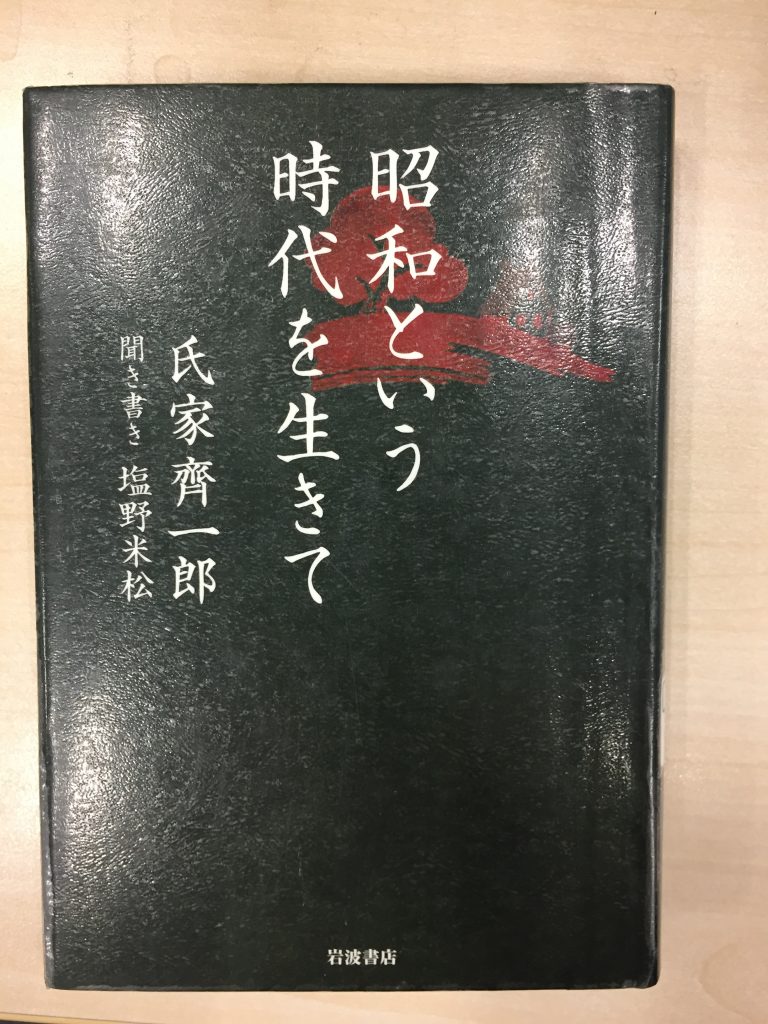敬白
昨日は、チンピラに絡まれた話を書いたところ、多くの方から御心配等のコメントやメール頂きました。誠に忝く存じ候です。
やはり、チンピラ如きを相手にして、こちらが加害者(被害者の可能性の方がもっと高いですが=笑)になってしまってはとんでもない話ですからね。
一昨日は、あんなことが現実にありえるのか、「おい、ジジイ!」なんて、まるで時代劇のドラマを見ている感じでした(笑)。昨晩はよく眠れましたので、少し回復しました。
皆さまにはご心配をお掛けして申し訳御座いませんでした。
◇◇◇
さて、名古屋にお住まいの篠田先生お勧めで、所功、久礼旦雄、吉野健一共著「元号 年号がら読み解く日本史」(文春新書)を昨日から読み始めましたが、面白いですね。来年は平成最後の年で、改元されるわけですから、大変タイムリーな本です。それに、非常にマニアックです(笑)。恐らく、一般向けの元号に関する本で、これ以上詳しいものはないかもしれません。ただし、その前に、古代史関連の本を何冊か読んでおくことをお勧めします。一層面白くなると思います。
とはいえ、まだ読み始めたばかりです。篠田先生がこの本を薦めてくれるに際して、「信じられないでしょうが、天皇は昔、住む所がなくて、京都市内の公家らの家にお世話になって、転々として暮らしていた時代があったんですよ。それは、この本に書かれています」と言うのです。
えっ???本当なんですか?全く信じられませんでした。

篠田先生は、やたらと京の都の歴史に詳しく、今ある京都御所は、平安時代のものではなくて、徳川家康が整備したもので、「平安宮」はもともと、今の千本通り(かつては、朱雀大路と呼ばれ、京の南北のメインストリートだった)の北の一条から二条にかけてありました。西の右京が水はけが悪く、大雨が降ると不衛生で疫病がはやり、大火で大内裏も焼失するなどして廃れてしまい、都の中心は東の左京に移っていたといいます。戦乱などで、江戸時代になるまで、天皇といえども、大内裏を失って、定住先がなかった時期もあったわけです。
少し話が本筋が外れてしまいましたが、元号とは、漢の武帝が最初に制定したと言われ、周囲の「属国」は、中国の元号を使わさせられました。日本の最初の公式の元号は645年の大化ですが、その時代に、よくぞ「独立国」として頑張ったものです。(その前に、中国に隠れて、非公式に元号を使っていた時もあったようです)。
この本には「属国」とは書かれていませんが、「中華思想」には、周辺国の民族は文明のない野蛮な夷狄(いてき)として、朝貢させることが当然だと看做されておりました。勿論、そんな「属国」は中国の元号を使うのが当たり前ですから、個別に元号を称するなどとんでもないということになるのです。
皮肉にも、本家本元の中国では、清の時代で元号を使うのが最後で、今は西暦を使っているというのです。朝鮮半島も、一時的に独自か中国の元号を使っていましたが、今はありません。かつて越南と呼ばれて中国に朝貢させられていたベトナムにも元号があり、何と「大正」もあったそうです。(日本が「大正」を採用した際、森鴎外が友人宛ての手紙「何で、他の外国の例を調べないのだ」と憤慨したそうです)
ということは、日本は、ほとんど唯一、今でも元号を使っている国であり、「優等生」と言えなくもないですね。(台湾は、今も中華民国暦を使っているようです)。何しろ、朝鮮半島もベトナムも、今では漢字まで廃止してしまい、日本は「哲学」や「科学」や「経済」など独自の漢字を造語して、中国に逆輸出してしまうぐらいですからね。
◇◇◇
今回、中華思想の夷狄について調べてみたら、南蛮とは、スペインかポルトガル人のことかと思っていたら、本来はベトナムなど南方に住む夷狄民族を指していたんですね。
つまり、中国の皇帝らは、中華の四方に居住していた周辺民族を蔑称して、
「東夷」(中国東北地方、朝鮮半島、日本)
「北狄」(匈奴、鮮卑、韃靼、契丹、蒙古など)
「西戎」(ウイグルなど)
「南蛮」(ベトナム、カンボジアなど東南アジア、西洋人)
―と呼んでいたというのです。
中華思想とは、自分たちの「華夏」が世界の中心であり、それ以外の夷狄は「化外の民」ということになります。
ところで、昨日は、習近平主席ら指導部は、アフリカ53カ国の代表を呼んで、「中国アフリカ協力フォーラム」を開催して、600億ドル(6兆7000億円)も支援すると約束したようです。以前にこのブログで書いたスリランカの港の租借の例もあるように、背後に、どこか、今でも「中華思想」が健在のような気がします。
あれ?元号の話からずれてしまいましたね(笑)。
いずれにせよ、この本、先を読むのが楽しみです。