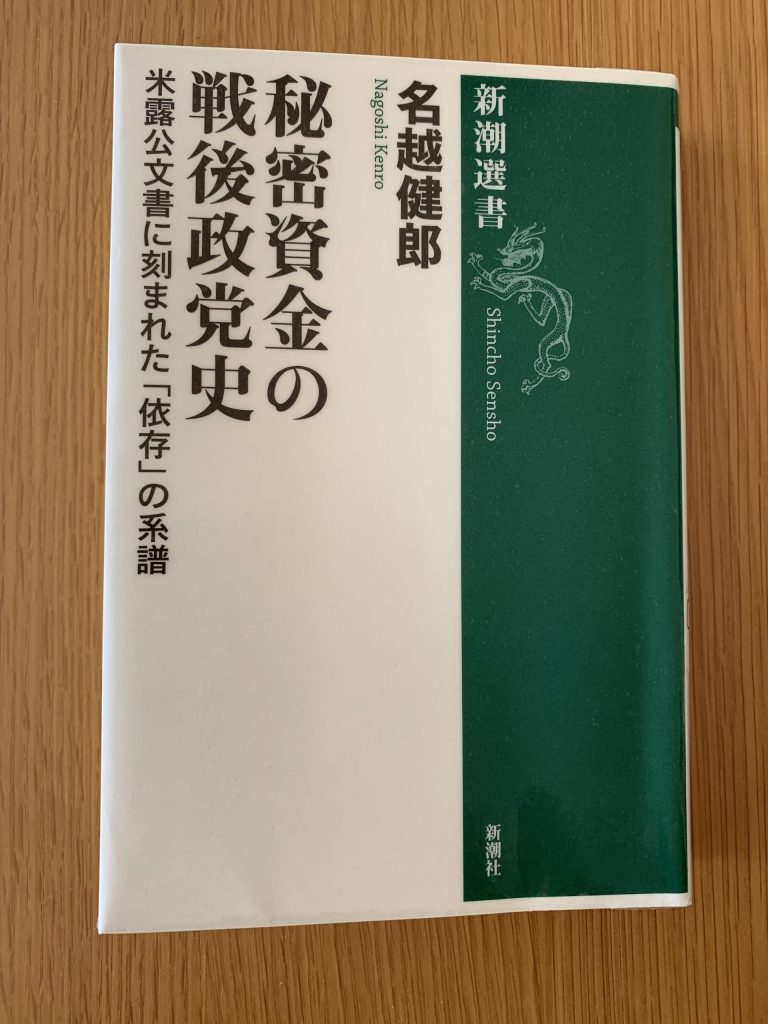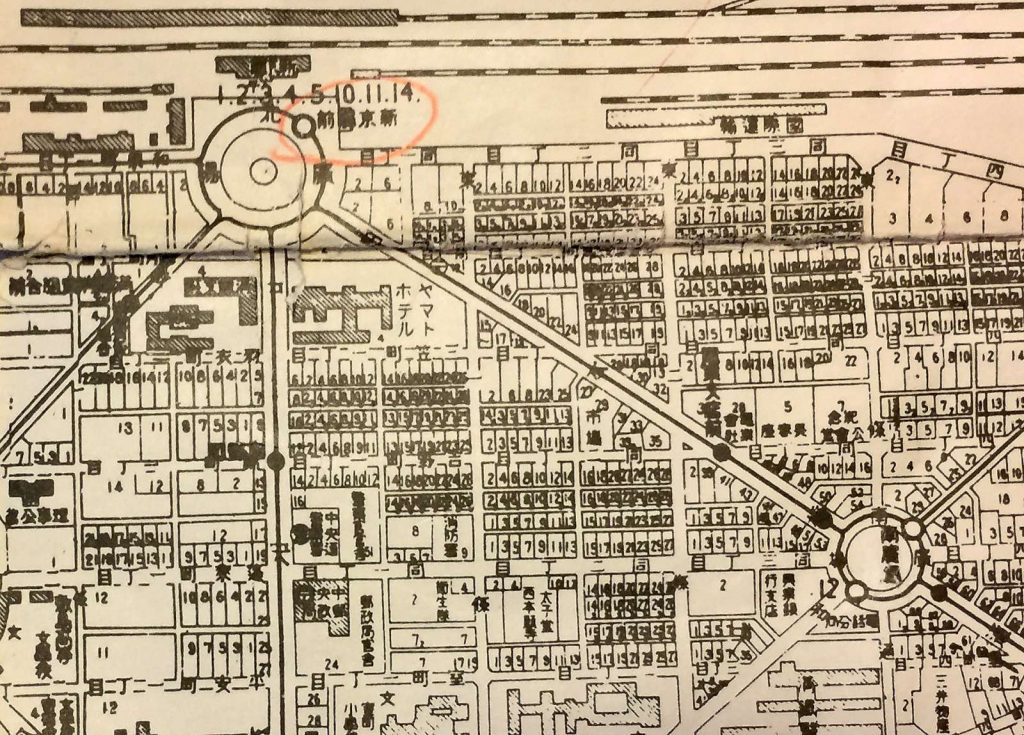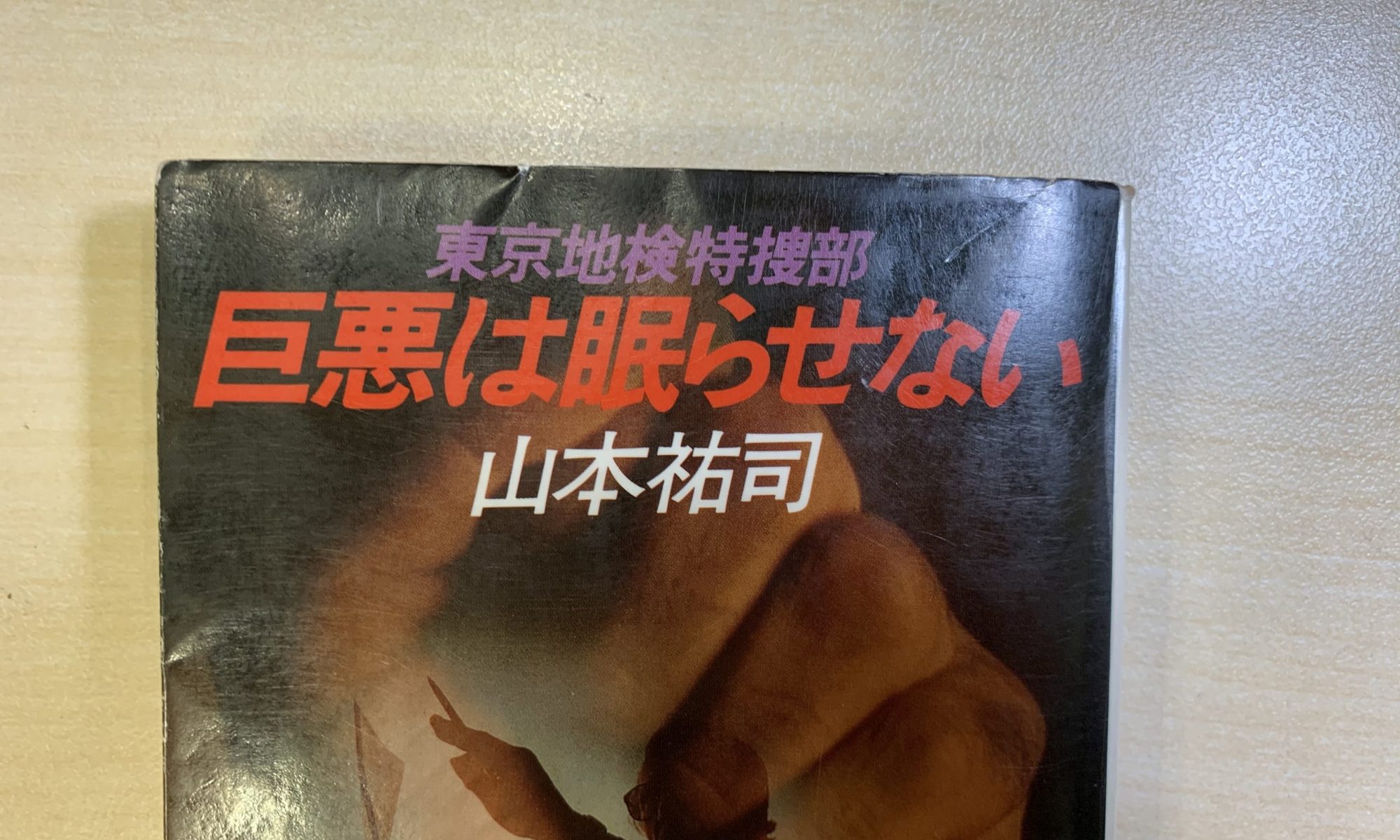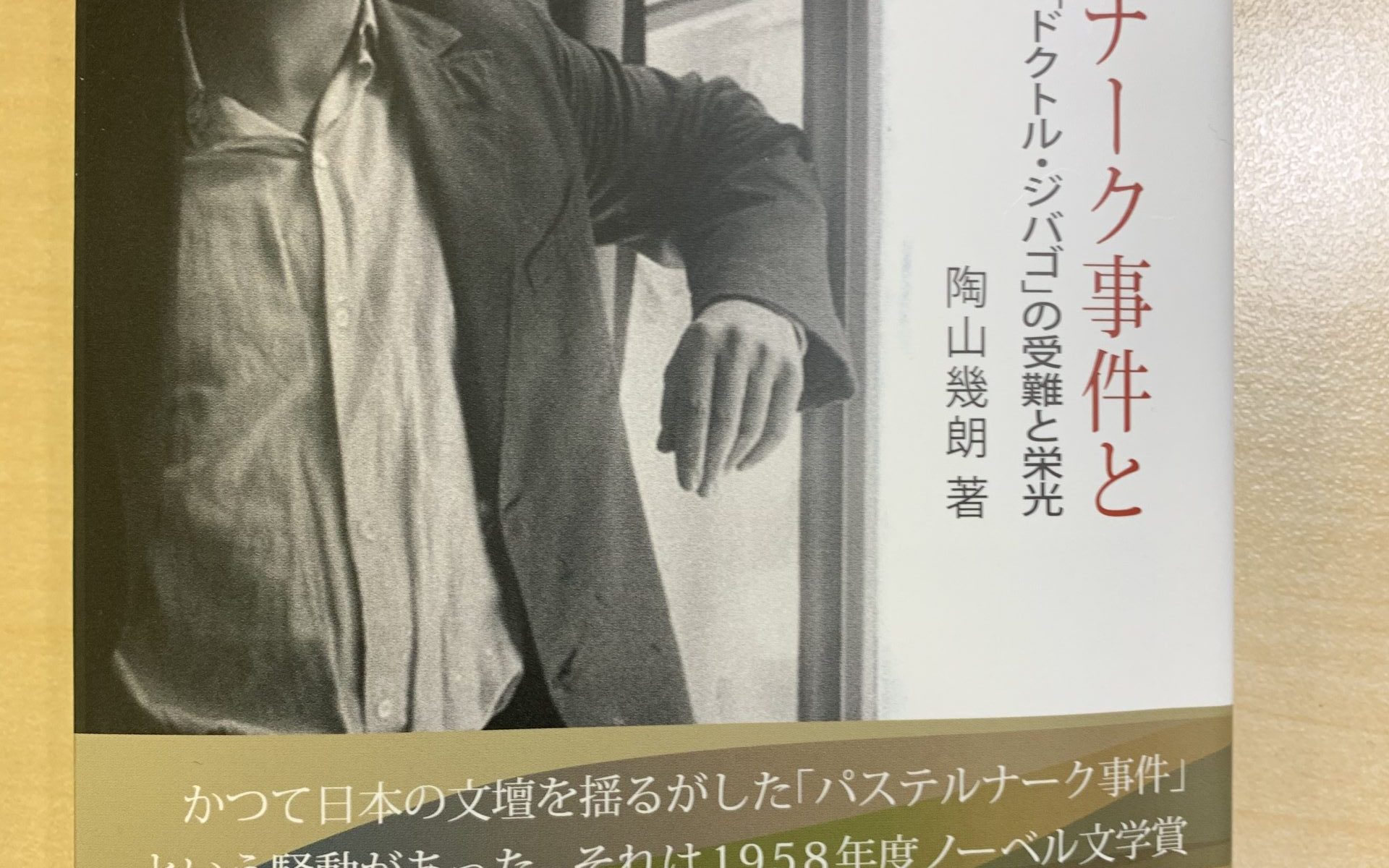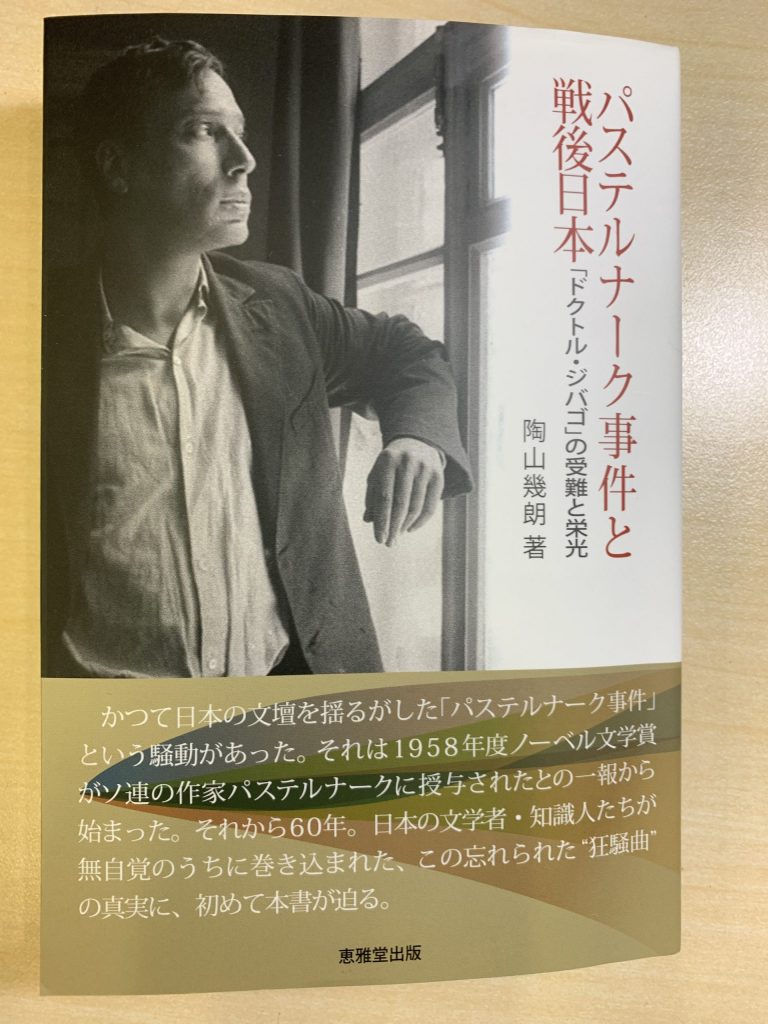WST National Gallery Copyright par Duc de Matsuoqua
こんにちは 大分の三浦先生です。
この3月1日から、日本経済新聞の最終面の名物「私の履歴書」で、段ボールの最大手レンゴーの会長兼社長の大坪清氏(1939~)の武勇伝が連載されています。賢い渓流斎さんのことですから、既にお読みになっていることでしょう。
本日(3月6日)も名前が出て来ますが、大坪氏の入社試験で面接した住友商事の社長だった「津田久」という方は、大変面白い人物です。連載の前回に書いてありましたが、住友商事は、財閥の商社の中でも後発で、戦後の昭和20年11月に「日本建設産業」の名称でスタートしました。知らなかったでしょ?当時は「十大商社の9番目」。住友金属(現日本製鉄)関係との取引が際立つ「鉄鋼商社」とも言われていました。それを総合商社として大きく成長させたのが津田久です。
もう一人、 摂津板紙の創業者である 「増田義雄」 も出てきますが、彼も大変喧嘩早く、今のITか何かの青年実業家なんかと違って、アクが強く、新聞・雑誌記者たちがその逸話を取り上げるだけで、下手な文章でも、輝き出すような取材対象です(笑)。
津田久も、その前の社長で事実上の住商を創業した「田路舜哉(とうじ・しゅんや)」も東京帝大出身で、卒業後、住友本社に入り、戦後の住友グループの事業拡大に尽力があった逸材です。
田路は、「ケンカ、とうじ」と言われたり、名刀のように切れるので「村正」と言われたり、まあ、凄いあだ名がついた面白い逸材です。
住友グループの原点の別子銅山に関連して、「別子三羽烏」など綽名もついていたそうで、それだけ、個性のある人物が数多いたわけですね。

田路の上司で、田路を可愛がった「鷲尾勘解治(わしお・かげじ)」は、住友本社の大幹部で、別子銅山の最高責任者だったのに、住友本社と対立して、住友を去ります。鷲尾は「鉱夫の気持ちが分かるには自分も鉱夫にならないとダメだ」と自ら鉱夫になって懸命に働き、同時に別子銅山の鉱脈の将来性も見通し、次の事業展開も考えていたそうです。
田路もそうした気風の継承者で、叙勲も固辞しています。まあ、皆さん、信念と気骨のある人ばかりですね。そういう残影に多少でも接した大坪氏だけに、「私の履歴書」には人間味のある逸話が多く出てくるのです(笑)
えっ?大坪清も増田義雄も津田久も田路舜哉も鷲尾勘解治も初めて聞く名前ですか?ああたのことですから、すぐ、ごっちゃになって、津田清とか、大坪義雄とか、言い出すことでしょう(笑)
政界も財界も官界も文学界も、人物の逸話が面白いのです。「こんな人がいたんだ」「こういう人たちのお蔭で今の我々がいるのだ」などと、歴史から学ばなければいけません。渓流斎さんも、政治家や財界人を毛嫌いせずにジャンルを超えて知らなければなりませんよ。