 Paris
Paris
どなたか分かりませんが、コメント有難う御座います。毎回、正座して拝読させて頂いております。
「獅子身中の虫」さんは、小生より遥かに学識教養が高いのに、いつも熱心に非才のブログをお読み頂き有難う御座います。
また、先日「忍どす」さんのアドバイスで、冷却ファンの出口に詰まったゴミを掃除したところ、作業の途中で電源がプツリと切れることがなくなりました。どうも有難う御座いました。(よおし、ウイルスバスターが有効の2017年までこのパソコンをもたすぞー)
さて、パリでの同時多発テロ以降、日本人のフランスへの旅行がキャンセルされて減り、日本からパリへの直行便も減らさざるを得ないというニュースをやっていました。
僕は、天邪鬼ですから、こういう時こそ、またパリに行きたいとウズウズしてしまったのですが、恐らくこの夢は一生叶うかどうか…。
ということで、空想でもいいから、パリに行きたいと思い、鹿島茂著「パリの秘密」(中央公論新社=2006年初版)を地図を片手に読んでいます。
何で地図を?かと言えば、「パリの歴史探偵」を自称する著者が探し当てる「スポット」は、ほとんどガイドブックに載っていない。それどころか、フランス人、いやいやパリジャン(パリジェンヌ)すら分からない歴史的モニュメントを探し当てて、微に入り細に入り、細密に描いているからです。(何しろ、当地に住むむパリの住民すら、尋ねても「知らない」と答え、著者が東京に戻って「パリの建築物事典」で調べ直して納得するぐらいですから)
まあ、マニア向けに書かれているために、私のようなトーシローにとっては、急に「ケール広場」だの「ヴィスコンティ通り」だのと、出てきても、一体それが何処にあるのか、何区でさえ分からないのです。しかし、私には、ムフフフ…、強力な武器があります。L’INDESPENSABLE社の「PLAN PLASTIFIE PARIS」があるのです。これは、昨年3月に一人でパリ旅行を敢行した際、地下鉄「マビヨン」駅近くの本屋で買ったのです。出版社名の’INDESPENSABLEは、「必要不可欠」という意味。(こんな言葉を社名にするとは!)タイトルは、強いて言えば、「プラスチック加工されたパリ地図」。つまり雨に濡れても平気なように紙が加工されているのです。
この地図は是非お勧め(10.10ユーロ)。パリ20区すべてのほか、「自転車道路」や「博物館」なども載っているのです。(ただし、鹿島教授がこの本で紹介する博物館は、この地図にさえ索引にも出てきません!)
また、脱線しますが、地図をパラパラめくっていると、至る所に「H」のマークがあり、最初は「さすが、観光都市パリ。何処にでもホテルがあるんだなあ」と思ったら、よく見たら、この「H」は、ホテルではなく病院(Hopital)だったんですね。やはり、パリでも病人が多いんですね。
さて、やっと「パリの秘密」の話です。面白かったところを箇条書きで引用させて頂くことにします。(換骨奪胎)
・フランスで「ライオン」の存在が知られる前の中世では、「百獣の王」は熊で、王侯の中には、実際に熊と猛犬と戦わせて、熊が犬になぶり殺されるのを楽しみにしていたシャルル9世のような王がいた。
・ジェットコースターのことを、フランス語で「ロシアの山」(montagne russe)という。これは、ジェットコースターの元祖のようなものが18世紀末にロシアから入ってきたため。(人工の山にレールを敷いて、急勾配をトロッコを遊具に使って降りてくる)これが、フランスからアメリカに渡り、今や世界中の遊園地でヒットするようになったとか。(ちなみに、英語ではジェットコースターのことを roller coaster と言うのに、この和製英語は誰が考えたのでしょうね?)
・世界各地でバラバラだった度量衡が「メートル法」に統一されたのは、フランス革命の影響だが、メートル法を浸透させるために、「メートル標準器」をパリには16か所設置したが、現存するのは二つだけで、そのうち元の場所に原型のまま保存されているのは、6区のヴォージラール通り36番地の標準器のみ。
・サン=ジェルマン・デ=プレ地区のヴィスコンティ通りは、バルザック、ラシーヌ、ドラクロワといったお札になるクラスの超大物たちが喜びと悲しみの日々を送った通り。
・サルトル、ボーボワール、ボードレール、モーパッサンらが眠るモンパルナス墓地を散策すると、メーヌ大通り寄りの場所にサイロのような場違いな建造物が見えるが、これは「シャリテの風車」の跡。モンパルナスもモンマルトルもかつては風車小屋だらけだった。
・モンマルトルにある「ステュディオ28」は、1928年に開館した映画館で、ルイス・ブニュエルの「アンダルシアの犬」などを上映するなど「シネマの聖地」と呼ばれている。1930年に独占封切りされたブニュエルの問題作「黄金時代」がスキャンダルとなり、右翼団体が乱入し映画館を破壊する騒ぎが起きる。しかし、経営者が変わり、紆余曲折を経て、今も健在だとか。
・パリの歌舞伎町ともいえるピガール広場からヴィクトル・マセ通りに通じるアヴェニュ・フロショーには、ヴィクトル・ユゴー、ロートレック、ルノワールの息子で映画監督のジャン・ルノワール、それにシルヴィー・バルタンらも住んでいた。
・シテ島のオテル・デュ(市民病院)の敷地は、かつては有名なデパート「ベル・ジャルディニエール」があり(パリ大改革を行ったオスマン卿の強制移転)、それまで、男性用背広はオーダーメイドが当たり前だったときに、既製服を破格の値段で売り出し、大ヒットした。
・ノートル・ダム大聖堂は長蛇の列ができる観光名所だが、通りを挟んですぐ近くにある「ノートル・ダム博物館」はいつもガラガラ。(ガイドブックに載っていないせいか?)ここには、意外にもナポレオンや一族の肖像画などが展示されている。その理由は、ナポレオンは、大革命以後に、カトリック信仰をコンコルダート(世俗権力者と教皇との政教協約)によって復活させたキリスト教徒にとっては大恩人。だからこそ、ナポレオンの戴冠式は、ノートル・ダム大聖堂で行われた。
以上、まだまだ書きたいことがいっぱいありますが、長くなるのでこの辺で。
 久しぶりの焼き肉屋さん
久しぶりの焼き肉屋さん
 Dekkaido
Dekkaido Monouquenochara
Monouquenochara
 松島屋の豆大福
松島屋の豆大福 日新堂のマドレーヌ
日新堂のマドレーヌ
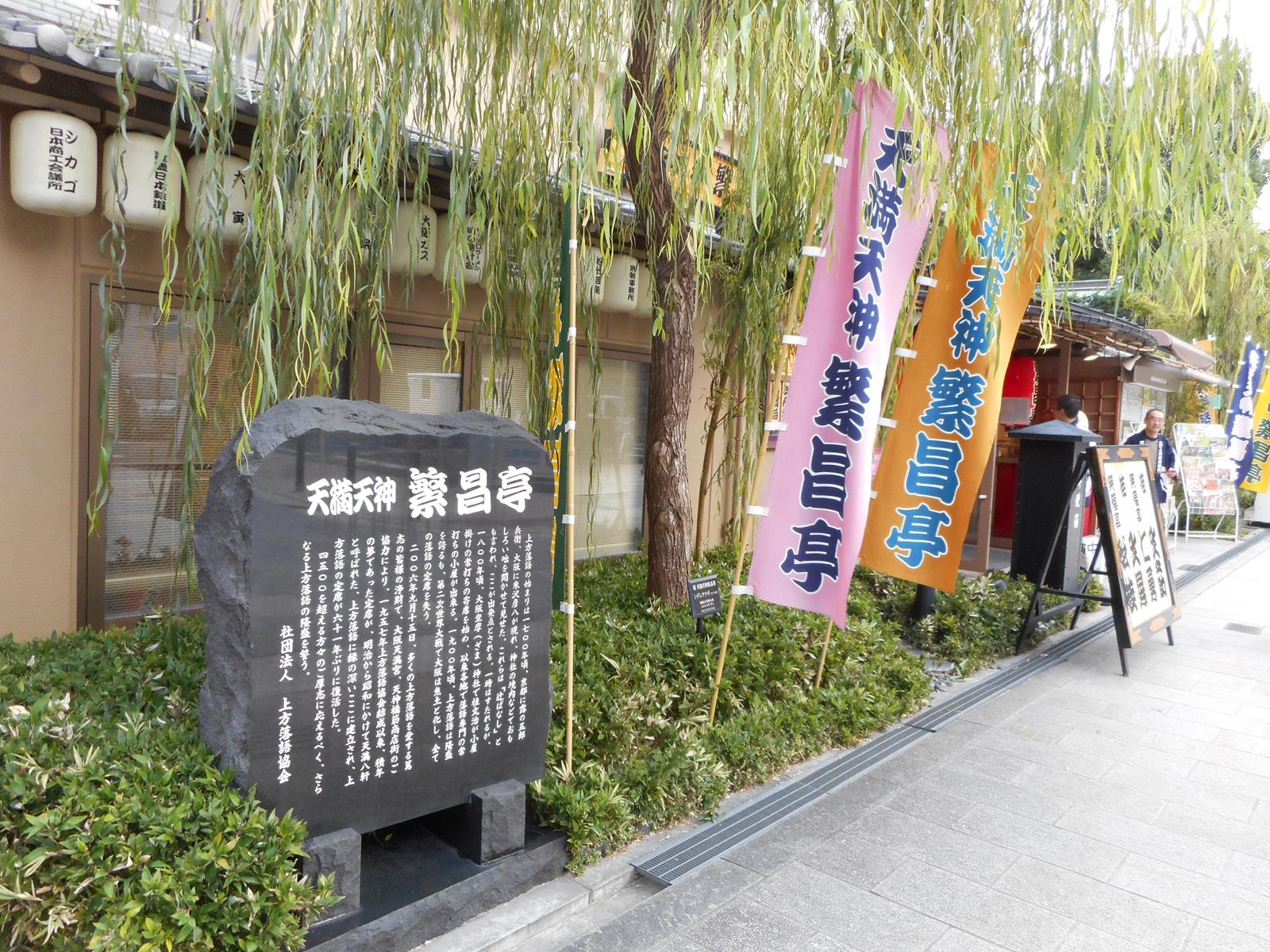

 「亥の子餅」
「亥の子餅」