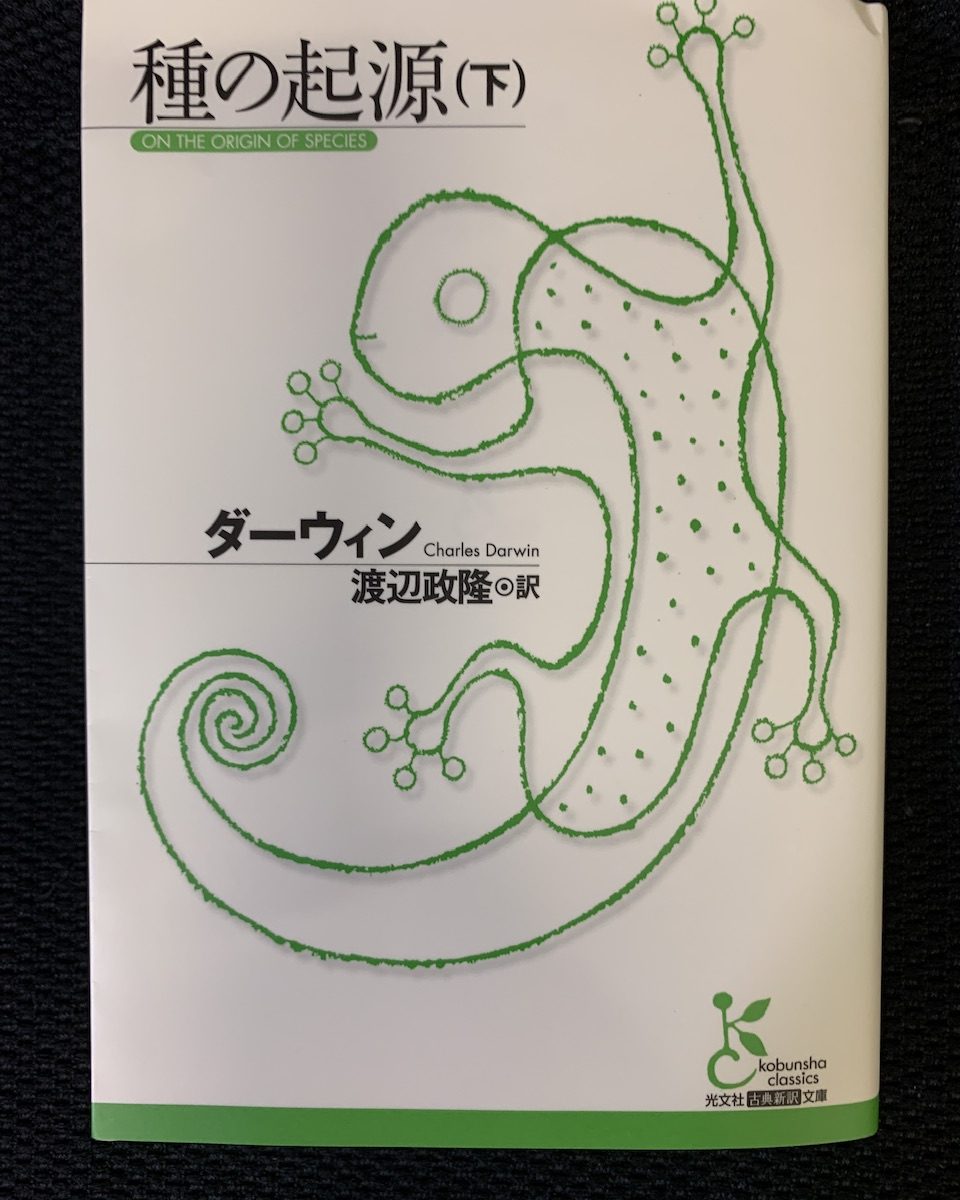「わーお、やったーー」。通勤電車の中で一人、心の中で快哉を叫んでしまいました。ダーウインの「種の起源」(渡辺政隆訳、光文社古典新訳文庫)をついに、やっと読了出来たのです。ハアハアと3000メートル級の高山を登頂できた爽快感と疲労感が入り混じったあの感覚が押し寄せて来ました。
「種の起源」は1859年11月24日に初版が発行され、ダーウインはそれ以降、13年間も地道に改訂作業を続け、1872年2月に「第六版」まで出版しました。訳者の渡辺氏によると、ダーウィンと言えば直ぐに連想できる「進化」evolution という言葉は、この最後の第六版になってやっと出て来た言葉だといいます。(それまでは「変異を重ねて来た」といったような表現。)また、ダーウィン主義のキーワードとなる「適者生存」も、1869年の第五版になって初めて登場したといいます。「進化」も「適者生存」も社会学者のハーバート・スペンサーが命名した造語でした。

いわゆるダーウィンの進化論は、今や定説になっていて疑問の余地はないと私は思っていましたが、今でも、キリスト教原理主義者だけではなく、科学者の中でも反ダーウィン主義者がいるとは驚きでした。訳者の渡辺氏も「あとがき」の中で、同氏が1970年代の前半、大学の生物学の最初の授業で、高名な教授から「ダーウィンの『種の起源』は読む必要もない。あそこに書かれているのは嘘ばかりだから」と聞かされたといいます。
ダーウィンの進化論とは、一言で言えば、「全ての生物は共通の祖先から進化してきたという考え方」で「生物の進化は世代交代を経た枝分かれの歴史であって、一個人が進化することはありえない」ということになります。しかし、「種の起源」は決して読みやすい本ではなく難解のせいか、正しく読まれずに、ダーウィンの業績も正しく評価されないまま、学界で論争を生んだのではないか、と訳者の渡辺氏は書いております。
なるほど、そういうことでしたか。「種の起源」の最後は「実に単純なものから極めて美しく素晴らしい生物種が際限なく発展し、なおも発展し続けているのだ。」という文章で終わっています。「種の起源」第六版を出版した時のダーウィンは63歳になっていました(その10年後の73歳没、ニュートンやヘンデルら著名人が眠るロンドンのウエストミンスター大寺院に埋葬)。

この難解の書物を私自身、どこまで理解できたのか心もとないのですが、読破できたことだけは自分自身を褒めてあげたいと思っております。「種の起源」を読まずに進化論を語る勿れですね。
訳者の渡辺氏も「解説」の中でこう書いています。
進化の起こり方は、常に偶然と必然に左右され、行方が定まらない。あらかじめ定められた運命など存在しないのだ。生存することの意味を問う中で虚無に走るのは容易い。しかし、偶然が無限に繰り返された結果として人生は存在するという考え方には荘厳なものがある。「種の起源」を読まずして人生を語ることができない。
これ以上、付け足すことがないほどの名言です。