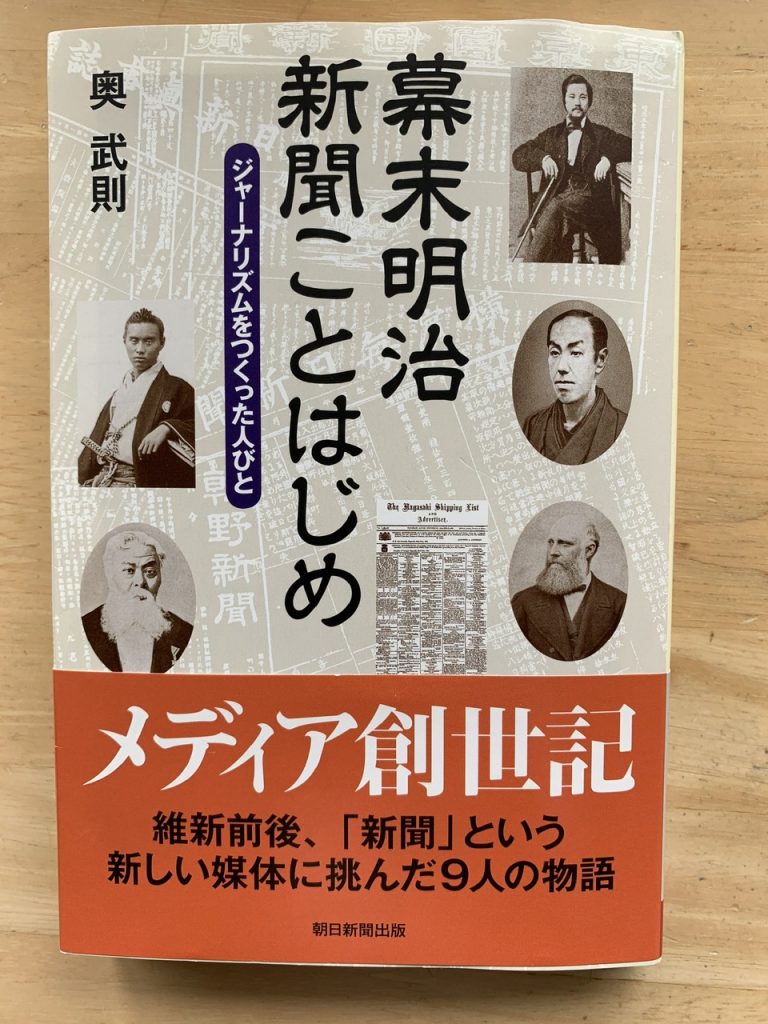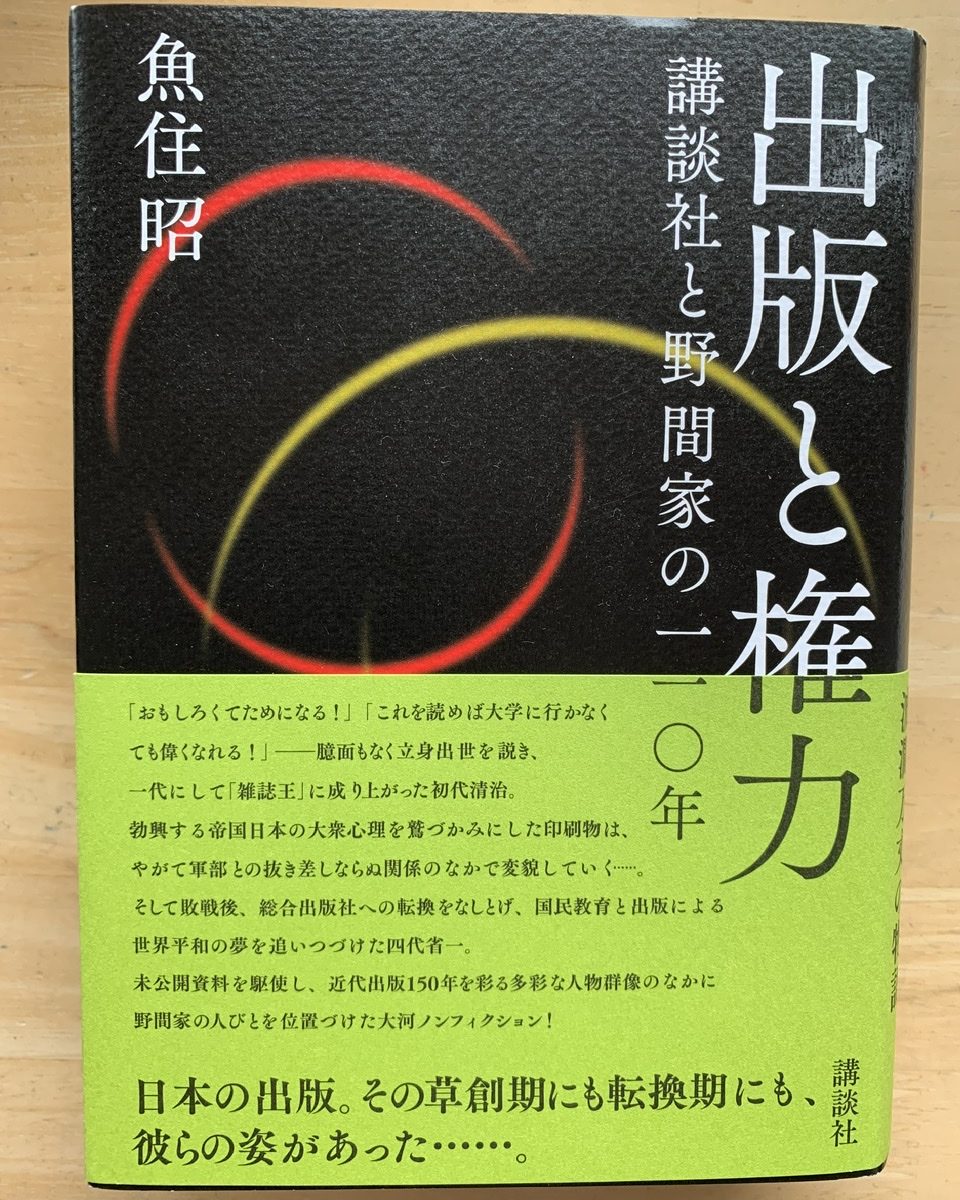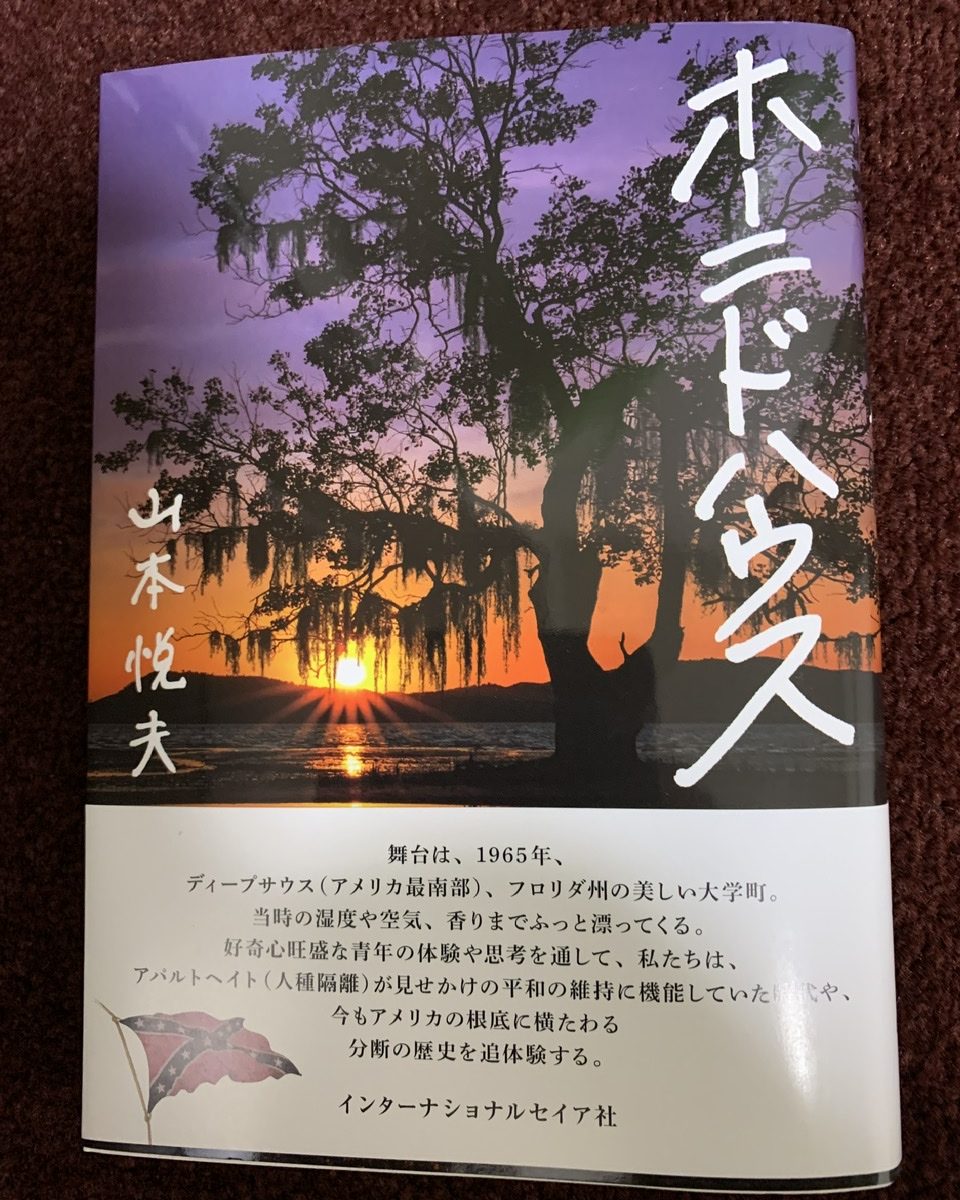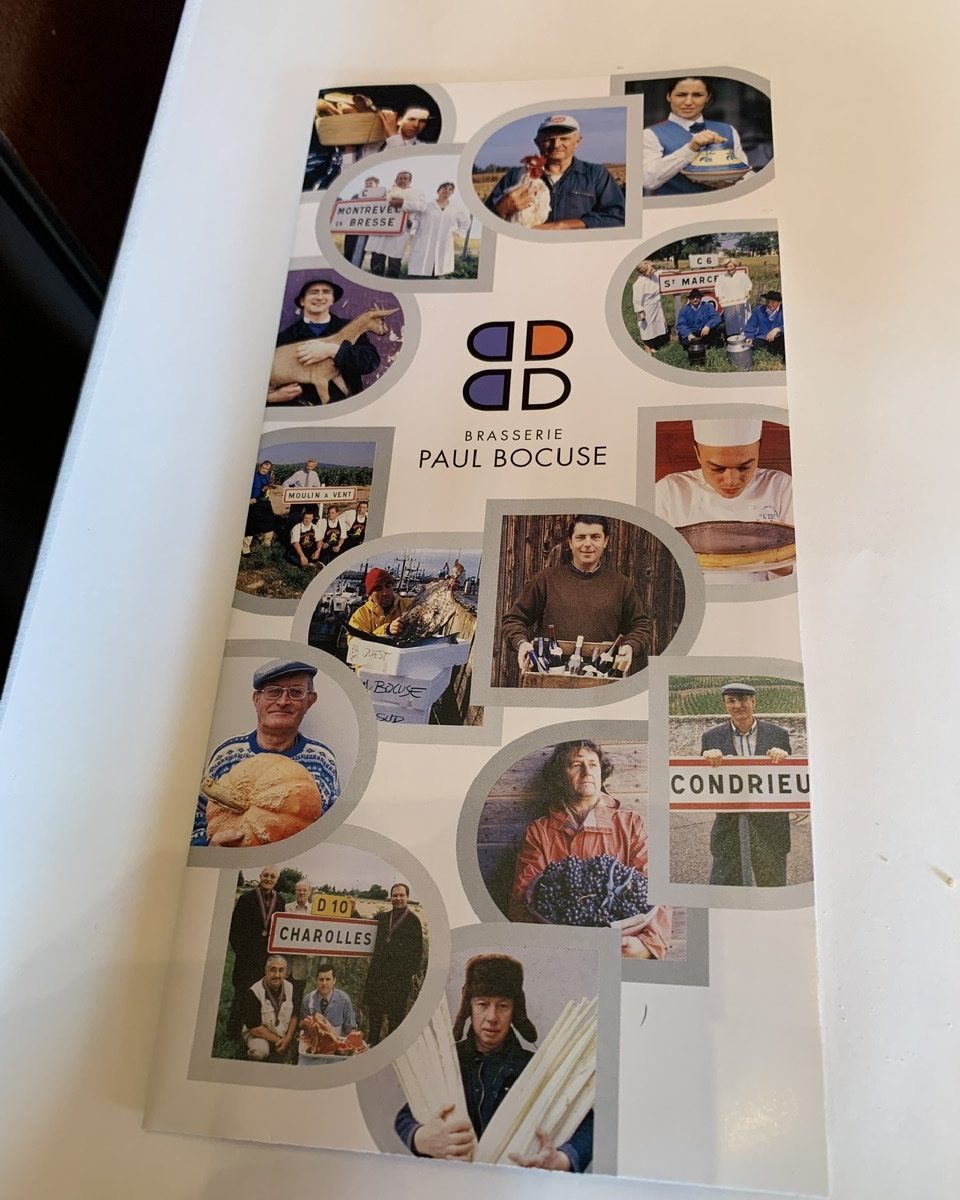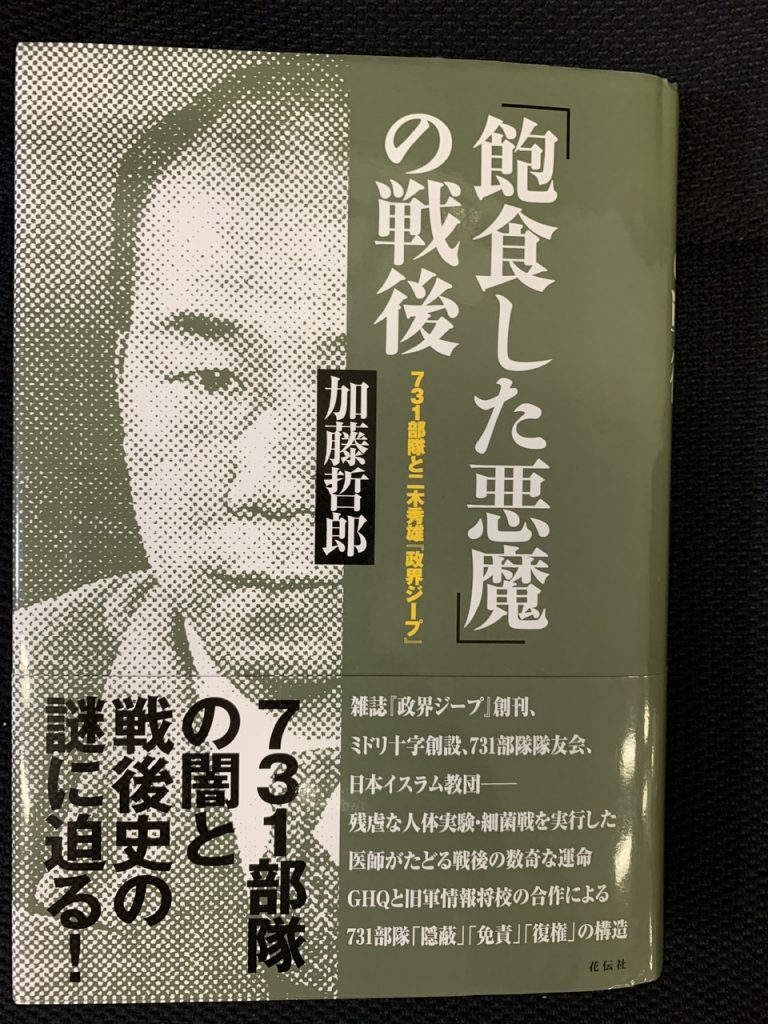昨日は、このブログで、インパール作戦の最高司令官・牟田口廉也中将のことを書きましたが、彼がいくら「部下のせいで失敗した」と自説を主張しようと、9万2000人もの将兵をビルマの山岳地帯に置き去りにして、自分だけ一人で飛行機で逃げ帰ったのは歴史的事実です。
彼は、この作戦で2万3000人もの将兵が戦死(主に餓死)したというのに、一切責任を取りませんでしたし、陸軍上層部も彼に責任を問わず、帰国後は陸軍予科士官学校長に栄転させています。
日本人は、戦前も戦中も戦後も、トップは自分の責任を取らないし、責任を問われないということが、日本のお家芸であり、伝統であるという良い見本をみせてくれています。(となると、コロナ感染拡大について、菅首相が責任を取ることはないことは、容易に分かります。)
戦前戦中は、今では考えられないほどの階級社会であり、エリート階級とそれ以外の庶民では天と地の違いがありました。将軍が雲の上の神さまなら、一兵卒は将棋の駒どころか、奴隷以下です。将軍ともなると、中には兵隊の人命など虫けら以下、と考えていたことでしょう。だから、インパール作戦のような無謀な作戦が立案できるのです。
牟田口廉也は、何十倍もの競争率を勝ち抜いて、陸軍士官学校~陸軍大学を出たエリート中のエリートです。恐らく幼年時代は、「神童」と周囲から褒められたことでしょう。超秀才です。しかし、学業成績が良いとか偏差値が高いといったエリート教育だけでは、国家を破滅させるほど弊害があることが、牟田口の例を見ても実証されています。
先日、面白い記事を読みました。西垣通東大名誉教授が書いた「天才ノイマンの悪魔的価値観」です(8月11日付毎日新聞夕刊)。ノイマンとは原爆を開発したマンハッタン計画に参加した天才科学者ジョン・フォン・ノイマン(1903~57年)のことで、その驚嘆すべき業績は、原爆だけではなく、人工知能など現代情報通信技術にまで広く及んでいます。ただ、ノイマンの思想にあるのは、徹底した科学優先主義と犠牲を顧みない非人道主義で、普通人の苦悩には無関心だったというのです。この下りを読んで、牟田口のことをすぐ思い起こしました。牟田口も成績優秀の秀才だったことでしょうが、犠牲を顧みない非人道主義者で、一兵卒の苦悩には無関心だったということです。
つまり、頭の良さと人格、思いやり、優しさ、品性とは一致しない、ということを私は言いたいのです。天才に限って、不幸だったり、浪費僻や性格が悪かったりします(笑)。

フランスのマクロン大統領も、最近、エリート教育の弊害に目覚めたらしく、自分の出身校でもあり、超エリート教育校で高級官僚の養成機関として知られる国立行政学院(ENA)の廃止を今年4月に表明しました。
でも、私はエリート教育の反対者ではありません。試験で良い成績さえ取れば、たとえ貧乏な家庭に生まれようが、爵位がなく、卑しい家系であろうと(注=差別用語なのですが、あえて)、上流国民に這い上がれるからです。人間生まれながらにして不平等であり、親を選んで生まれてくることはできません。本人の努力で、しかも、試験で、チャンスをもらえるなら利用しない手はありません。
ただ、エリートは何でも優遇されますから、本人が気が付かないうちに傲岸不遜となり、他人の犠牲はやむ得ないという思想になることでしょう。軍人とは言っても、高級官僚ですから、自分自身は、最前線に出ることなく、血の雨も見ることはなく、安全地帯にいて、飲食の心配をすることもないからです。
ですから、エリート教育だけではなく、落ちこぼれた人への敗者復活の機会や場所の提供、セイフティネットの充実と福祉事業も必要です。何よりも、傲慢なエリートたちの所業をチェックする機関とその人材育成も大切でしょう。となると、江戸時代の目付役のようなものも必要でしょうが、批判精神を持ったジャーナリスト、操觚之士の出番です。ジャーナリズムがその国の民度を表すというのは、正鵠を得ているのではないでしょうか。